表紙ページへ
background
脳(な づ き)
![]()
![]()
(はじめに)
「Εν αρχη ην ο λογος ,και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος.(始まりの源は言葉だった。そして言葉は神へ。そして言葉は神だった」(『新約聖書』「ヨハネ1:1」)。
日本語の「かみ(神)」は希求とその対象化を表現している。なぜ言葉は神となったか、言葉が神となるとは人間にどのようなことが起こることなのか、がここでの問題である。すなわち 本書の主題は神であり言葉である。神たる言葉。言葉たる神。
以下、以下に述べられる項目とその内容を簡単に記す。
以下、本書は四つの部に分かれている。
すなわち。
・第1部 脳
脳の機能が総合的全体的に簡単に触れられる。
・第2部 脳ニューロンの反応としての言葉
脳ニューロンの反応たる言葉の見地から、言語が自然言語と非自然言語の二種に分類される。
・第3部 音を感じる中枢として考える言語中枢と光を感じる中枢の関係――音と光・聞くことと見ること――
音覚中枢たる言語中枢と他の全知覚中枢という観点から、言語はさらに二種に分類される。
以上の分類により、言語作用の本質的部分が知られる。
・第4部 脳・言語・神、そして時間
そうした言語作用の本質によって人に起こる“ある状態”に関し述べられる。
![]()
脳は複雑な立体交差のようなものである。立体的で複雑な通路に様々な方向から様々な情報が入り様々な方向へ出ていく。しかし、基本的にはただの通路である。脳が絶対的命令者であるかのような脳の擬人化は誤りである。そうした、情報の相互の関係のし合い方や影響のし合い方が人格や性格である。人格や性格は、情報それ自体ではなく、情報の相互の関係の仕方、関係のあり方なのである。
脳は神経の末端が肥大化したものである。神経の末端の肥大化した部分が漠然と「脳」と呼ばれている。どこまでが脳であり、どこからが脳ではない普通の神経なのかの限界は曖昧である。脳その他の神経系は発生的には外胚葉を起源としている。皮膚もまた外胚葉を起源にしている。それも、外胚葉を起源にしているのは、内側の真皮ではなく、最も外側の外皮である。人間の体において、風や日の光に触れたり、ほかの人の肌に触れたりする部分である。内側の真皮は中胚葉が成長したものであり、その外側の外皮と脳その他の神経系は外胚葉が成長したものなのである。受精卵の成長過程(これを「発生」と呼ぶ)は生命体の進化の過程を短期間になぞり繰り返すといわれているが、そうした、受精卵の成長過程を見たとき、発生起源的には脳その他の神経は皮膚と同じであり、皮膚は脳その他の神経と同じなのである。発生起源のレベルで言えば、皮膚は脳であり、脳は皮膚なのである。それは、人間という生命体の内側に由来する情報と外側に由来する情報の接点であり、相互交渉の場であり、様々な複雑な相互関係を機能する器官なのである。それが脳である。もっとも、脳だけではなく、生命体自体がそうした相互関係を機能する器官なのかもしれない。脳はもちろん、神経系自体の無い生命体もある。
人間が考えたり感じたりするとき脳ニューロンが反応している。それは脳のニューロン(神経細胞)に電流が流れているのだということは広く知られている。脳ニューロンは、根が生えたような妙な形をしているが、基本的には、一つ一つが一個一個の細胞である。肛門で糞まみれになっているのもひとつの細胞であり、哲学や数学などを考えて反応している脳ニューロンもひとつの細胞である。基本的にはみな同じである。
脳ニューロンにどのようにして電流が流れるかというと。「ニューロン」と呼ばれている細胞の内側と外側のイオン濃度が普段と違う状態になり、それが電気的変化になる。脳のニューロンの活動は、普段と違う状態が生じ、それをまた普段の状態に戻そうとするような動き、調和を破壊してまた調和を得ようとするような動きなのである。ニューロンには興奮性の、プラス性の、ニューロンだけではなく、それとは逆の、抑制性の、マイナス性の、反応を示すものもある。それらが相互に全体的に関係し合い全体の調和を保とうとしているわけである。しかし、限界を越えた過大な(或いは過小な、つまり、過大にマイナスな)刺激を受けると、抑制性のニューロンが或る瞬間とつぜん興奮性のニューロンになったりすることもある。ニューロンの抑制が働かなくなるのである。脳に入ってくる情報によってニューロンの反応の仕方がおかしくなってくるわけである。
脳生理学に脳の局在論がある。脳のこの部分は記憶をつかさどる中枢であるとか、食欲や性欲をつかさどる中枢であるとか、運動をつかさどるとか、運動の中でも、ここは手の運動の中枢であるとか、足の動きの中枢であるとかいうものである。この局在論は、脳の働きを考えるには非常に参考になり、脳の病気の治療などにはとても重要なことなのであるが、脳の全体的・総合的な把握ではない。
脳の機能は模式的に前脳((右脳・左脳共通に)中央溝から前の部分)・後脳((右脳・左脳共通に)中央溝から後ろの部分)、右脳(前脳・後脳を問わず)・左脳(前脳・後脳を問わず)、上脳(表面脳)・下脳(奥脳)にわけて考えることができる。
前脳((右脳・左脳共通に)中央溝から前の部分)は人間の内側の情報というか、刺激というか、とにかく人間の内側が外側へ(環境へ)むかって能動的に関係していくような働きをする部分である(全体的にそういう働きの中枢になっている)。運動として環境へ働きかけ能動的に未来へ働きかけるような働きをする。脳の前の方には前頭葉がある。推測や予測やそれへ向かって努力する目標といった、未来的なことをつかさどる中枢である。この前頭葉の発生起源は嗅覚中枢である。なんとなく怪しいことを「その話はクサイ」などと言ったりするのも前頭葉の本質をよく表している。嗅覚は極めて原始的な感覚であるが、未来的でもある。逆に言えば、未来は原始的な感覚で察知するものである。
後脳((右脳・左脳共通に)中央溝から後ろの部分)は視覚器官や聴覚器官その他を経た外的刺激(人間の外側たる環境に由来する刺激)に受動的に作用してそれらを処理する働きをする部分である。何かを記憶するといった過去的な部分でもある。
右脳(前脳・後脳を問わず)は全体を総合的にとらえる即自的(主観的)な働きをする部分である。疾病自覚性欠如、すなわち、脳に病気や傷害が生じているにも拘わらず、そうした病態が無視される状態――つまり、脳自体が脳自体の病的異常に気づかないという状態――は右脳損傷の場合に多いという医師による観察報告がある。つまり、自分の異常性というか、脳自体の脳自体の異常に気づく機能(脳自体が脳自体の異常に気づく機能)は右脳(非言語脳)にあるわけである(脳自体の異常に気づく機能に損傷が生じる結果、脳が脳自体の異常に気づかず、疾病に関し自覚が生じないわけである)。
左脳(前脳・後脳を問わず)は反省的に分析するような対自的(客観的)な働きをする部分である。
上脳(表面脳)は、上へ上がるほど(あるいは、脳の表面へ行くほど)原始的な生命体から人類へ、さらには具体的な個人へと向かっていくような、生命個別的な(一つ一つの生命体の個別化へと向かっていくような)反応をつかさどる部分である。或る具体的な人間の個性はこの最も表面の薄皮的部分の問題である。
下脳(奥脳)は、下へ下がるほど(あるいは、脳の奥へ行くほど)、食欲や、睡眠欲や、性欲や、呼吸、あるいは、心臓の鼓動や内分泌(ホルモン)などの自律系、といった、生存衝動というか、生命反応自体というか、そうした、生命体としての普遍的な反応へと向かっていく、生命普遍的な反応をつかさどる部分である。
ただし、右脳と左脳は(言語中枢は多くの場合左脳にあるが、まれには右脳にある場合もあるように)機能が空間的に左右が入れ替わっている場合もあり、この表現はあくまでも典型的・模式的なものであって、各部分の境目も解剖学的に明確な一線をひけるものではない。たとえば、上脳と下脳の境目は視床下部あたりであるが、この部分は、個別生命体としての反応と普遍生命体としての反応の橋渡し的な、中間領域的な働きをしている。脳の働きを総合的・典型的・模式的に表現すればそういうことになるということである。 そうした、前脳・後脳、右脳・左脳、上脳・下脳が、立体的・全体的に調和をめざして動いていくのが脳の働きである。それは、人間という生命体の内側と、「環境」や「(人間に対する)自然」と呼ばれる外側との調和である。その場合、あらゆる人間はあらゆる人間にとって外側の環境にもなるという点も注意が必要である。人間関係の問題である。脳は、人間という生命体の内側と外側の中間領域にあり双方の情報を相互関係させる、人間と環境の中間領域にあるような器官である。機能としてそうなのである。人間の内側と外側の情報や刺激が相互に立体的に交流しあう回路、場(ば)―それが脳である。 「ノウ(脳)」は中国語であるが、日本語というか、外国語の影響を受けていない和語ではこれを「なづき」という。『華厳音義私記』という奈良時代の書物にもそう書かれている。「なづき」の語源は「なあとつき(名跡付き)」である。音(ね)たる私の記憶の思念的作用のあるところ。つまり「な(名)」が働くところ、言葉が生まれるところ、という意味である。古代の人たちもそれが脳だということを経験的に気づいていたのである。たいしたものである。しかし、そういう名が生まれるということは、脳はそういうところだぞという、古代からの警告でもあるだろう。
![]()
ここでは言葉を脳ニューロンの反応として考えていただきたい。わざわざこのようなことを言うのは、人間は、喋ったり、聞いたり、読んだりするときには脳ニューロンの反応など意識しないからである。しかし、そういうときにも脳ニューロンは絶え間無く反応しているのである。それを意識していただきたい。ただ、そうなっているのだという自覚をもって意識してくださればそれでよいのである。具体的にどのように反応しているかなどは知っている必要はない。神がどのように生まれるのかを知るにはそういう姿勢が必要なのである。
脳ニューロンの反応として言葉を考えた場合、神がどのように生まれるのかを知るために欠かせない、極めて重要な事実は日本の角田忠信氏により発見された。
外的知覚(人間という生命体の外部に由来する知覚)と内的知覚(人間という生命体の内部に由来する知覚)の相互関係を機能する器官として神経系があり、その中枢として脳がある。
外的知覚の要素としては、光や、音や、匂いや、味や、物質それ自体やその作用(その作用とは熱のことである)がある。つまり、感覚で言えば、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚である。
しかし、重要なのは、やはり、光と音―すなわち視覚(光覚)と聴覚(音覚)である。
光は、それが波動なのか粒子なのかはよく知らないが、視覚は、つまり、見ることは、存在自体を、すなわち、「在(あ)る」という疑惑の無い状態を、生じさせる働きをする。見たものは在るのである。「百聞は一触に如かず」や「一味に如かず」などとは言わず、「一見に如かず」というのも見ることの効力を表している。つまり、光(視覚・光覚)は、それに他のあらゆる知覚を代表させてよいような、(あらゆる知覚の総合的結果として「在る」という状態が生じるわけであるから)存在知覚(存在を生じさせる知覚)と言ってよいような、作用を果たす。
聴覚(音覚)がなぜ重要なのかというと。言葉は音(おと)だからである。言葉は声帯を振動させるなどして口から発する音である(囁きの場合には声帯は振動しないが)。文字には光の刺激、つまり、視覚の問題が入り込むが、文字がある遥かに前から言葉はある。言葉は音である。音も言葉である。机をトントンと叩いて「これは言葉か」と聞かれれば、それは音であるが。「音(おと)」は言葉である。
角田忠信氏はもともとは耳鼻咽喉科の医師であり、東京医科歯科大難治疾患研究所の教授なのであるが、1960年代に、聴覚の遅延戻り音効果(遅延聴覚フィードバック・delayed auditory feedback:DAF)を利用して或る人間の言語中枢が脳の右側にあるか左側にあるかを判断する方法と装置を開発しその実用化を始めた。聴覚の遅延戻り音効果(DAF)とは―人間は喋るときには自分の声を聞きながら喋っている。聞きたくなくても自分の音声が頭蓋骨に響いて聞こえてしまう。耳を完全に塞いでも喋っている自分の声は聞こえる。ところが。電気的な操作その他何らかの理由により、その音声が0・125秒~0・25秒遅れて戻って聞こえてくると、人間はとつぜん失語症や言語障害に陥ったような状態になり、正常に喋ることができなくなる。それが聴覚の遅延戻り音効果(DAF)である。この効果はドラム演奏でモニター音を電気的に遅らせた場合にも起こる。つまり、音と運動の関係で一般的に起こる。それを利用して、鍵(キイ)を叩くとヘッドホンに音が聞こえるようにし、その音を二つのチャンネルに分け、一方のチャンネルで遅延音を聞かせることが出来るようにしておき、右耳・左耳双方に音を競合させながら、右耳と左耳それぞれの音の強さ(デシベル)を増大させたり減少させたりし、叩鍵(タッピング)の乱れから、或る種の音に関し遅延戻り音効果(DAF)が生じる音の強さを右耳と左耳で比較し、その音に関し右耳と左耳のどちらが主的に中枢として働いているかを調べるわけである。聴覚(音覚)神経は、右耳から入った音は左脳へ左耳から入った音は右脳へ行く交差タイプと、右耳は右脳へ左耳は左脳へと行く直行タイプの二系統が併存しているが、交差タイプの方が主的に有効に働いている。つまり、右耳がより有効に働いている音は左脳が中枢となって、左耳がより有効に働いている音は右脳が中枢となって、処理されているわけである。脳の音覚(聴覚)神経が主的に左右交差して進化した理由は、光覚(視覚)関係の神経は右視野の光は左脳へ、左視野の光は右脳へという交差した関係にあるので、右視野と右聴野の光と音は左脳へ、左視野と左聴野の光と音は右脳へ入れ、光と音、見ることと聴くこと、光覚系(視角系)と音覚系(聴覚系)の関係を調整し調和させようとする要請が働いているのだろう。
人間の言語中枢が多くの場合左脳にあることは、病気や事故による脳障害者の観察から、19世紀後半にはだいたい分かっていた。20世紀後半には、手術のために頭を開いた患者の無麻酔の脳を電気的に刺激して調べるといういささか乱暴な方法で実験的にもこれは確認され、左脳のどの部分に言語中枢があるかということもさらに詳しく確認された。しかし、この方法では手術前に言語中枢の所在(右脳か左脳か)を知りこれに対処することができなかった。そこでさまざまな判定方法が工夫され、脳の片側ずつに麻酔薬を注入するなどという方法もあるのであるが、そうした乱暴なこともせずになんとか判定できないかと工夫されたのが角田氏の方法である。これなら、手術が必要な病人や怪我人だけでなく、普通の健康な人の脳も調べられる。ところが、この方法が、我々が想像もしていなかった事実を明らかにした。それは、この方法と装置の性質からそうなった。たとえば、脳を片側ずつ麻痺させ、どちらの脳を麻痺させたとき言語障害が生じるかを観察する方法は、言語としての言語音が、右脳と左脳の、どちらの脳を中枢として処理されているかしか知ることができない。しかし、角田氏の方法は、その性質上、あらゆる種類の音に関して調べることができた。つまり、あらゆる人を、あらゆる種類の音を、調べることができる。
最初は言語音と言語音ではない電気的な機械音を調べてその結果を比較したりしたのであるが。さまざまな資料や他の人のさまざまな実験結果と比べてみると、どうも腑に落ちないことがあった。角田氏が日本人を被験者に母音(ぼいん)音に関して得た実験結果と、アメリカの学者がアメリカ人を被験者に母音音に関して得た実験結果がどうも合わないのである。母音音は言語音であるから当然言語脳(多く左脳)が中枢になりそうである。日本人はそうなるのである。ところがアメリカ人はそうはならないのである。アメリカ人の場合は母音音が非言語脳(多く右脳)が中枢になったり、実験結果が明瞭にあらわれなかったりする。そこで、角田氏自身、日本に在住する外国人をいろいろと調べてみると、アメリカ人やヨーロッパ人はすべて、母音音は明瞭に非言語脳が中枢になっているのである。そうなると、言語音と非言語音―言語である音(おと)と言語ではない音(おと)の違いは一体何なのだということになってくる。そんなときである。秋の涼しさが訪れたころ。角田氏の部屋の窓の外で鈴虫がコロコロと鳴いていた。この鈴虫の鳴き声が、学会に出す論文のことを考えていた角田氏の思考をどうも邪魔する。妙に気になり。角田氏はこの鈴虫の鳴き声を録音し、前に言った装置でその脳ニューロン反応の仕方をしらべてみた。鈴虫が「ボクを調べて」と呼んだのかも知れない。角田氏も日本人であるから。鈴虫にひかれるのである。そもそも、鈴虫が羽を擦って出す音を「声(こえ)」と表現すること自体日本的である。調べてみて驚いた。なんと鈴虫の鳴き声は言葉と同じように言語脳(左脳)で処理されていたのである。鈴虫の鳴き声は非言語音であるから非言語脳(右脳)のような気がする。しかしそうではないのである。言語脳(左脳)なのである。しかし、アメリカ人やヨーロッパ人を調べてみると、彼らにおいては、鈴虫の鳴き声は非言語脳(右脳)へ行った。なんだこれは……ということになる。さまざまな言語を母語にしているさまざまな民族に属す人々を被験者に、さまざまな種類の音に関して調べはじめた。すると、沢山の実験結果の集積から次のようなことが分かった。実験には年月もかかり、ひとつひとつ手間のかかる作業で試行錯語もあるのであるが、そうしたことは割愛し、結果だけをまとめると次のようなことがわかった。
すなわち。
◎日本語人(幼い頃から日本語で生活している人、あるいは、幼い頃には日本語で生活していたが今は他の言語で生活している人)とポリネシア系言語人(ポリネシア系言語に関し日本語人の日本語に対する関係と同じ関係にある人)は、言語音の他、言語以外の人間の声(赤ん坊の泣き声、人間の笑い声、叫び、ハミングなど)、人間以外の生物(動物)の鳴声(小鳥の囀りなども含む)、昆虫の発する音(コオロギや鈴虫の鳴声など)、海の音(つまり波の音)、といった音がすべて言語脳(多く左脳)の方へ行く。また、人工的に発される音でも、和楽器の音は言語脳へ行く。そしてそれ以外の音、たとえば、電気的に人工的に作られた音(ただし言語脳へ行く音を電気的に加工し人工的につくることもできる)、オートバイや自動車のエンジン音のような機械音、洋楽器の音(オーケストラ演奏も含めて)は非言語脳へ行く。人間の体を打つ音(つまり拍手)も非言語脳へ行く。
◎英語やフランス語その他ヨーロッパ系言語人(それらの言語に関し日本語人の日本語に対する関係と同じ関係にある人)、中国語人、朝鮮語人、(公表された資料からは明らかではないが多分アラビア語人も)は、子音と母音の複合した言語音、たとえば「pa(パ)」のような、は言語脳へ行く。しかし、「あー」と母音をのばした音の録音の一部を短く取り出して調べると、母音音は、言語音ではあっても、非言語脳へ行く。さらに、言葉以外の人間の声(赤ん坊の泣き声や笑い声その他)も非言語脳へ行く。また、人間以外の生命体の発する声や音(動物の鳴き声、小鳥の囀り、コオロギや鈴虫その他昆虫の鳴声その他)も、海の音のような自然界の音も、人工的な電気音も、機械音も、和楽器の音も洋楽器の音も―すべて非言語脳へ行く。
・この調査は地球上のあらゆる言語人に関して行われたわけではないが、この視点から分類された場合、この上記二種以外の言語は存在しないだろう。
・この実験結果は、たとえば、ヨーロッパ系アメリカ人を両親として日本で生まれ、日本語の言語環境で育ち、成人後、英語と日本語の双方を話せるが、英語の方が幾分得意、という状態の人間であっても日本語人型の反応を示し、逆に、日本人を両親としてアメリカで生まれ、英語環境で育った人間がヨーロッパ系言語人型の反応を示すように、生物学的意味での人種、すなわち遺伝的特性、脳の物的構成上の特性、によるものではなく、あくまでも言語作用によるものである。
・実験の際に用いられる音は、50~75ミリ秒(20分の1秒~13分の1秒)、ときには10ミリ秒(100分の1秒)といった瞬間的なものであり、被験者にはそれが何の音なのかはまずわからない。つまり、その反応は、音の種類を自覚的・意識的に識別してなされているわけではなく、脳ニューロンの反応として自動的に、オートマチックに生じている。
・その他、脳に言語音や非言語音を背景的に負荷した場合の変化、知的活動が、つまり(とりわけ抽象的)言語活動が、あまりに過度に永続的になされた場合(電気的人工音なども含めて)あらゆる音が言語脳側へ病的に偏倚する問題(日本人に関する所見のみ)、片側ずつにさまざまな種類の嗅覚刺激を与えた場合の変化(日本人とヨーロッパ人の場合の変化の違い)、単なる嗅覚刺激ではなく、「クラッ」となり一瞬麻痺するほどアンモニア刺激を与えた場合の(先程の病的偏倚者に及ぼす)作用、麻酔で片脳ずつを麻痺させた際に付随的に生じる躁状態や鬱状態の問題(それに関する日本人とヨーロッパ人の症状の違いの問題)など、角田氏はその他にも興味深い実験や問題提起があるが、基本から外れるのでそれらのことはここでは省略する。
角田氏の研究に関して以上に述べたことは、角田忠信著『日本人の脳』(大修館書店)にすべて書かれている。この本は、発見した事実の評価、すなわち、発見した事実をどう評価するかという点、そして、その評価の結果述べられる文化論や社会論、に関してはみるべきものはない。しかし、発見された事実それ自体は人類史的発見と言ってよいほど重要なものである。実は角田氏自身、ご自分が発見した事実の重要性があまりお分かりになっていないようなのである。しかし、考えようによってはこれは量子論や相対論よりも重要である。なぜなら量子論も相対論も言葉で表現され叙述されるわけであるから。
つまり。角田氏により発見された事実は我々に何を教えるかといえば。それは。言葉は音であるから。脳の言語中枢は広い意味で音覚(聴覚)中枢である。そうした、音(おと)がどのような脳ニューロン反応をひき起こすかという見地から、地球上の全言語を分類したとき、人類の言語は、(言葉以外の)人間の声、人間以外の生物の声、昆虫の羽の発する音(たとえば鈴虫の鳴声のような)、海の音といった自然音が音覚中枢としての言語中枢に作用する自然言語と、その音が自然界に無い音であればあるほど言語中枢を作用させる非自然言語との二種に分類されるということなのである。その結果、たとえば赤ん坊の泣き声が、或る人間においては言語脳に作用し、或る人間においては非言語脳に作用する。たとえばアメリカで生まれ、生まれたときから英語で生活している人間(国籍上はアメリカ人とは限らない)にとっては赤ん坊の泣き声や笑い声は機械音と同じただの雑音であったりただ注意をひくための踏切の信号音のようなものであったりするのに対し、日本で生まれ生まれたときから日本語で生活している人間(国籍上は日本人とは限らない)にとっては、赤ん坊の泣き声や笑い声は言葉なのである。
人類の言語には、自然音が言語になる自然言語と、それが自然に反していればいるほど言語になる非自然言語がある。
ただし、念のため言っておけば、その場合どちらがより優れた価値の高い言語であるかという議論は意味がない。
自然なものの価値だけを認めて人工のものの価値を否定するのは人間否定であって馬鹿げている。人工のものの価値だけを認めて自然なものの価値を否定するのは、人間も自然から生まれたのであるから、馬鹿げている。ただ、そういう事実があるのだということを知ればそれでよいわけである。
もっとも。それを知ることでさまざまな問題が出てくることもまた事実である。たとえば。自然言語・非自然言語(人工言語)双方の性質を備えた類型の人類普遍言語は原理的にあり得ないということ。あるいは。たとえば「始めは言葉だった」(「ヨハネ1:1」)と聖書が言うとき、その言葉は自然言語なのか非自然言語なのかということ……。
人類の言語には自然言語と非自然言語がある。
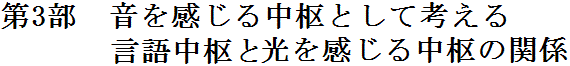
![]()
言葉はどういう働きをしているかを考えるには、音覚中枢としての言語中枢と他の知覚中枢一般がどのような関係にあるかを考えることが必要である。つまり、人間にとっての音と光、音覚神経系と光覚神経系、聞くことと見ること、との関係や、音覚神経系と触覚神経系、聞くことと触れること、との関係などである。もちろんその場合、音と光が直接に反応したりするわけではない。音の刺激によるそれも、光の刺激によるそれも、どちらも脳ニューロンの反応としては同じであり、その相互の関係を考えることが必要だということである。その相互の関係は重要である。言葉によって意思や感情が伝わるとか、情報が伝わるとかいっても、それらは全て言語中枢たる音覚中枢と他の知覚中枢(もちろん記憶中枢も含めて)との関係によるものなのであるから。
言葉がどういう働きをしているかは、誰もが知っているようでいて、誰も知らない。しかし、ニュートン力学やアインシュタイン力学にしても(その間の「パラダイムの転換」と表現される共約不可能な断絶にしても)、量子論の宇宙にしても、そういう言葉の世界が何故生まれたのかは言葉の働きが、すなわち言葉がどのような作用を果たしているかが、分からなければ分からない。仏教やキリスト教やイスラム教にしても言葉の働きが分からなければ分からない。
言語中枢は広い意味で音覚中枢であり、言葉は音である。言葉は人間にとって外から聞こえてくる音であると同時に発声運動の結果としての声として人間が内側から発する音でもある。人間の声は、人間の内側にも外側にも属さないというか、内側・外側という相対性のないものでもある。その人間の声が、言葉ではない声の場合、日本語人その他自然言語人においては言語脳(多く左脳)が中枢になり、英語人その他非自然言語人においては非言語脳(多く右脳)が中枢になる。
言語中枢は広い意味で音覚中枢であるが、右脳であれ左脳であれ、音覚中枢を作用させるあらゆる音が言葉になるわけではない。或る音の音響的性質によってその或る音が言語になるわけでもない。周波数比が倍音関係に無い複数の音や、或る程度の周波数変調度を帯びた周波数変調(FM)音の組み合わせといった、言語脳側を中枢とする音を電気的・人工的に合成することはできたとしても、その音がすなわち言葉というわけでもない。
音は、人間という生命体のあらゆる内的知覚・外的知覚との関係において言葉となり、対自的機能の中枢(多く左脳)がその中枢となる。
音覚中枢としての言語中枢と他のあらゆる知覚中枢――内的知覚中枢(分泌系・循環系・呼吸系・筋肉系・衝動関係)・外的知覚中枢(光覚系・触覚系・その他)――との関係、とりわけ重要な光覚(視覚)中枢との関係、を一般的に調べるという見地からの、言語活動に関する脳ニューロン反応の観察・実験―たとえばヨーロッパ人と日本人を被験者として並べ、「同じことを考え同じことを感じそれを言語表現してください」と要求し、そこで生じる脳ニューロン反応を、外部からニューロンの活動状態をモニターし得る方法や装置などを開発し、観察し比較するというような実験(とりわけ興味深いのは昔のドイツ観念論哲学や量子論のような抽象的思考を行っている際の様子である)―、それによる言語の作用の解明、どういう言語がどのような作用を及ぼしているのかの解明、は未だなされてはいない。しかし、たとえそうした方法や装置が開発されたとしても、そうした実験は、言語中枢以外の他の全知覚中枢の同一性(それを同一にして、つまり、言語関係以外は同一人格にして、言語人ごとに音覚中枢たる言語中枢との関係の違いをしらべるわけである)を維持することなど不可能であるから、事実上不可能だろう。
そこで、こうする。人間は大昔からさまざまな言語活動を行っているわけであるから。その言語活動を観察する。つまり、地球全体を観察フィールドとし、人類史全体を観察期間とし、過去から現在に至るあらゆる人間を被観察者とし、そこに現れる言語活動からそれを、すなわちさまざまな言語人の音覚中枢としての言語中枢と他の全知覚中枢(とりわけ光覚中枢(視覚中枢))との関係を、知る。つまり、古代から現在に至るまで、地球上に現れたあらゆる人間は、すべてが同じ生命体たる「ひと(人)」であるという事実により、生命体たる人類の生命普遍的レベルにおいて被観察者の言語中枢以外の他の全知覚中枢の同一性を担保する。そして、その場合観察の主体も客体もどちらも同じ人間の脳であるから、そうしたさまざまな言語活動の追体験により、逆探知のように、自分自身の脳がモニターにもなるわけである(これは期待し得る最も高性能なモニターである)。これなら誰にでもわかる。むずかしいことではない。「我思うゆえにわれあり」ってどういうこと? なんでヨーロッパ人はこんなこというの? といった程度のものである。
そこで。
地球全体を観察フィールドとし、人類史全体を観察期間とし、過去から現在に至るあらゆる人間を被観察者とし、そこに現れた言語活動を幾つかあげていく(幾つかといっても、もちろん二つや三つではない。全体を見渡せる程度の最小限である)。あげながら、なんだこれは、と考えていくわけである。
これは思考実験ではない。事実の確認である。
まず『資本論』。
いうまでもなく、これはカール・マルクスの著作物である。第1巻の発刊は西暦1867年。かといって、ここで共産主義が論じられるわけではない。ここでの関心事は、その『資本論』における言語表現のあり方、言葉の用いられ方、(叙述として現れている)思考における言葉の作用の仕方、である。
『資本論』の冒頭。すなわち、その第1巻・第1篇・第1章・第1節。
まず、第1節の標題。
そこにはこうある。すなわち、「第一節 商品の二要素 使用価値と価値(価値実体、価値量)」。
ここに「(価値実体、価値量)」という言葉がある。
「価値(Wert)」の、「実体(あるいは、本質:Substanz)」と、「量(あるいは、大きさ:Größe)」……。
すなわち、この著者(マルクス)は、「価値」の「質」と「量」を思考している。「価値」という抽象概念を対象として、その「質」と「量」を考えるという思考を行っている。
価値の質と量……。
「価値(Wert)」は、「岩」や「木」のような、具象概念ではなく、抽象概念である。
抽象概念と具象概念の違いは、具象概念は見たり触ったりすることができるものを表するが、抽象概念により表されるなにかは見ることも触ることもできない。それは純粋に言葉である。音である。音覚神経中枢としての言語中枢の作用たる言葉である。それは見えない。その「言葉」の、すなわち「価値」の、質と量とは何だろう。岩や水の質と量ならわかる。「価値」の質と量とは何だろう。まるで「価値」が具象概念であるかのようである。
つまり、どういう事態が起こっているのかというと、カールという名のこの男は、「言葉」が、つまり「価値」が、人間の外側に存在する物体のように客観的(対自的)に対象化され、まるで、得体の知れない物体(たとえば透明なゼラチンの固まりのような)を目の前に置かれ何者かに「これを調べよ」と命ぜられたかのように、「価値」に関しその「質」と「量」を思考しているのである。
資本家はなぜ儲かるのか、マルクスが言うところの「剰余価値(あるいは、より一層の価値:Mehrwert)」がなぜ生じるのか、に関する疑問とその解明への知的衝動が彼を『資本論』の思索へと駆り立てた。そして、彼の「分析」は「価値」の「質」と「量」を思考することへと辿りつき、そしてそこから『資本論』のすべてが始まった。それが『資本論』の叙述として現れる思考すべての始まりだった。
「価値」の「質」と「量」……。
同じような思考はいくらでも可能である。たとえば「愛」の質と量、「憎悪」の質と量、「自由」の質と量、「民主主義」の質と量、「正義」の質と量、あるいは、「真理」の質と量……。
「資本主義的生産様式の支配的である社会の富は、『巨大なる商品集積』として現れ、個々の商品はこの富の成素形態として現れる」。これは『資本論』本文の冒頭である。
富は、商品集積として、現れる。個々の商品は、富の成素形態として、現れる(erscheinen:光や輝きによって存在を感じるような、非常に視覚的な言葉である。英語でいえばshine(輝く)。名詞化したErscheinungは幻影や亡霊や神の顕現も意味する)……。
「富」が「現れる」……。
この表現には、「富」という、物体のような、あるいは人間のような、何かが、「巨大なる商品集積」に変容し、光となって、視覚を刺激し眼前に出現するような印象を受けないであろうか。「巨大なる商品集積」に変容した「富」は、元素のような個々の商品の総和。個々の商品は「富」の成素形態……。いうまでもなく、「富」は抽象概念である。
多少後には次のような一文もある。
すなわち、「一つの物の有用性はこの物を使用価値にする」。
有用性は、物を、価値にする……。
ここでは、「有用性」と呼ばれる物質のような何かが化学反応を起こし「価値」と呼ばれる物質のような何かに変質するような印象を受けないであろうか。
あるいは、「使用価値は、富の社会的形態の如何にかかわらず、富の素材的内容をなしている。われわれがこれから考察しようとしている社会形態においては、使用価値は同時に ―― 交換価値の素材的担い手をなしている」。使用価値は、富の、素材的内容。使用価値は、交換価値の、素材的担い手……。
ここでは、「富」という物質のような何かが、「使用価値」という物質のような何かを素材とした化学反応により生成されたような、「使用価値」という物質のような何かにはその化学反応により「交換価値」と言う物質のような何かに変質する性質があるような―そんな印象を受けないであろうか。
あるいは、「交換価値は、まず第一に量的な関係として、すなわち、ある種類の使用価値が他の種類の使用価値と交換される比率として、すなわち、時と所にしたがって、たえず変化する関係として、現れる」。
使用価値と、使用価値が、(まるで物のように)交換される……。交換価値は、(その交換の)比率として、関係として、現れる……。
ここでも、「交換価値」が「関係」(これも抽象概念である)に変容し眼前に出現するような印象を受けないであろうか。まるで「交換価値」が見えてくるような……。くどいようであるが、「交換価値」は抽象概念である。音覚神経中枢たる言語中枢の作用たる音である。
『資本論』のその後の叙述は、二つの対象(商品)の交換を客観的に判断した場合の(まるで天秤が釣り合うような)平衡感・公平感・公正感を論理正当化の根拠として、交換される二つの対象に同じ「価値」を認め(つまり、二つの対象の価値が等しい場合に交換が生じることを論理の前提にするわけである(交換される二つの商品の価値が同じならいかにも公平かつ公正な感じがする))、そしてこの「価値」を「交換価値」とも表現する。この間の事情を、マルクスは、「交換価値」が「同一物」を「言い表す」と表現し(つまり、交換が生じる場合、交換される二つの対象に同じ「価値」があるということである。どちらにも同一人物たる「価値」さんがいるような状態である)、そしてこの「同一物」を、交換される二つの対象から分離された、「両(ふた)つのもののいずれでもない」、「第三のもの」と表現し、「交換価値はそもそもただそれ(具体的商品)と区別さるべき内在物の表現方式、すなわち、その「現象形態」でありうるにすぎない」と表現する。交換価値は、商品の、内在物が、現れる、その現れ方(現象形態)……。交換価値(価値)は、(交換される)両(ふた)つのもののいずれでもない、第三のもの……。ちなみに、二つの対象が交換される場合双方に同じ価値がある、という認識は交換の平衡感・公平感・公正感を満足させはする。しかし、二つの対象が同じ価値である場合に交換現象が生じるという『資本論』の全論理の前提にはべつに何の根拠もない。そこにはただ素朴な公平感があるだけである。そしてその後の『資本論』の叙述においては、その「第三のもの」としての「交換価値」には物体のように大きさ(量)があり、その大きさは(商品は労働生産物なので)労働の量によって量られる。ただし、その場合も、それは、具体性のなくなった、「労働(力)」という抽象概念の量であり、いうなれば、「交換価値(価値)」の「量」は、具体性の無い抽象概念としての「人(あるいは、人格:persona・ペルソーナ)」が行う抽象概念としての「労働」の「量」によって量られる。マルクスの場合、この「労働」の「量」は、「(或る種の商品を生産するために)社会一般的に必要な労働時間」を単位として量られる(もちろんこれを現実に計量することは不可能である)。抽象的「人」による抽象的「労働」の結果たる労働生産物(商品)は透明な凝結体のようなものとなり、透明な物質のごとき「労働(力)」とその生産物と透明な物質のごときその「価値」は(思考において)同価となり、そして、この透明な物質のごとき「労働力」が(つまりそれと同価たる「価値」が)交換されていく過程として、あらゆる生産や交換の現象が、すなわちあらゆる経済現象が、把握され、表現されていく――。
その他、『資本論』には、その叙述(として現れる思考)全域にわたる問題として、具体性と抽象性の分裂、たとえば、「使用価値(具体的価値)」と「価値・交換価値(抽象的価値)」、「具体的労働」と「抽象的労働」、「労働過程(具体的生産過程)」と「価値生産過程(抽象的生産過程)」、のような、具体性と抽象性の分裂の問題があるのであるが、それに関しては、基本からそれるので、ここでは省略する。ただ、それに関し一言すれば。具体性と抽象性の分裂とは、視覚中枢関係や触覚中枢関係といった音覚中枢たる言語中枢以外の全知覚中枢関係(具体性)と音覚中枢たる言語中枢関係(抽象性)の分裂であり(つまり、『資本論』と総称される言語表現自体に、マルクスがその内面を告白するように、そうした分裂性が現れている。すなわち、分裂関係に無い言語と分裂し現実から遊離し抽象化した「言語」が併存しているような状態である。とりわけ/価値/に関しては、分裂関係に無い価値と分裂し現実から遊離し抽象化した「価値」が併存し、二つのような一つのような、精神分裂的な状態になっている)、そうした具体性と抽象性の分裂は、いわゆる「(資本主義の)絶対矛盾」や「(歴史の)運動法則」の問題も含めて、マルクスや資本論にまつわるあらゆる謎を解く決定的な鍵となる。
マルクスを離れ、フランスの言語学者・ソシュール。
その『一般言語学講義』(ただし、これは、その講義録を収集する形で、ソシュールの死後出版されたものであり、彼自らの手により書かれたものではない)には次のような言葉がある。
すなわち、「(言語(langue)概念に関して、あるいは、言語(langue)と言(parole)との概念的峻別に関して)ここに注意を要することは、われわれは語ではなく、ものを定義したということなのである―ものを定義するにあたって語から発するのはよくない方法である」。
つまり、言語は、言葉は、端的に、一般的に、語とは、言葉とは、関係の無い、「もの」なのである。マルクスにおいて、「価値」が、つまり「言葉」が、人間の外側に無言の存在感をもって存在する物体のように、客観的(対自的)に対象化され、存在化するように。得体の知れない物体のように。「言葉」は「もの」なのである。
ソシュールにおいては「langue・言語」と「parole・言」が峻別されている。ソシュールの言う「langue」とは、要するに、「抽象的言語・抽象的言葉」であり、「parole」とは、「具体的言語・具体的言葉(現実的と言ってもいい)」である。つまり、具体性と抽象性の分裂という、マルクスにおいて生じていたのと同じ現象が、ソシュールにおいては言語に関して生じている。ただしソシュールにおいては、マルクスにおいて「抽象的価値(価値・交換価値)」が社会一般的なものであったのと異なり、「抽象的言葉(langue)」は、社会的なものではなく、「私」に属するもの、純粋に個人に属するものになっている。なぜそうなるのかといえば、それは、言葉は人間相互の音声のやりとりによるものであるから、社会性(社会性とは人と人との相互関係性である)は「parole・具体的(現実的)言葉」の属性になるわけである。逆に言えば、「抽象的言葉(langue)」は、社会性と表現されるところの、人間相互の関係性など無いものなのである。言葉に人間関係など無い……。
あるいは、『一般言語学講義』には、「言葉の本質は、のちに見るように、言語記号の音楽物質とは無関係なのである」などという表現もある。
「言葉」は、その本質として、「音楽物質」と表現されるところの、音とは無関係なのである。赤ん坊の泣き声や笑い声その他(言葉以外の)人間の声は、ヨーロッパ人では、言語脳(多く左脳)ではなく非言語脳へ行くわけであるが、こうなると、言語中枢は音覚中枢からも遊離しているような印象を受ける。言葉は聞こえるであろうか、聞こえないであろうか(文字は聞こえないが)。
このソシュールからは、「言葉」を何かを表す「記号」として考え、物質(あるいは物質のごとく存在する対象)としての「言葉」の「構造」を知る、あらゆる言葉に関しその記号としての特性を知り、言語という巨大に構築された宇宙の構造を知る、という努力が生じる。すなわち、言語学における構造主義である。さらにその後は、文化人類学を大きな発条(ばね)としつつ発展し、あらゆる現象(もちろんこれも言語化される)を記号として考え、あらゆる現象に関しその記号としての特性を知り、現象という巨大に構築された宇宙の構造を知るという、知的活動努力一般における構造主義。フロイトを言語学的に表現した、フランスの構造主義的精神分析学者ジャック・ラカンには「無意識は言語活動(ランガージュ)として構造化されている」という言葉がある。あるいは、「無意識はひとつの言語として構造化されている」「『構造化されている』と『ひとつの言語として』とは私にとっては正しく同一のことがらを指す」(1966年ボルティモアで行われた国際シンポジウムにおけるラカンの口頭発表)。その他ラカンには「無意識は他者の言表(ディスクール)である」という言葉もある。無意識たる、構造化と同じ意味の言語活動は、自分のではなく、他者の活動のようである(ただしこれは、無意識たるラカンの言語活動の分裂性の問題である(その分裂性が他者性を生じさせる。この絶対的分裂性の源因は後の『脳・言語・神、そして時間』で問題になる)。
あるいはドイツの哲学者・ハイデッガー。
「ロゴス(言葉)それは存在者の、つまり絶対存在の安定した内省であり、その即自的瞑想である。フィジス(自然、あるいは存在物一般)といいロゴスというのも同一物にほかならない。ロゴスは絶対存在を新しい、しかも古い観点から特徴づける。つまり、存在者であり、即自的に自明のこととされるものは、自己のうちにあって、自己から出発して内省されるのであり、そしてそのような内省のうちに維持されるのである」(『形而上学総論』)。
ロゴス(言葉)とフィジス(存在物)は同一なのである。たとえば、「価値」というロゴスや、「真理」というロゴスは、フィジス(存在物)と同一なのである。ロゴス(言葉)は永遠の絶対存在(者)……。
あるいはカント。「或る悟性的な至高の原理」「道徳的な諸法則のもとにある理性的存在者の現存のみが、世界の現存在の究極目的であると考えられうる」(『判断力批判』)。「道徳的な諸法則のもとにある理性的存在者の現存」……。ちなみに、カントには次のような言葉もある。「すべての真理に対する唯一の絶対普遍的第一原理は存在しない」「唯一の第一原理は単純な命題でなければならない」(『形而上学的認識の第一原理』)「純粋な実践的理性が存在する」「この(純粋な実践的)能力とともに、また超越論的自由が今後は確立するのである」(『実践理性批判』)。純粋な実践的理性による単純な命題で或る悟性的な至高の原理にたどりつき道徳的な諸法則のもとにある理性的存在者になれそうである。
あるいはヘーゲル。
「真なるものは体系としてのみ現実的であるということ、あるいは、実体は本質的に主体であるということは絶対者を精神として語る考え方のうちに表現されている。この「精神」というのは、もっとも崇高な概念であり、われわれに近い時代と、その宗教とに属する。――精神的なもののみが現実的なものである」(『精神現象学序論』)「理性的であるものこそ現実的であり、現実的であるものこそ理性的である」(『法の哲学』))。理性(理の性(さが))は、対自的に自分をコントロールする性質、というような意味で言われるが、絶対者が精神として語られるとき、すなわち、絶対的存在が精神という人格の抽象的なありかたとして語られるとき、その(人格の抽象的なあり方が絶対的な存在になることの)対自的存在性の絶対性と言語の抽象性と対自性により、つまり対自的存在たる抽象的あり方(このあり方として「言葉」がある)の絶対的実在性(Wirklichkeit:Wirklich・ヴィルクリッヒ―実在の、現存する、現実の、有効な)ゆえに、それ(理性)は人間が言葉により思考するその性質、言葉による脳ニューロン反応過程を生じるその性質、になる。言葉による人間のコントロールである。そのような性(さが)が人間にはある。ヘーゲルにおける「体系」は、そのような性質(人間の言葉による脳ニューロン反応過程を生じる性質)の結果、言葉による思考とその結果、その記憶の総体、である。すなわち、「体系」は「言葉」の総体である。「言葉」の記憶の総体である。それはあらゆる「言葉」の総称としての「言葉」である。それがすなわち「絶対者」である。
「精神的なもののみが現実的なもの(あるいは、実在。あるいは、実在性)」「理性的であるものこそ現実的」「真なるものは体系としてのみ現実的」……。
こうした、言葉が物体(存在物)のように対自的(客観的)に存在化する思考や言語表現のあり方は、ヨーロッパやその系統の知的努力においては極めて一般的に平凡にあらわれているわけであるが、十四・五世紀頃のヨーロッパには極めて分かりやすいあり方で広範にあらわれている。すなわち、オランダの歴史学者・ホイジンガーがその著『ホモ・ルーデンス』や『中世の秋』において精力的に収集している抽象概念の擬人化表現の例がそれである。ホイジンガーは、この現象を、「(この時代の)広く文化一般に固有の傾向」(『中世の秋』)と表現している。これはヨーロッパではそれほどに一般的な現象だったのである。ただし、ホイジンガーの思考においては、或る思考過程(A)が何らかの理由により他の思考過程(B)に融合し、過程(A)が過程(B)として思考され表現される過程、すなわち、象徴(シンボル)や隠喩(メタファー)や寓意(アレゴリー)の過程と、抽象概念が擬人化される過程とが峻別されておらず、そのため叙述における用語法は極めて曖昧なものになっている。後者、すなわち抽象概念の擬人化においては、抽象概念過程(A)が擬人過程になるのであって、過程(B)によって過程(A)が表現されるのではない。過程(B)により過程(A)が象徴されたり隠喩されたりするわけではない。たとえば、「希望」が擬人化された場合、「人」によって「希望」が象徴されたり隠喩されたりするのではなく、「希望」は人になるのである。以下、ホイジンガーのそれらの著書から擬人化例を幾つかあげれば。
たとえば、ハインリッヒゾイデは「かの女は、頭上高く雲のわく天空に浮かんでいた。かの女は、暁の星のごとく明るく、太陽のようにまばゆく輝いていた。その冠は永遠、その衣は至福、その言葉は甘美、その抱擁は悦楽の極み。かの女は、遠くにいてしかも近く、高みにいてしかも低く、ここに姿をあらわしていて、しかも隠れていた。だれでもがかの女に近づけたのだが、しかし、誰もかの女をつかまえることはできなかった」などと表現する。この場合、「かの女」とは「永遠の知恵」なのである。ニーチェなども、『ツァラツーストラかく語りき』において「永遠」と踊りを踊ったりしていた。この男は「永遠」に子供を産ませたいと言っている。さらにホイジンガーから摘出すれば。ユスタスデシャンは、『結婚の鏡』なる詩において、「率直な欲望」や「愚かさ」や「情欲」が彼に結婚をすすめ、「知識の蓄え」がその逆を説く。あるいは、アッシジの聖フランチェスコは、彼の花嫁「貧困」を敬虔な感激のなかに至福の熱情を抱きつつ崇める。あるいは、或る写本に見られる系統樹「法と慣習の起源の樹」では、法に関するさまざまな事柄がたくさんの枝を広げた樹となる(これは擬人化ではなく擬木化である)。あるいは、『道徳的文書 別名アレゴリーにうつされた文法書』では、あらゆる名詞は人間、代名詞はその人が罪人であることを示したりする。あるいは、『パリ一市民の日記』を記した男は次のように記す。「そのとき、無思慮の塔にいた不和の女神が立ちあがり、憤怒や貪欲や激怒や復讐を呼びさまし、一同は、てんでに得物をもって、理性、正義、神を想う心を、そして穏和を、恥を知らぬやり方でのけものにしてしまった」。ちなみに、この日記を記した男は非常にきまじめな、面白みの無い性格で、日記の他の部分では文章を飾ってよろこんだり、考えに凝って遊んだりするようなことは全くしていないという。その男が、1418年6月、パリにおけるブルゴーニュ派によるアルマニャック派虐殺事件の目撃という興奮状態に陥ったそのとき、唐突にこのような表現があらわれた。これは示唆的なことといえる。あるいは、シャルル・ド・ロシュフォールは、『宮廷で騙されたもの』なる論において、「愚かな軽信」や「愚かな奢り」などの擬人を登場させ、「貧しさ」や「病(やまい)」によって病院へ連れていかれる。あるいは、13世紀に書かれた『薔薇物語』では、愛の庭園の壁に「憎悪」や「裏切り」や「粗野」「強欲」「貪欲」「嫉妬」「悲哀」「偽善」「貧乏」の絵姿が描かれ、「遊楽」の友である「閑暇」夫人が門をあけ詩人を迎え入れ、庭園の中では「歓喜」が踊り「愛」の神が「美」の手をとる。踊りの輪の中には「富」「寛大」「率直」「儀礼」「青春」がいる。「愛」の女神は詩人に「美」「率直」「儀礼」「友だち付き合い(カンパニー)」「愛想のよさ」を(矢として)射かける。「儀礼」の息子「歓待」が詩人を薔薇のところへ誘(いざな)う。すると薔薇の番人「危険」「悪口」「恐怖」「恥」がやって来て彼を追い払う。「理性」が高い塔から降りてきて彼を説得する。ヴィーナスは「純潔」を罠にかけようとし、「率直」と「憐み」は詩人を「歓待」のもとへ連れ戻す。「歓待」は薔薇に接吻することを詩人に許す。ところがそれを「悪口」が告げ口し、「嫉妬」が走ってやって来る。薔薇の周囲には壁がめぐらされる。「歓待」は塔に押し込められ「危険」とその一味が門を見張る。詩人が嘆く……。この『薔薇物語』を悪徳の源泉として非難した攻撃文においてパリ大学総長・ジャンジェルソンは記した。さまざまな「想い」の翼に乗り、ここからあそこへ、ついにはキリスト教の聖殿堂へ。そこで彼は「正義」「良心」「知恵」に出会い、「純潔」が狂気じみた熱愛者(『薔薇物語』の作者)のことで嘆いているという話しを聞く、と。
ホイジンガーは、古代ローマや古代ギリシャにおける擬人化例もとり出している。
すなわち、古代ローマには『インディギタメンタ』という宗教文書があり、そこでは「驚愕」や「恐怖」その他が擬人化され神格化されている。
あるいはギリシャ関係では、古代ギリシャ哲学者の思想として残されたその残存断片において、プラトン以前の哲学者・エンペドクレスは言う。「その歓喜なき場処、そは殺人、激怒、さらにその他の有害な神々の群の、伝播し来る疫病、腐敗、而うしてあらゆる腐蝕の生みの子らと共に、悲哀の原野の暗がりを徘徊するところなり」「かしこには又、大地の母、遠目利きの太陽の処女、血腥き争い、厳しき眼付きせる調和、美夫人、醜夫人、忙夫人、鈍夫人、而うして愛らしき誠実と、漆黒の髪束ねたる翳とありき」。あるいはホメロスは『イーリアス』において、人間の心に忍びこむ「迷妄」や醜いやぶにらみの「嘆願」をうたう。これらはすべてゼウスの娘である。あるいはヘシオドスの『神統記』においては、「労苦」「忘却」「飢餓」「苦悶」「殺人」「闘争」「虚偽」などが悪しきエリス(不和)の子孫として登場する。
ホイジンガーがこれらの擬人化(彼の言うところの象徴や隠喩)に興味を抱いたのは、彼が若き日に言語学を志し、比較言語学にひかれ歴史主義的な青年文法学派(ユンググラマティカ)に接近したことの影響があるだろう。彼によれば、「(擬人化、彼の言う象徴化表現、において)根源的なことは、知覚された事物が生きて動いている生命体という観念に置き換えられる、ということなのである。それは、我々のうちに知覚したものを他人に伝えたいという欲求が動き出すやいなやすぐさまに生じる」(『ホモ・ルーデンス』)そうであり、さらにこれは「プリミティブ(原始的、あるいは根源的)な精神状況」(『中世の秋』)であり、「プリミティブな精神は、およそ名づけられ得るもの全てを存在と考える」(『中世の秋』)そうである。つまり、少なくともホイジンガーにおいては、彼がその著で多数例示したような抽象概念の擬人化・擬物化、あるいは、言葉の物体のごとき対自的存在化、は人類に普遍かつ永遠の本能だ、ということだろう。しかし、このような現象が起こっているのは全地球上でただヨーロッパだけである。ホイジンガーにも、「象徴主義は、その力強い両腕に自然と歴史の全容を抱きかかえる」「アレゴリーとは、表面に流れがちな弱い想像力に投射された象徴主義である」(『中世の秋』)等の表現による「象徴主義」や「アレゴリー」や「想像力」の擬物化や擬人化がある。さらに彼が、未開人や子供や詩人や神秘家の知恵と称して「一般的性質が、すなわち事物の本性であり存在の核心である」(『中世の秋』)と記すとき彼の脳もまた、彼がその著でふれた多くのヨーロッパ人たちと同じ状態になっている。
ホイジンガーを離れ、さらに古代ギリシヤ関係から例をあげれば。
たとえばプラトン。
「(数学者たちは)四角形そのものや対角線そのもののために議論するのであって、かれらが描いているもののためではない。その他の図形についても同様である。また、彼らが形作ったり描いたりしているちょうどそのものを―それらにも影像とか水に映った映像とかがあるが―、これらをも彼らは似像として用いはするが、見ようと求めているのは、悟性によるのでなければ見ることの出来ないかのものそのものなのである」「事物はそれ自体で、それ自体の或る不動の有性を持っており、われわれとの関係においてあるのでも、またわれわれに依存しているのでもなく、われわれの虚しい想像でもって上へ下へと引き廻されることもなく、それ自体だけでそれ自体の有性との関連において、元来あるがままの状態を保持している」「知識は感覚的なものを何ひとつ伴わない」(『テアイテトス』『クラテュロス』)。
あるいはアリストテレス。
「原理とは――(三)或る事物に内在してそこからその事物が最初に生じてくるような構成要素をいう。たとえば船の竜骨や家の土台のごとき。」「因とは一つの意味では、(一)或る事物に内在していてその事物がそこから生ずるところのものをいう。たとえば青銅は銅像の因であり、銀は銀杯の因であるが、まてこれらの類も因といわれる」「要素といわれるのは、(一)合成された事物に内在し、その事物がまづ第一にそれから合成されるものであって、種としてはもはや異なった種に分割されることのできないものである。」
いかにも彼アリストテレスは事物を考察しているように思われる。まさに事物を考察している。彼にとっては、言葉が、抽象概念が、事物なのである。「もしも永遠的で離在し恒存する何ものかがないとすれば、いかにして秩序があり得ようか ―― 」(以上アリストテレスは全て『形而上学』)。
「悟性によるのでなければ見ることのできない“かのもの”」「事物は我々との関係は一切なしに、感覚的なものは一切ともなわず、それ自体の不動の有性をもつ」「永遠的で、離在し(我々とは離れて在り)、恒存する(常に在る)、何ものか」……。何かにより、物的有性をもって、物的な「在る」という感覚をもって、彼らの思考が、脳が、肉体が、強迫的に支配されている。それはけして見えない。しかし、彼らはそれを見ようとしている。
あるいはギリシャ神話における神々。ヘシオドスの『神統記』には、前(さき)にあげた例のほか、「ニュクス(夜)は忌まわしいモロス(定業)とケール(死の運命)とタナトス(死)を産み、またヒュプノス(眠り)、オネイロス(夢たち)を産み、次いでモモス(非難)と痛ましいオイジュス(苦悩)を産んだ」という表現もある。ゼウスはテミスを娶りエウノミア(秩序)、ディケ(正義)、エイレネ(平和)やモイラ(運命)を生んだ。プロメテウスは「先慮」であり、憎悪や病気や盗みなどの悪のつまったパンドラの箱を開きそれらを外へ飛び立たせてしまった弟のエピメテウスは「後の思慮」、いうなれば「後慮」である。エピメテウスは慌てて箱の蓋を閉じようとした。すると中からか細い声が聞こえた。「私も外へ出してください」と言う。「お前は誰だ」とたずねると、その声はこたえた。「私は「希望」です」……。
その他、ギリシャ神話では、「法」や「記憶」や「調和」その他が歩き回っている。
あるいは北欧神話における『エッダ』では、主神オーディンの両肩に「思想(心)」と「記憶(識別力)」がとまっている。これは鴉(からす)である。
あるいは古代ペルシャ。
アケメネス王朝(前550―331)が確立された後ももちろんそうであるが、とりわけ原ペルシャ。彼らが未だパールサ人(辺境の人:「パールサ」は辺境の地名)であったころ、彼らの共同体統治の原理は「ミトラ(あるいは、ミスラ)」だった。「ミトラ」は神であり、千の目・万の目をもって全世界を見張った。「ミトラ」は「契約」である。契約とは、言葉による合意であり、複数の人が同じ言葉を得ることである。この「ミトラ」という言葉は、語源的には、量ることを意味する。つまり「量(はか)り」である。「はかる(量る・測る・計る・図る・慮る)」という言葉は努力経過を思考・推量することであり、対自的な思考努力を遂行することを表現し、「はかり」はその連用形・抽象名詞化である。対自的な思考努力の遂行―すなわちそれは「理性」を意味する。ラテン語でも、「理性」を意味する「ratio」は質的量的、時間的空間的に対自的に対象の全体と部分の相互関係を思考することを表現する。「言葉」が対自的に存在化しその対自的思考努力が言葉によって生じるとき、その(対自的思考)努力は言葉への奉仕となり、神たる「はかり(ミトラ)」は、理性による支配、「言葉」による支配、をもたらすものとして、神たる「言葉」への信仰をあらわし、その(「言葉」の)正しさを保つ。すなわちそれは、複数の者が言葉を同じくすることを、すなわち「契約」を、(理性による支配として)もたらし、その正しさを保つ。それは人と人との同一感をもたらしもする。そうしたことから、この神は「誓約」「正義」「友情」といった神にもなる。このミトラは大神としてイラン(ペルシャ)世界その他に、東はインド西はブリテン島(イギリス)に至るまで、広く信仰された。アケメネス朝ペルシャはもちろんのこと、アルサケス朝(パルティア・前247―後226)、ササン朝ペルシャ(後226―651)などでは、「ミトラ」は王朝の守護神として崇拝され、パルティア帝国時代には、アルメニア(アルメニア人はインド・ヨーロッパ語族)、カッパドキア、ポントス(どちらもトルコ東部の古地名であり、歴史的には、ヒッタイト人(インド・ヨーロッパ語族)、フリュギア人(インド・ヨーロッパ語族)、キンメル人(インド・ヨーロッパ語族とする説が有力)等が主に進出し定住した地域)の諸国には「ミトラ」を冠した「ミトラ・ダテス」の王名がみられる。これらを介して、そして兵士や商人らを介して、「ミトラ」は古代ローマ帝国にも浸透し、拡大し、その遺跡はブリテン島(イギリス)にまで及ぶが、このローマ帝国のミトラ教は、それが受け継がれる過程において、太陽神信仰やその他さまざまな土着信仰と融合し、本来のそれとは相当にあり方の変わったものだった。このローマ帝国のミトラ教は、「ミトラ」が一時は帝国の守護神となったりもするが、後にキリスト教と闘争関係に入り、敗北していく―― 。ミトラのこうした大神性は、この神が、その本質において、言葉の正しさをもたらし、見守り維持する理性神・言葉神一般の性質を有することによるものであり、「言葉」への信仰心、「言葉」が対自的に存在化するその作用が悟性でなければ見ることのできない“かのもの”を思わせ、その“かのもの”(その存在感は「言葉」によって生じ、“かのもの”とはその存在感を生じさせているそれ、すなわち「言葉」なのであるが)が神として信仰されるその信仰心、がそれへの信仰を生じさせ、その信仰を維持したのである。「名にし負うミトラは人々をして互いに合意せしむ。ミトラは天と地を支う。ミトラは瞬きもせず諸民を見守る」(古代インド文書『リグ・ヴェーダ』)。
あるいは古代インド。
各種『ヴェーダ』や『ウパニシャッド』にあるように、その思想や信仰において中枢的役割を果たした「ブラフマン」(もちろんこの「ブラフマン」は対自的に存在化し、人格化し、神格化(あるいは聖化)している。つまり、神である)。ちなみに、「ヴェーダ」は、「ヴィドゥ:知る」に由来する言葉であり、「知ったこと」を意味する。この場合、「知る」とは、神々についてさまざまなことを認識することであり、事実上、詩(うた)・神々への賛歌、において、言葉を得ることを意味する。「知ったこと」とは、そのようにして得られた言葉のすべてである。『ヴェーダ』は神々への賛歌集なのである。詩(うた)を書き集めたものなのである。「ウパニシャッド」の意味は必ずしも明らかではない。この「ブラフマン」という言葉は、「ブラー:増大する、あるいは、生む」に、動作・動きを表す接尾辞「マン」が融合した言葉である。すなわちそれは、「増(ふ)え・増(ふ)ゆ、の連用形・抽象名詞化」であり、「生まれ」(古語で言えば『生(あ)れ・生(あ)る、の連用形・抽象名詞化』)であり、全く何も無い空間からの無から有の生まれ出(現れ出)をあらわすような―そんな言葉である。では、何が生まれるのであろうか。何の「生(あ)れ」があるのであろうか。それは、「在(あ)る」と対自的に感じられる何か、対自的に存在化する何かであり、脳ニューロン反応としては、対自的に存在化していない状態(無)が或る瞬間対自的に存在化する状態(有)になる何かであり、それは「言葉」である。「言」葉の「生(あ)れ」、「言葉」の「現れ出」、言葉を生(あ)れさす何か、言葉の創造源―それがすなわち「ブラフマン」である。そしてそのようにして生(あ)れ出た(生み出された)無数の言葉が神々への賛歌であり、『ヴェーダ(知ったこと)』である。「ブラフマン」は当初は中性名詞だった(後には男性名詞となる)。すなわちそれは、性差を超越した、前に記したプラトンの表現を借りれば、「感覚的なものを何ひとつともなわない」―そんな言葉だった。このブラフマンは、極めて素朴な表現においてであるが、『リグ・ヴェーダ』において、世界創造、あるいは全存在物の創造、のごときことを行っている。すなわち、「ブラフマナス・パティ(ブラフマンの主、あるいは、主ブラフマン)はこれら(神々、あるいは万物)を冶工のごとく鍛接せり、神々の初代において有は無より生じたり、そ(有)のあとに方処(方向と場処・処(ところ))生じたり―」。ブラフマンは無から有を生じさせ、四方の全存在を生じさせる。言葉の「生(あ)れ」が、言葉を生(あ)れさす何かが、全存在を創造する。言葉が全存在となる。言葉が存在それとなる。存在となった言葉はさらに確固たるものとして維持される。確固たるものとして維持する存在、いうなれば、創造された全存在としての言葉をのせておく安定した、確固たる台座のごとき、あるいは、それを安定したものとして維持する柱のごとき、が一般的に据えらる。そしてこの確固たる安定した存在もまた言葉なのである。すなわち、「ダルマ」がそれである。「ダルマ」は、「ダル:支える、保つ」に、「ブラフマン」と同じように、動作・動きを表す接尾辞「マン」が融合した言葉である。この言葉は、仏教典などにおいて、日本語では一般に「法」と訳される。或る原始仏教典は仏陀の弟子を評して言う。「(仏陀の弟子は)世尊の嫡子 かれ(ブッダ)の口から生まれた者 法(ダルマ)から生まれた者 法(ダルマ)から化生した者 法(ダルマ)の相続者」。そして仏陀を評して言う。「如来(ブッダ)は法(ダルマ)を身体とするもの ブラフマンを身体とするもの 法(ダルマ)より成るもの ブラフマンよりなるもの」。古代インド・マウリヤ王朝のアショカ王はこの「ダルマ」を国の統治の中枢に据えた。インドにおけるこのブラフマン教とでもいうような信仰のあり方、言葉のあり方、脳ニューロン反応のあり方は、インド・ヨーロッパ語族の一族たる、「アーリア人」とも呼ばれる人間たちにより、西暦紀元前千数百年前から、西から徐々に永い歳月をかけインド地域へ浸透していった。もちろん、それ以前から、現在「インド」と呼ばれている地域には人々は平凡に生活し、そこには彼らの言語生活があり、信仰があった。その、原住の人間たちと西からやって来たインド・ヨーロッパ語族の一族たるアーリア人とが、幾世代にもわたって永々とさまざまに関係し合いつつ何千年かの歳月を経た結果が現在のインドの文化であり宗教である。インド・ヨーロッパ語族との接触、ブラフマンとの接触は、後(のち)、紀元前5世紀頃、その当時のブラフマン教圏としては辺境の地たる、現ネパール国境方面や現ビハール州(ベンガルの北方)において仏教やジャイナ教を生じた。後に「ブッダ」と呼ばれることになるシャカ族の王の子・ゴータマは、少年時代より、バラモンの学問を学んでいた筈である。「当時のインドでは、上流階級にあっては、七・八歳になると、バラモンの学者のところで、ヴェーダなどの学問を学ぶことが、一般の風習となっていた」(水野弘元『釈尊の生涯』)。原始仏教典『スッタニパ-タ』には、修行するブッダに悪魔ナムチが「あなたがヴェーダ学生としての清らかな行いをなし、聖火に供物をささげてこそ、多くの功徳を積むことができる。(苦行に)つとめはげんだところで、何になろう」といたわるように囁く伝承が残され、彼がヴェーダを学ぶ者であったことは確かなことである。ちなみに、『スッタニパータ』は、現存する仏教典の中では遡り得る最古のものであり、その表現は極めて素朴であるが、仏教を考えるうえでは最も本質的なものである。「セーラ・バラモンは――三百人の少年にヴェーダを教えていた」(『スッタニパータ』)。ゴータマもそんな少年たちの中にいたのであろう。そうした中で、(後世の言葉で言えば、「原住民」のような)シャカ族の子たる彼は、インド・ヨーロッパ語族系の王族や貴族の師弟らから、隠然あるいは顕然と、その知的優越感、(神々に関する)認識の優越感に由来する差別を(つまり蔑視を)受けたかもしれない。あるいは、蔑視などなくとも、彼は劣等感を感じたかもしれない。「ヴェーダ」は基本的にインド・ヨーロッパ語族の知であり認識なのである。そうした思い出(記憶)も外傷(トラウマ)となり、仏教を生みだすひとつの副次的な、あくまでも副次的な、要因になっているかもしれない。「外傷(トラウマ)」とは、自己の体験として容認しない(されない)体験記憶をいう。『スッタニパータ』には、ブッダが、バラモンが甘蔗王(伝説的大王。太陽の裔(すえ)たるシャカ族の祖とされる)に祭祀をすすめ(犠牲として)牛を殺した、と非難する伝承が残される。ここには、ブッダのバラモンへの、すなわち、インド・ヨーロッパ語族の信仰のあり方、インド・ヨーロッパ語族のあり方、への、批判が感じられる。ちなみに、祭司兼学者たる「バラモン」の語源は「ブラフマン」である。しかし、仮に差別があったとしても、それは要因としてはあくまでも副次的なものである。けしてそれが仏教が生じた動因の本質ではない。少年の頃から、彼ブッダは学問として何を学んでいたのであろうか。『スッタニパータ』には次のような伝承が残される。すなわち、「セーラ・バラモン――かれは三ヴェーダの奥義に達し、語彙、活用論、音韻論、訓釈論、―語法と文法に通じ、順世論(詭弁説? )―に通達し」――。バラモンはそうしたことを教え、述べたのである。そうしたことを学び、考えることが当時の「学問」だったのである。すなわち、彼らは言語を、言葉を、思考したのである。言葉を思考すること、言葉に関しさまざまなことを覚え、考えること―それが当時の学問だったのである。少年時代より、ゴータマは、「言葉」を数十年間思索し続け、やがて「ブッダ(目覚めた人)」となる。ブッダは、飢え、病気、老い、死といったさまざまな苦しみから人間が救われるにはどうしたらよいかを考え、瞑想や思索へ入ったわけではない。彼はただ、瞑想思索し、認識の道を歩み、それを深めたのである。『スッタニパータ』には「ナーマルーパ」(漢語や日本語では一般に『名色』や『名称と形態』と訳される)という言葉が頻繁に現れる。『スッタニパータ』においてブッダは次のように言っている。すなわち、争闘と争論と憂いと悲しみと慳(ものおし)みと慢心と傲慢と悪口は愛し好むものにもとづいて起こる、愛し好むもの及び世の中にはびこる貪りは欲望を縁として起こる、欲望は「快」と「不快」と称するものによって起こる(19世紀最末期から20世紀最初期のオーストリアの精神分析学者・フロイトが辿り着いた認識はここまでだった。しかし、ブッダはさらにその先へいっている)、快と不快は接触(触れ、あるいは、さはり(触り・障り))を縁として起こる、そして、「ナーマルーパ(名称と形態)」によって接触(触れ、あるいは、さはり(触り・障り))が起こる……。ブッダはそう言っている。ブッダが辿りついた認識はここまでだった。「ナーマルーパ」がなぜ……というその先の思索は彼には無い。たとえあったとしても、それがなぜなのかの答えは無い。ここまで辿りついた彼に、次の段階として起こったことは、あらゆる知覚・感覚作用の無作用化努力、その無意味化・虚無化の無限努力だった。解脱である。そうなることにより、彼は快と不快の因縁たる「接触(触れ・障り)」から解放されたのである。何故なら、「触れ(触り・障り)」は知覚・感覚作用によって生じているわけであるから……。仏教的虚無へと入っていく。「ナーマン」は「名」。「ルーパ」は「形(かたち)」、あるいは「形あるもの」。「ナーマルーパ」は、「名となった形あるもの」、「言葉となったもの」、「言語化した存在」、である。言葉と存在が、すなわち、「在り」の脳ニューロン反応と言葉の脳ニューロン反応のあり方が、彼に、「接触(触れ・障り)」という言葉で表現されるところの、あらゆる存在不安の源たる根源的に不快な、不調和な、抵抗感を生じさせ、その存在不安が、彼のあらゆる瞑想や思索の源動因だったのである。そしてその根源的に不快な、不調和な、抵抗感は、「ブラフマン」との、すなわち、言葉が対自的に存在化する脳ニューロン反応のあり方との、融触により生じた。その意味では、ブラフマンは仏教の父体(母体ではない。母体はあくまでも人間)である。しかし、それは、何かの要因がつけ加わることにより、インド・ヨーロッパ語族の宗教たるブラフマン教がそのまま仏教になったわけではない。それは、人格化し、神格化した「ブラフマン」が人間内部に深く融け込むように触れることにより、或る人間に、或る虚無的な思考のあり方、感性のあり方、人格のあり方が生じ、それが、その「触れ(障り)」からの、根源的に不快な、不調和な、抵抗感とそれゆえの存在不安からの、或る解放であったことによるその開放感から、その人物は「ブッダ(目覚めた者)」と呼ばれ、その思考や人格のあり方が、やがて、「仏教」と呼ばれるようになったのである。それが仏教の起源であり、無から有が生じるような、その発生起源としての起動因である。ブッダ(或いはゴータマ、或いはシャカ)がインド・ヨーロッパ語族であるか否かに関しては議論がある。当時のそのネパール方面の生活圏を考えれば、ブッダが属したシャカ族はインド・ヨーロッパ語族ではないだろう。しかし、シャカ族の王家が、インド・ヨーロッパ語族系の王族や貴族の子弟を婿として迎え入れた可能性は否定できない。ブッダの父親の名として伝えられる「シュッドーダナ(淨(きよ)らかな米飯(めし))」はインド・ヨーロッパ語族系の言葉なのである。すなわち、彼はインド・ヨーロッパ語族系人とモンゴロイド系人の混血児かも知れない。仏教には「観音菩薩(かんのんぼさつ)」なる言葉がある。「菩薩」は、「悟りに生ける者」を意味するサンスクリット語「ボーディサットヴァ」の音をそのまま漢字で表現したものであり、言うなれば「求道者」であるが、「観音」は、西暦5世紀初め、クマーラジーヴァ(鳩摩羅什)という人物が、仏教典を中国語(漢語)に翻訳する際、或るサンスクリット語原語に関し、(その音(おん)ではなく)その意味を漢語で表現した言葉である。これに関しては、翻訳のもとになったサンスクリット語原語そのものに議論があり、別人による「観自在」や「観世音」という訳語もある。しかし、中央アジアで生まれたとはいえ、父親がインド人であるというその出自や、翻訳年次の古さを考えれば、やはり、「観音」というクマーラジーヴァの訳語が最も正確に原語の意味を伝えるだろう。観音―すなわち、音(おと)を観(み)る……。言語中枢は広い意味で音覚中枢であり、言葉は、その現象の性質として、声であり、音である。仏教典『般若心経』においては、この「観音菩薩(アヴァローキタスヴァラ・ボーディサットヴァ)」、すなわち、音を(言葉を)見る求道者、あるいは、見られたる音(見られたる言葉)たる求道者、は、色(しき・ルーパ:形あるもの)も受想行識(あらゆる感覚・知覚作用)も、すべて「空(くう)」だ、という境地へと入っていった。「空(シューニャター)」は何も無い状態であり、それは脳ニューロン反応の無作用化無限努力の表明である――。
では、古代のエジプトにおいてはどうであろうか。
そこに、「言葉」が対自的に存在化し擬物化し擬人化していく過程(そうした表現、及びそうした表現を現す脳ニューロン反応のあり方)はあるであろうか。
太陽神ラーや、死の国の支配者オシリスへの信仰に、ヨーロッパやペルシャ(イラン)やインドにおけるような、抽象概念が擬人化していく過程はあるであろうか。無いことを資料を掲げて例示するのはなかなか難しいのであるが。あるであろうか。
女神イシスなどはもともとは玉座だった。
抽象概念が擬人化されたような過程としては、「権威ある発言」や「知覚」などと言われる「フゥ」や「シア」、あるいは「真理」や「正義」などとも訳される「マアト」がある。「マアト」という言葉は、元来は「平らな」「まっすぐな」という物的状態を表すようである。この「マアト」は女神として肖像が描かれたりもする。しかし、これらは、その言葉(発言)が言葉通りの情況を生じさせていく権威ある人間、或る「思い」や「考え」(これが「知覚」と言われる)を抱いている人間、世の中に「平らな」「まっすぐな」状態をもたらす人間―それらが一般的に神格化される過程であろう。つまり、属性による神名である。あるいは、間接的にエジプト第1王朝期に由来すると思われる或る石碑文には次のような文句がある。「偉大なるプタハ かれは神の中なるエネアド(九神)の心臓また舌―プタハは神たちを生んだ―アトゥムの姿をした或るものが心臓に生まれ出て また舌の上に生じた」「プタハがその望むすべてのものを心臓として思考し 舌として命令することで生みだしたように すべての神々 すべての人間 すべての動物すべての地を匍(は)うもの あらゆる生あるものの身体にプタハが存在し またすべての口に存在していることを教えることによって 心臓と舌とは身のあらゆる部分を支配するようになったのだ」。「アトゥム」は創造神である。この言葉は「完成」という語感があるかもしれない。この石碑文は、「舌」という言葉で象徴される「言葉」で全存在を創造していくようにも読める。しかし、新興都市メンフィスのこの神学は、太陽神ラーを奉じるヘリオポリス(旧約聖書に言う「オン」)その他の神々に対抗するための、いうなれば、「私の神の言葉こそが他の神々の言葉よりも権威がある」という主張、まるでファラオの言葉のように、それによってあらゆる秩序ができていくのだ、という主張であり、さらに、ここに言葉によって何かを生み出すという過程があったとしても、それは言葉の普遍的本質的作用にもとづくものであろう。たとえば、「海」「山」「木」「岩」等の言葉により、(各々の記憶に応じ)海や山等を見る。あるいは、「夜」「朝」「良し」「悪し」等の言葉により暗さや明るさや肯定感や否定感を感じる。これは言葉を言葉としている本質的作用であり、この作用は言葉を用いる人間であればいつの時代にも誰にでもある。この作用によって、たとえば人の名を口にすればその人の記憶が蘇り、死者の名を口にすることがその死者をそこに存在させたかのような作用を果たし、或る場合には、それが死の穢れをもたらしたかのような作用を果たすという、フレイザーの『金枝篇』にあるような現象も起こる。この資料で産み出されるエネアド(九神)は、「空気(シュー)」「湿気(テフヌート)」「空(ヌート)」「大地(ゲブ)」等の、地上の存在秩序とでも言うべきものであり、創造された対象も、財産や食物や町という、やはり地上の存在秩序的なもの、具象的な要素なのである。『死者の書』にある、創造神が名づけることによる神々の創造なども同様の過程である。ここに、言葉を生(あ)れさす何か、言葉の創造源「ブラフマン」が無から有を、全存在を創造し、「ブラフマナスパティ」という中間的擬人化過程を経、さらにこれが男性名詞化し、見え始める過程、あるいは、「(視覚や触覚といった)感覚的なものを何ひとつ伴わない」何か、「悟性によらなければ見えない“かのもの”」たる何か、「永遠的」で「離在」し「恒存」する何か、まさに自分を離れて在る存在感を感じさせる何か―そんな何かに、強迫的にその思考が、全人格が、支配されていくような過程―そんな過程がこの古代エジプトにあるであろうか。最後に、多分新王国期頃の、パピルス文書にある言葉の中から、言葉に関する彼ら古代エジプト人の思いを伺い知ることのできる部分を抜粋しておこう。
「(神は)声の高い者よりも口数の少ない者を愛される」「神の住居では 禁断は騒がしい音を立てることである お前は言葉を隠して心を尽くして祈れ そのとき神はお前が必要としているすべてを与えるだろう (そのとき)神はお前が述べることを聞き お前の捧げ物を受け容れるだろう」「それ(知恵)は口(言葉)を見つける者には閉ざされているが 黙っている者には開かれている」――。
あるいはエジプトを離れ、メソポタミア方面。すなわち、シュメール、バビロニア、アッシリアなどではどうであろうか。
そこにおける神々。
「アヌ」は空。
「エンリル」は「嵐の君」。
「キ」は「地」。
「エンキ」は「地の君」。
バビロニアの「マルドゥク」は農業神、あるいは太陽神。
アッシリアの「アッシュリー」は山に関係がありそうである。
呪術文集『マクルー』における「私のかかっている魔法を破ってくれ おお塩よ 呪いをといてくれ 私から惑わしを取り除いてくれ さすれば私の造り主として御身をほめたたえるだろう」と「塩」に呼びかける過程、「私は御身を私の立腹している男神 立腹している女神の許にやろうと思う―どうか私の立腹している男神女神の心をなだめてくれ」と「穀物」に呼びかける過程、「おお火よ それらの男と女を亡ぼしてくれ」と「火」に呼びかける過程―こうした過程に「悟性でなければ見えない“かのもの”」の過程はないだろう。
では、中国はどうだろう。
その古代神話。
おおきな斧で天地を開いたともいわれる「盤古」や、瓢箪に乗って大洪水を免れたのち産み落とした肉の塊をばら散いたら人間になったといわれる「伏羲」や、同じく人間を創ったといわれる「女婦」や、その他「炎帝」や「黄帝」や「堯」や「舜」の神話(あるいは伝説:中国には元来「神話」という言葉はなかった)に「悟性でなければ見えない“かのもの”」の過程はない。中国には総体的にまとまった神話はない。その点はエジプトにも似ている。エジプトの神話は、ピラミッドの壁面や石棺に彫られた文書、あるいは発掘されるパピルス文書によってその断片が知られ、断片の堆積となり、断片相互には矛盾もある。同じように、中国の神話もさまざまな書籍その他に記された断片の集積として現れ、しかもその断片は多数の詩人や古代の思想家等により改変されている。したがって、その全体像を知ることは極めて困難である。ここで述べられる中国神話はもっぱら、中国の古い文献を精力的に渉猟しまとめている袁珂の『中国古代神話』によっている。それによれば、天地を開いた「盤古」は元来は「槃瓠(ばんこ)」だそうである。その昔、高辛王の耳が痛んだ。やがて耳から金の虫が飛び出した。皇后はこの虫を「瓠(ひさご)」に入れ「槃(たらい、あるいは盆)」でふたをしておいた。それゆえに「槃瓠」。この槃瓠は後に人間になる(ただし頭は犬)。天地を開く神話とこの話の前後関係は明らかではない。槃瓠神話があり、後に天地開闢神話があり、その主体が槃瓠(後の盤古)になったということであろうか。また、産み落とした肉をばら散いたら人間になったという「伏羲」は「匏戲」であり、これは瓢箪(ひょうたん)のことである。瓢箪に乗って洪水を免れたからである。つまり、或る物語の主人公として或る人間が空想され、その人間の特性やその状況に応じて名がつけられている。それに対し、ギリシャ神話などでは、空想された或る人間に「虚偽」や「労苦」や「調和」と名づけるのではなく、「虚偽」や「労苦」や「調和」が人間に(あるいは神に)なる。その結果、古代ギリシャなどでは神話それ自体が抽象的思考の過程となる。たとえば、エロス(愛)をプシュケ(心)が裏切るような―。帝俊の妻・羲和が太陽を十個産んだ。子供である太陽たちは、初めは母親の言いつけをよく守り、毎日順番通り一つずつ空へ現れていた。ところがある日、子供たちはひそひそと相談し、面白半分に無邪気にみんな一緒に空へ出ることにした。十個の太陽に灼かれ、人々は炎熱と旱魃に苦しんだ。弓の名人羿(ゲイ)が十個のうち九個を射落とした。羿(ゲイ)の妻嫦娥は、夫婦二人で呑めば不老不死になり、ひとりで呑めば天に昇って神にもなれる薬をもらう。嫦娥はひとりでそれを呑んでしまう。彼女は天へ昇り、月宮殿へいく。一説では、彼女はそのまま蝦蟇(がま)になってしまう。他の一説では、ただ一匹の兎が薬を搗き、桂の木が一本生えているだけの月宮殿で、あまりのさみしさに、彼女は薬をひとりで呑んでしまったことを永久に後悔する―。こうした物語のどこに「感覚的なものを何ひとつ伴わない何か」の過程があるであろうか。たとえ神になれなかったとしても夫婦二人で分かち合い仲良くすればよかった、ということなのである。西暦紀元前6世紀から前3世紀頃の中国に、孔子、老子、孟子、荘子等の思想家がいる。『論語』、『孟子』、『老子』、『荘子』―これらの書物のどこに、抽象概念を、透明な「イデア」を、交錯させ構築していくような過程があるであろうか。「道可道 非常道 名可名 非常名 無名 天地之始 有名 万物之母 故常無欲 以観其妙 常有欲 以観其徼 此両者 同出而異名 同謂之玄 玄之又玄 衆妙之門」。これは『老子』の冒頭である。さまざまな訓みがなされているが、一応の訓みをしめせば。「道の(道と)なる可きは常の道に非ず。名の(名と)なるべきは常の名に非ず。名無きは天地の始。名有るは万物の母。故に常に欲無きは以って其の妙を観(み)。常に欲有るは以ってその徼(きょう)を観る。此の両(ふたつ)は同じきより出で而も名を異にす。同じきは之玄と謂(い)う。玄の又玄 衆(あら)ゆる妙の門」。すなわち、道が道であることができるとき、それはもはや永遠不変の道ではない。名が名であることができるとき、それはもはや永遠不変の名ではない。名無きが、言葉無きが、天地万物の始め。そして、名無きを前提として、名有るが万物の母となる。故に、常に何らの欲をもたないことによってこそその「妙」(言葉では表現できない、不思議な、美しいなにか)を見ることができる。欲の有ることによってはその「徼」(物事の、現象の、末(うわべ)端)しかみることはできない。次に言う「此両」とは「妙」と「徼」だろう。つまり、「何か」の、言葉には言い表し得ない不思議な美しい何か(妙)とその上辺(徼)―それらは同じ「何か」から出ているが、「妙」と「徼」のように、名を異にしている。あるいはその同じ「何か」が、「美」と「醜」や、「善」と「悪」のように名を異にする場合もある。その同じ「何か」は「玄」、さらには、「玄の玄」という。「玄」とは、何も無い暗黒である。そしてこの「玄」は衆(あら)ゆる妙の出てくる門だという。あるいは『老子』には、「聖人は無為の事に処(お)り不言の教えを行う」という言葉もある。聖人は何もせず、何も語らないのである(もちろん書きもしない)。あるいは、「慧智出でて大偽有り」―知恵、かしこさが現れて大いなる偽りが始まった、などという言葉もある。孔子の『論語』には、「人能(よ)く道を弘む 道人を弘むに非ず」という言葉がある。此の場合、「道」とは、人が生きることを旅のように考え、其の旅において人間が歩むべき道、人間が生きることにおいて従う指針、指針としての言葉、教え、考え、思想である。つまり、人が教えを弘めるのであって、教えが人を弘めるのではない、人が言葉を弘めるのであって、言葉が人を弘めるのではない、ということである。あるいは、中国におけるいわゆる五経。すなわち、『易』、『尚書』(あるいは『書経』)、『詩』、『春秋』、『礼記』(いわゆる四書、すなわち『論語』『孟子』『大学』『中庸』、における『大学』と『中庸』は元来この『礼記』の中の二篇である)。「乾下坤上―泰」や「巽下艮上―蠱」の『易』、『尚書』は君臣の言行録、『詩』は詩の本、『春秋』は歴史物語り、『礼記』は君臣や父子母子間等の、まさに礼に関する書―これらに抽象概念構築の過程はあるであろうか。中国では漢(前漢)の武帝(西暦前141―85)以後儒学が国の教学となった。3・4世紀頃には仏教思想・仏教教理も浸透し始め.(中国の仏教は紀元前1世紀頃にはシルクロードの隊商とともに流伝していただろうと言われている)。六朝期(後漢の滅亡(220)から隋による統一(589)まで。当時、今の南京を首府にしていた六つの王朝を六朝という)、その六朝期、儒学に関しては既に「後世には経と伝と既に已だ乖離し、博学者は又た『多くを聞いて疑わしきを闕く』の義を思わず。しかも義を砕いて難を逃れんと務め。便辞と巧説もて形体を破壊し、五字の文を説くに二・三万言に至る。後進は弥よ以て馳逐す。故に幼童にして一芸を守り、白首にしてしかる後によくもの言う。その倣う所に安んじて見ざる所を毀ち、終に以って自らを蔽う。これ学者の大患なり(後世には孔子等の教えを記した本文とその注釈書はひどくそむき離れ、博学者は「多く聞いて疑わしいところをなくす」という正しい思いをもたず。正しさを破壊してまで自分の学問が非難されたりすることから逃げることに務め。いいかげんな巧みな説であるべき形や体を破壊し。五字の文を説くのに二・三万言もの言葉を用いる。後の世の人間はますます逐(お)いたてられるようにひどくなる。ゆえに、幼い頃から一つの学問を守り、老人になってはじめてものが言えるようになる。自分が習った学問の中に安んじ、見ないところは崩れて壊れ。ついには自らが蔽われ何も見えない状態になってしまう。これは学者の大きな病、大きなわざわいと言える)」(『漢書』)という状況が生じ、こうした、いわば虚しい言葉から解放されようとする現象として、「儒学は乱を撥(おさ)めて正に反(かえ)し、鼓を鳴らして俗を矯める大義なるも、未だこれかの理を窮めて性を尽くし陶冶変化する実論にはあらざるなり」(『終制』)という儒学への拒否(ただし、拒否とは言っても、それは、人間の真相・宇宙の真相はもっと奥深いのだ、というような言い方で表されるような逃避的拒否である)、あるいは、「道のなるべきは常の道に非ず」の老子思想の蔓延、その影響も受けつつ陰陽五行説や神仙思想を含み土着的習俗に根ざした多分に神秘主義的な「道教」の興隆、「六経は抑引を主となすも、人の性は欲に従うを歓びとなす。抑引すればその願いに違い、欲に従えば自然を得ん。然らば則ち自然の得らるるは抑引せる六経に由らず、性を全うする本は情を犯す礼律を須(もち)いず」という竹林の七賢人的清談、「万象渾べて冥観し、兀として体を自然に同じくする」という自然への指向、「山水は形を以て道に媚び、仁者は(これを)楽しむ」という山水への誘引、山水文学、山水画の勃興、世を離れた「隠逸」―等々の現象が生じた。もちろん、ここには乱世による厭世という問題がある。しかし、その場合も、当時の北方諸民族の動向も含めて、その「乱世」がなぜ生じたのかが問題となる。隋の時代には官吏登用試験としての「科挙」が生まれる(その起源とでもいうべき現象は漢代からあった)。その後は知識人層としての「士大夫」なども生じる。そして12世紀には朱熹(朱子)が「朱子学」を大成する。この朱子学は一般に「思弁的」と言われる。この印象は、朱子の、たとえば陸象山との論争に現れるような、太極に汎ゆる存在や現象の根拠たる理を認める窮理説的傾向によるものであろうか。「思弁」には、経験的所与によらない純粋思惟による言葉、という印象がある。しかしながら、いわゆる書院教育によって、科挙を最終目標としない、現実社会で役立つ真の人材を養成しようとし、貧民救済のための米貸し出し制度たる「社倉」などもつくり、ときおり行った政治活動には能吏も及ばぬ実効性があったと評価される朱熹の「思弁」なるものは―北宋の宰相・王安石の影響なども受けながら(この王安石という人物は、ときには儒教倫理をないがしろにして(たとえば、政府が高利貸的行為を行うなどとは王道や儒教の精神に反する、と批判されるような)現実的(あるいは実利的)合理的な国政改革を行った。この人物は科挙も実際政治への応用を重視する方向で改革を行った。言葉の人、知識の人たる士大夫層を現実政治に役立つ人間にしようとしたのである)―その朱熹の「思弁」なるものは、学問の虚学化と言われる情況、すなわち、五経やその周辺の膨大な著作物を読み、意味も分からなくともただ反省的思考なしに記憶しなければ科挙には受からないという情況―ちなみに、四書五経の重複部分を除いた漢字数は四十数万あるそうである。さらにその周辺にはその何倍かの注釈書やら何やらがある。それらを全て覚えなければ科挙には受からない。その昔、中国では、科挙に受からせるために腹の子に(つまり胎児に)『論語』やら何やらを読み聞かせた者もいたという―、さらには、「知識人」たちがただ読み、聞いて記憶しただけの言葉を得意げに言い回し書き回すことで「知的人間」を気取る不毛さ、そうした情況を打破するために、学問を、言葉を、なんとか現実の社会で実効的・実利的に働き得るものにしたい、そのための学問方法を一般的に定立したい―その「思弁」なるものはそんな彼の願望によるものだろう。隆興元(1163)年、南宋の皇帝・孝宗に対し朱子が行った奏箚の一部を抜粋する。「大学の道は、天子より以て庶人に至るまで、壱是に(すべて)皆な身を修むるを以て本となす。――然れども、身は以て徒に修むべからざるなり。深くその本を探るときは、すなわち物に格(いた)りて以てその知を致すに在るのみ。それ物に格る都は、理を窮むるの謂(いい)なり。蓋し、この物あれば、必ずこの理あり。然れども、理には形なくして知り難く、物には迹(あと)ありて賭(み)易し。故にこの物に因って以てこれを求め、この理をして心目の間に瞭然たらしめて毫髪の差なからしめば、すなわち事に応じて、自づから毫髪の繆(あやま)りなからん。ここを以て、意誠に心正しくして身修まる。―而るに秦漢より以来、この学(累聖相伝の学)、講を絶ち、儒者、詞章記誦を以て功と為し、而して事業日に卑近に淪(しず)む。亦(ま)たそのここに止まらざるに意あるときは、すなわちまた転じてこれを老子釈氏の門(老荘思想的玄学と仏教)に求むるに過ぎず。―意(おも)に、前日、勧講の臣、程式に限られ(勧説講習の臣は方式が限られ定式化され)、以て陛下に聞(もう)す所のものは、詞章記誦の習いに過ぎず、而して陛下以てこれより進む所のものを求むるに、またこれを老子釈氏の書に取るに過ぎず。ここを以て、生まれながらにして知るの性、世に高きの行いありと雖も、而も未だ嘗て事に随いて以て理を観ることをせざるが故に、天下の理、未だ察せざる所多く、未だ嘗て理に即きて以て事に応ずることをせざるが故に、天下の事、未だ明らかならざる所多し。」―。要するに、詞藻文章の暗記暗誦や仏教的玄学的虚理虚論ではなく、その肌で感じその手で触れることのできる現実の社会に即す学問で身を修めよ、と言っているのである。それが、太極にある筈の「理」へ向かうことであり、「格物致知」なのである。この朱子学が、元の時代、14世紀初めには国の教学となる。15世紀初めには、朱子学を批判した者が杖刑に処されその著作物を焼却されるような情況が生じる。そして15世紀末、あるいは16世紀初。王陽明が「知行合一」「良知」の陽明学を定立していく。彼の「知行合一」とは、「知」とはすなわち「行」だ、両者の間には何ら質的差異は無い、というものである。すなわち、これもまた「知」が、すなわち言葉が、現実から遊離することを防ごうとするものであり、朱子が現実社会の中に一般的に言葉をつなぎ止(とど)めようとしたのに対し、王陽明はさらに人間の肉体の中へ、肉体へ直接言葉をつなぎ止め、肉体と言葉を一体化させようとしたのである。王陽明はただ単に「知行合一」「良知」と言ったのみであり、実質的には無内容であったとしても、その指向性はけして誤ってはいない。しかし、無内容であるが故に、やりたいことは何でもやればよいというような「狂気」も生じる。さらに、17世紀の顔元などは、文字を(すなわち言葉を)毒薬砒素にまでたとえ「性命の理は講ずべからざるもの」(『存学論』)と言う。彼は「正徳」「利用」「厚生」を主張する。「正徳」は人間の正しい道徳。「利用」は物質的現実的効用。「厚生」は現実的な、豊かな人間生活の樹立。すなわち、彼は現実に役立つ実学的なものを主張したのである(朝鮮でも、17世紀に、虚学化した儒学に対して『実学』が起こっている)。王陽明にしても顔元にしても、けして彼らの学問が社会において一般的だったというわけではない。主流はあくまでも朱子学である。しかし、彼らのような学問傾向が相当根強く生じている。つまり、中国においては、古代以来、常に、言葉を現実の世界へひきもどそうとする力、そうした人間の努力、が一貫して強く働いている。これは、相対的に意えば、言葉を現実から遊離する作用が常に働いているということでもある。中国の場合、この遊離作用は、言葉の問題ではなく、たぶん文字の問題だろう。中国ではその思想は、孔子や老子の昔から、言葉の拒否や現実性の無い言葉の拒否から始まっている。対自的・言語的な儒学の系譜と即自的・非言語的な道教の系譜の二系譜が相互に或る程度の緊張感を維持しながら流れていく中国の文化・思想情況の問題や、儒学内の「理」と「気」の二元説(つまり、人間の内界・外界を問わない対自性と即自性の二元説)の問題なども含めて、「感覚的なものを何ひとつ伴わない」透明な抽象概念に埋もれ、これに呑みこまれ我を喪失してしまうようなことは中国人には起こらない。
では、日本ではどうであろうか。
『古事記』や『日本書紀』にある神名。これはギリシャ神話などとは対照的なものと言える。すなわち、ギリシャでは、言葉により、すなわち、音覚過程により、神格化が生じているのに対し、日本の神々の神名においては、基本的に、視覚過程が、すなわち光覚過程が、極めて強く働いて神名表現がなされ、あるいは、或る神が想定されその神にその属性を表現する(たとえば強ければ強そうな)神名がつけられ、「愛」や「虚偽」やらの抽象概念がそのまま擬人化し神格化してはいない。すなわち、極めて素朴かつ象徴的な言い方をすれば、古代ギリシャにおいては神々は音(おと)であり、古代日本においては神々は光(ひかり)なのである。「おほひるめのむち」(天照大神)は太陽に象徴されるの光の印象・効果による神名である。「たけはやすさのをのみこと」は「猛(たけ)く」「逸(はや)く」「凄(すさ)まじい」「雄」の神。島(陸)産みを行った「いざなき」「いざなみ」は発動している発動の元たる男と女を意味する(古代の日本語においては「き」と「み」でそれぞれ「男」と「女」を表現する場合があった)。この場合には、男と女が一つになり一つの生命の誕生として全世界・全宇宙が創造されたという点が重要である。島産みの後に生まれる神々は、「いはつちひこ」―これは岩や土。「いはすひめ」―これは岩や砂だろう。「かぜもつわけのおしをのみこと」―これは風に関係がありそうである。「おほわたつみ」は海。「おほやまつみ」は山。「たけみかづち」は雷……。不和の女神が「労苦」や「虚偽」を生んだりするような現象は日本では起こらない。あるいは『万葉集』や『古今集』や『新古今集』、あるいは『源氏物語』―これらに「イデー」を構築する過程などないことは言うまでもない。神道、(日本の)朱子学、陽明学、国学(たとえば賀茂真淵や本居宣長)、数々の仏教僧の著作物―それらに「悟性でなければ見えない“かのもの”」の過程はあるであろうか。18世紀の三浦梅園などはカント的と言われることがある。しかしながら、その著『玄語』を見る限り、陰(没)・陽(露)、精(気)・粗(物)、散・結、明・暗、清・濁等の対位的過程をただ並べ、すべては(一)だ、それが(一)(一)になったとき条理が生じる、と断言するだけの論理のどこがカント的なのだろう。『玄語』の初めの言葉を記しておこう。「蓋人之為生 必染於所習 染於所習 則失其所素 是以 俗習之蔽 学為之砭鍼 学習之蔽 殆擲薬石 染之也易 素之也難 蔽之也易 復之也難(人は生きる限り必ず習いに染まる。習いに染まれば素を失う。俗習の蔽は学によって治療し得るが、学習の蔽は殆ど治療がおよばない。染めるのはやさしいが、素にするのはむずかしい。蔽(おお)うのはやさしいが、もとに復するのはむずかしい)」。さらに最後に、素朴であるが本質的な18世紀初期の日本の思想書(あるいは人生書)『葉隠』から「知」に関するいくつかの言葉を記しておこう。「少し理屈などを合點したる者は、やがて高慢して、一ふり者と云はれては悦び、我いまの世間に合はぬ生れつきなどと云ひて、我が上あらじと思ふは、天罰あるべきなり。何様の能事持ちたりとて、人のすかぬ者は役に立たず」「物が二つになるが悪しきなり」「智慧・利発ほどきたなきものなし」「智慧ある人は、実も不実も智慧にて仕組み、理をつけて仕通ると思ふものなり。智慧の害になるところなり。何事も実にてなければ、のうぢなきものなり」「物識りの道に疎き事は、東に行く筈の者が西へ行くがごとくにて候。物を知るほど道には遠ざかり候。その仔細は、古の聖賢の言行を書物にて見覚え、見解高くなり、はや我が身も聖賢の様に思ひて、平人は虫のように見なすなり。これ道に疎き所にて候。道と云ふは、我が非を知る事なり」。
ついでに、14世紀最末期の芸道書『風姿花伝』より―「ただ誠の花は咲く道理も散る道理も心のままなるべし されば久しかるべし」――――――――――。
ヨーロッパ、ペルシャ(イラン)、インド、エジプト、メソポタミア、中国、日本―― 大まかにこんな過程をたどった。
そして、或る特異な現象に気づく。
すなわち、過去数千年にわたる人類の、全地球的規模の文化現象を総観したとき、どうも、そこには、抽象概念をまるで物体のように思考し表現する人間たちがいる。その思考作用において、言葉が、言葉それが、まるで客観的に、自分を離れて、存在する物体のように作用する人間たち、言葉が自分を離れて浮かんで在る透明な物体のように対自的に存在化する人間たち、がいる。そして、その人間たちの共通項・共通特性を捜したとき、どうも彼らはインド・ヨーロッパ語族なのである。
西暦紀元前3000年(あるいは4000年)頃、後世においては南ロシアや東ヨーロッパと呼ばれる広い地域、すなわち、黒海北部のウクライナと呼ばれる地域や、あるいは少し西寄りの東ヨーロッパ方面までも含めた地域に、或る人間たちが生活していた(ただし、この時期と地域は、あるいはそうとも言える、といった程度の極めて漠然としたものである。場所や時期の特定はここでの問題ではない)。やがて、その人間たちは、牛や羊などの放牧のためか、あるいは次々と土地を変えての農耕のためか、あるいは部族内の闘争や他の系統の民族に逐われたか、あるいは気象その他の自然条件によるものか、あるいはそれが遺伝的特性なのか、あるいは他の何かの要因があるのか、彼らは、やがて、徐々に、徐々にその居住地を移動させていった。100年単位、1000年単位で測られるような、緩慢な、緩慢な浸透性をもって、徐々に、徐々にその居住域を移動していった。或る集団は、カフカス山脈を越え、アナトリア(トルコ)方面へ、或る集団は、多分カスピ海北部を迂回して、後世にはアフガニスタンと呼ばれる国のあるあたりの地域をぬけ、インド方面へ。或る集団は、これも多分カスピ海北部を迂回して、後世にはイランと呼ばれる国のあるあたりの地域へ。また別の集団は、バルカンとも呼ばれるあの半島をぬけ、ギリシャ方面へ。また或る集団は、西へ、すなわち後世にはヨーロッパと呼ばれるあの地域へ――。その移動は、永い永い歳月をかけ、永々と行われた。たとえば、この集団の一部がインドのインダス河流域へ辿りついたのは、西暦紀元前16・7世紀頃といわれており、たとえば紀元前3000年を起点に考えれば、前16世紀として、1500年の歳月が流れているわけである。
この、各地へと移動していった集団は、その言語のあり方、すなわち、或る対象をどのような音で表すか、あるいは、言語による表現過程のあり方そのもの、に広範な共通性を示している。――もっとも、現実になされた歴史的判断過程においてはそれとは逆の順序で思考がなされた。すなわち、あるとき、地球上の広範な地域でさまざまな民族・さまざまな国民として分類されつつさまざまな言語を用いて生活している多くの人々のその言語間に類似が気づかれた。よくあげられる例で言えば、日本語で「うま(馬)」を意味するサンスクリット語、ペルシャ語、ギリシャ語、イリュリア語、タレントゥム語、ゴール語、アイルランド語、ウェールズ語、ゴート語、ラテン語などの諸言語間の単語の類似。そうした類似は、単に語彙のみにとどまらず、文法に関しても多くの例が認められた。そして、そうした類似を説明するためには、たとえば前記「馬」のような、それらの諸単語が派生してきたであろうところの単一の源たる語が想定され、そうした作業はただ語彙の問題のみにとどまらず、すなわち、音韻、語形、文構造などの言語のあらゆる部分にわたってこころみられ、その結果、単一の源たるそれらの総体、すなわち、それら諸言語の単一の源たる「共通言語」が想定された。その「共通言語」の再建は事実上不可能と言ってよいほど困難ではある。しかし、そうしたものがあったであろうという想定はなし得た。その結果、それらの諸言語を用いている人間たちの遠い先祖に、それがいつなのかは明確には分からないが何千年もの遠い昔に、その「共通言語」を用いて、それがどこなのかは明確には分からないが或る程度の特定性をもった地域で、その集団固有の思考類型や行為類型、さらには信仰類型、を有して生活していたであろう人間の集団が想定されたのである。
この、言語の共通性、言葉による思考や表現のあり方の共通性に貫かれた人間群や言語群は、一般に、「インド・ヨーロッパ語族」とよばれている。その調査と判断がなされた時期に、その言語を用いる人間たちが、広く、東はインドから西はヨーロッパに生活していたからである。
「インド・ヨーロッパ語族」という言葉は、或る共通の表現過程を示す言語の総称として用いられる場合もあれば、その言語を用いている人間たちの意味に用いられる場合もある。そこで、ここでは、混乱を避けるため、それが言語群の総称として用いられる場合には「インド・ヨーロッパ言語族」、それを用いている人間たちを表す場合には「インド・ヨーロッパ語族」と記すことにしよう。
この、インド・ヨーロッパ言語族に属す言語から、或る程度著名な言語を列記すれば次のようになる。
すなわち、インド・イラン語系統では、ヒンディー語、ベンガーリー語、ペルシャ語(イラン語)、アフガン語等。日本では仏教典の原語としてよく知られる昔のサンスクリット語(梵語)やその俗語の一つたるパーリ語などもこの系統である。スラブ語系統では、ロシア語、ポーランド語、チェック語、スロヴァキア語、ブルガリア語等。ギリシャ語系統では、ギリシャ語。イタリック語系統では、イタリア語、ルーマニア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語等。昔のラテン語はこの系統である。ケルト語系統では、アイルランド語、ウェールズ語等。ゲルマン語系統では、ドイツ語、オランダ語、英語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語等。さらに、20世紀においてこれらの言語がその社会で或る程度の支配的影響性をもって使用されている地域を20世紀の主な国名を用いて列記すれば。インド、パキスタン、アフガニスタン、イラン、ロシア、ポーランド、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ等。すなわち、インド、イラン方面から、ロシア、ヨーロッパ東部、バルカン半島方面。さらに、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、イギリス、アイルランド、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストリア、ドイツ、イタリア、スイス、フランス、スペイン、ポルトガル。すなわち、ヨーロッパ全域。さらには、大西洋を渡って、カナダ、アメリカ合衆国、メキシコ。すなわちアメリカと呼ばれる大陸の北部全域。さらには、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、ベネズエラ、コロンビア、ブラジル、チリ、ペルーその他。すなわち南アメリカ大陸全域。さらには太平洋を渡って、ハワイやニュージーランドやオーストラリアその他。さらに太平洋を渡ってアフリカ大陸最南部、すなわち南アフリカなどでも或る程度の支配的影響性をもって用いられているだろう。ただし、或る言語が用いられている地域の境界を明確に、ましてや国境をもって明確に、定めることは不可能であり、また、或る地域、或る国内部においてもさまざまな言語が併存的に用いられていることは言うまでもない。
インド・ヨーロッパ語族は、言葉が、自分を離れて浮かんで在る透明な物体のように、対自的に存在化する。言葉が全知覚中枢系(視覚や触覚その他あらゆる外的・内的知覚中枢系)との関係で「在(あ)り」という対自作用を生じさせ、そこに「在(あ)る」のはそうした対自作用を生じさせているそれ、すなわち言葉、という現象である。
要するに、インド・ヨーロッパ語は、言葉が透明な物体のように存在化して作用する物化言語なのである(これが明瞭に現れるのは見ることも触ることもできない抽象概念に関してであるが、問題は言語一般に関することである)。では、インド・ヨーロッパ語族における言葉の対自的存在化・言葉の物化とは何なのであろうか。
音がどのような脳ニューロン反応をひき起こすかという見地、すなわち、音覚中枢たる言語中枢という見地から分類したとき、人類の言語は自然言語と非自然言語に分類される(→『第二部 脳ニューロンの反応としての言葉』)。この自然性・非自然性は、音(おと)の関係での、右脳的・非言語脳的――言語中枢は片脳的(多くは左脳的)なわけであるから、その意味では、それは、言語を片脳的・左脳的・言語脳的なものに偏向することを抑制する全脳的――抑制の有無の問題であり(自然言語では(言葉を知らない)赤ん坊の笑い声や泣き声その他の(言葉以外の)人声や動物や虫の鳴声や海の音といった自然音の関係を左脳・言語脳に作用させることにより、言語に全脳性を維持しようとする機能が働いている。非自然言語の言語音にはその機能がない)、すなわち、この場合の自然性とは言語の即自性(左脳性(言語脳性)・対自性に対する右脳性・即自性的抑制、その影響作用)すなわち全脳性ということであり、非自然性とは言語の対自性(左脳性(言語脳性))すなわち片脳性、ということであり、音覚中枢たる言語中枢という観点、すなわち、言語音の質という観点から人類の言語を考えた場合、その語音自体に右脳的(全脳的)影響・抑制機能が含まれ働いている全脳型言語(自然言語:日本語その他)とそうした影響・抑制機能の働かない片脳型(言語脳型・左脳型)言語(非自然言語:ヨーロッパ系言語・アラビア語・中国語その他)があるということなのである。それと同じように、言語中枢系たる音覚中枢系と他の全知覚中枢系(たとえば視覚中枢系や触覚中枢系その他の全外的・内的知覚中枢系)との関係という見地から人類の言語を考えたとき、そこにもやはり、右脳的(非言語脳的)影響・抑制機能(言語に全脳性を維持しようとする機能)の働いている全脳型言語(自然言語)とそうした影響・抑制機能の働かない片脳型(言語脳型・左脳型・対自性型)言語(非自然言語)があり、インド・ヨーロッパ語における言語の対自的存在化・物化とは、そうした後者の、言語中枢たる音覚中枢と他の全知覚中枢との関係における言語の非自然性の、現れなのである(つまり、他の全知覚中枢系との関係において「在(あ)り」という対自性が作用し、そうした対自性が作用するからこそそれは「在(あ)り」、自分を離れ浮かぶ透明な物体のごとく言葉が存在化する。そこに右脳的(非言語脳的:すなわち言語を全脳的なものにしようとする全脳的)影響・抑制機能が働いていないのである)。
すなわち、言語中枢系たる音覚中枢系と他の全知覚中枢系との関係、という観点から人類の言語を分類したときにも、やはり、人類の言語は自然言語と非自然言語に分類され、非自然言語としてはインド・ヨーロッパ語があり、自然言語に属するのはその他のあらゆる言語である。
その関係を表にまとめれば。
自然言語・全脳型言語――日本語
非自然言語・片脳型(言語脳型)言語・“かのもの”が存在する言語――インド・ヨーロッパ語
非自然言語・片脳型(言語脳型)言語・“かのもの”が存在しない言語――アラビア語、中国語その他
ということになる。
つまり、語音の質という観点からも言語中枢と他の全知覚中枢との関係という観点からも、日本語は典型的な全脳型(右脳型・非言語脳型)言語であり、インド・ヨーロッパ語は典型的な片脳型(左脳型・言語脳型)言語であり、アラビア語や中国語その他はその中間的なものである。
その場合、インド・ヨーロッパ語はもっとも言語脳的・左脳的・理性的な、最も進化した最も言語らしい理想的言語であり、日本語は最も非理性的な、言語らしくない、進化に取り残されたような言語と言うことも可能であり、また一方、インド・ヨーロッパ語は現実から遊離し言語機能自体が自己崩壊する危険性の最も高い言語であり、日本語はそれに対する全脳的抑制機能・安全機能が最も完全に備わった、生命体として最も進化した、最も理想的な言語であると言うことも可能であり(疾病自覚性欠如は右脳損傷の場合に多いという症例報告があり、自分自身の異常に自分で気づく機能、脳自体の異常に気づく脳の中枢は右脳(非言語脳)にあるものとおもわれる。ただし、ここで問題にされているのはあくまでも言語機能に関する全脳性・片脳性である)、また、アラビア語や中国語その他はその二者の中間的な、最も中庸を得た理想的な言語であると言うことも可能である。しかし、そうした言い方が可能であったとしても、これは言語に関する右脳的・全脳的影響・抑制の程度の問題であり、言語に関する右脳的(非言語脳的)・全脳的影響・抑制がどの程度であることが最も理想的であるのかの判断は誰にもできないわけであるから、その意味で、どの言語が言語として最も優れた理想的なものであるのかの議論は意味がない。ただ、それぞれの言語にそうした特性があるということ、とりわけインド・ヨーロッパ語に(あるいはインド・ヨーロッパ語族に)そうした特性があるということが重要である。また、言語におけるこうした影響・抑制機能は、言語自体の問題なのか、物的機構上の問題、すなわち遺伝的要因も働いているのかに関しては、生物学的に言語を考えた場合、何らの遺伝的要因も働いていなければ、それが何万年前なのか何十万年前なのか詳しく分からないが、そうした言語の発生自体を説明することはできないわけであり、何らかのあり方で遺伝的要因も働いているのかも知れない。ただし、それは、それが遺伝的にインド・ヨーロッパ語族であればどのような言語生活をおくろうと常に絶対的に作用するというような類型のものではなく、その言語に応じて、何らの作用も示さず、その言語に機能として組み込まれてしまうような類型の遺伝的要因、つまり、言語環境に応じて発動し言語環境に応じて喪失するような―そんな遺伝的要因で出ある可能性も十分に考えられる。
インド・ヨーロッパ語は言葉が、浮かぶ透明な物体のように対自的に存在化する物化言語であり、インド・ヨーロッパ語族においては言葉が、浮かぶ透明な物体のように対自的に存在化する。
![]()
スフィンクスが聳え立つ古代エジプト。
このエジプトにその昔或るひとりの特異な男が生まれた。
時代はエジプト新王国・第18王朝期(前1552―1306:ただし、以下古代エジプトに関する年記は必ずしも正確なものではない)。
この男は、やがてエジプトのファラオになった。「ファラオ」とは、要するに「王」であるが、元来はこの言葉は「大きな家(ペル・アア)」という意味のようである。
このファラオの名はアメンホテプ4世という。
この男は新王国第9代目のファラオであり、その治世は紀元前1364―47とも言われている。
この男の何が特異であったのか。
それは、この男が生み出した宗教、この男に起こり、そして表現された或る信仰が当時のエジプトとしては極めて特異なものだった。
古代のエジプトは、言うまでもなく、ラーや、オシリスや、アモン、イシス、トト、ホルスその他雑多な神々が混在する多神教の世界だった。
その古代エジプトで、この男は、ある日、唐突に、唯一絶対の神への信仰を抱いた。つまり、この男の脳にそうした現象が起こったのである。
彼が信仰した神の名は、「アトン(あるいは、アテン。もしくは、アトゥム)」―彼の信仰した神は、当時のエジプトとしても古き神、ヘリオポリス(メンフィス遺跡の北約25km:エジプト名は『旧約聖書』では「オン」と記される)の太陽神・創造神アトゥムと密接な関係がある。密接な関係があるというよりも、その、古代からの復帰なのである。アトン(アトゥム)は太古から帰ってきた。混沌たる原初の深淵たる海ヌンから自らの力で、「独りでなった」アトゥム。そして、誰の力もかりずに。ただ独りで、シュー(空気)やテフヌート(湿気)やゲブ(大地)やヌート(空)を、すなわち、全存在物、天地万物を産み出した創造神アトゥム。ゲブやヌートらのエグアド(九神)の名を産み出すことで世界を創ったともいわれるアトゥム……。そして、このアトンは創造神であるとともに太陽神でもあった。ちなみに、この「アトン」という言葉は、「すべてのもの」を意味すると同時に「無」をも意味したそうである。つまり、「アトン」とは、完璧な成就であり、なにかが「在る」という相対性を生じさせない完璧な「ある」だった。それは始めであり、終わりであり、アルファであり、オメガだった。この天地万物の創造神であり、そして太陽神でもあるアトンをこの男は崇拝した。アトンは万物の創造神であり、そして唯一の神なる神だった。彼はこの神への賛歌において「おお御身 並ぶものなき唯一の神よ」と歌った。「並ぶものなき」とは、相対性が生じないという意味である。さらに、墓壁に彫られ遺されたアトン賛歌の一部を記せば次のようなものがある。すなわち、「御身はわが心の中にあり」「この世は御身の手にかかり 御身のつくり給いしままに生まれ出でしなり」「御身は終生御身自身なり 御身によってのみ生くるものなればなり」「目は御身の沈むまで御身の美しさに向けらる」「おお独りの神よ よそものなきもののごと!」「御身独りありしまに御身思いのままにこの世を創り給えり」…。彼は、「アメンホテプ:アメン(あるいは、アモン)は満足する」という自分の名を拒否し、これを「イクナートン(イク・エン・アトン:「アトンの意に適うもの」あるいは「アトンはそれを欲す」)」と変えてしまった。「アメンホテプ4世」は「イクナートン」になったのである。さらに、彼は国中のそこここの碑文の刻名から、しかも自分の父親アメンホテプ3世の名に見られるものまでも、「アメン」の名を削り消し去ってしまった。さらに、古い記念碑などをも調べさせ、多神教を表す「神」の文字の複数形をも消し去ってしまった。彼の拒否が最も強くあらわれたのは当時最も大きな勢力をもっていたアモン神に対してであった。しかし、彼はアモン神のみを拒否したのではない。他の神々の祭祀も停止され、国中いたるところで神殿は閉鎖され、神殿領は没収された。さらに、彼は伝統的なテーベを去り、アマルナに首都を遷し、居所を建設し、アトンの神殿を作り、この首都を「アケト・アトン:アトンの地平線」と命名した。
アトンは唯一絶対の神だった。彼のアトン信仰は他にもさまざまな特性をもっている。
まず第一に、彼は、神の、すなわち崇拝対象の、いかなる彫像も作らなかった。すなわち、崇拝対象を視覚的に表現することをしなかった。崇拝対象は見えなかった。彼の言うところによれば、「真実の神は形をもたない」のであって、彼は終生それを守り通した。さらに、彼の信仰においては、「マアト:「正しさ」あるいは「正義」あるいは「真理」」が極めて重視された。彼は、自らの碑文に必ず自らを「マアトに生きる」と表現し記した。さらに、彼の信仰では、神話、魔法、呪術の類が全て排除された。すなわち、迷信的な、非科学的な思考・信仰過程に忌避的だった。アマルナ芸術も、非科学的・類型的な表現は排除され、写実的なものとなった。さらに彼の信仰では、死後の世界・彼岸の世界(あの世)や葬祭が否定され、古代エジプトにおいてあれほど重要な位置をしめていた死の国の支配者オシリスなどは全く無視された。さらに、付随的に、碑文用の公式用語に口語が採用されるという現象も起こっている。つまり、伝統的権威ある公の様式性に束縛されず彼の肉体から自然に現れる言葉―それをそのまま彼は神に捧げようとした。
彼の信仰は国中に極めて強い抵抗をひき起こした。それによる反動もあり、彼は次第に国の内政や外政に熱意を示さなくなり、国は混乱し、17年ほどの治世の後、彼の死後、その信仰を思い出させるようなものはことごとく破壊され、アマルナは廃墟となった。この過程で、とりわけアモン神官団による。アトン信仰者への復讐により、あるいは暴力行為などもあり、死者なども生じたことだろう。我々は、今は、遺跡に残された痕跡の断片からかろうじて彼の信仰を知ることができるだけなのである。
彼の信仰は特異であり唐突だった。
では、何故彼は唐突にそのような信仰を抱いたのであろうか。
彼の脳にどのようなことが起こったのであろうか。そして、それはなぜ起こったのであろうか。それを考えるには、まず、唯一絶対の神への信仰、すなわち、「一神教・monotheism」、とは何なのか、それはどのような過程(脳の反応過程)なのか、を考える必要がある。脳の反応過程とは言っても、どの脳ニューロンがどのように反応するかということが実験的に検証されるわけではない。各自の脳をモニターとした体験として、どのような脳の反応過程なのか、ということである。
一神教においては、唯一絶対の神が無から有を、無から全存在・森羅万象の全てを創造し絶対的な全秩序を創造する。そして、その絶対的な創造神を信仰というあり方で思考しているのは(その絶対的な創造神が信仰というあり方で脳ニューロン反応となっているのは)その信仰者自身である。すなわち、唯一絶対神信仰においては、その信仰者自身として―その信仰者として現れた具体的な人間の脳におけるニューロン反応として―無からあらゆる有を生み出す絶対的な創造神がある。つまり、その信仰者の人格が絶対的な創造神の現れとなり、彼・彼女は創造神となる(その意味で唯一絶対神信仰は無からの人格の創造である)。自らが絶対的な創造者となっていくこの過程―これは、精神分析学で言うところの、「ナルシシズム」である。「ナルシシズム」という言葉はギリシャ神話に由来する。その昔、ナルシスという美しい若者がいた。多くのニンフ(乙女の姿をした精霊)が彼に恋をした。しかし、彼は人を恋するということを知らなかった。そのために、彼に恋い焦がれたニンフ・エコー(木霊(こだま))はとうとう痩せ衰え、消えはて、ただ声だけになってしまったりもした。彼の薄情さは神々の怒りをかい、ある日、彼は、復讐の女神により、彼にも「恋しい」という思いがわかり、しかもそれがけして報いられることのないように、との呪いがかけられた。あるところに美しい泉があった。ある日、ナルシスはそこを通りかかり、喉がかわいたので泉の水を飲もうとした。そしてそのとき、彼は鏡のように清らかな水面に映った自分の影に目を奪われ、そして恋をした。彼は自分を捉えようとした。しかし、影を捉えることは出来なかった。彼は自分の姿から目を離すことが出来なくなった。つまり、彼は自分しか見えなくなった。彼は、永遠に報われることの無い自分への恋にやつれ、そして死んでいった……。この神話を考える場合、ナルシスは神々の呪いを受けたのだということも記憶しておく必要がある。
「ナルシシズム」という言葉はそんな神話に由来する。この神話に由来し、或る精神医学者が、人間の或る状態を「ナルシシズム(ナルシス的状態・作用)」と表現した。では、「ナルシシズム」とはさらに一体どのような過程なのであろうか。一般的には、「ナルシシズム」は「自己陶酔」と言われている。フロイト的な表現をすれば、「対象リビドーが全て自我(Ich:私)へと撤収される状態」ということになるだろう。客観的な、(リビドーの流動という)仮定システム的な言い方をすれば、そうしたフロイトの言い方も正しいのだろう。しかし、そうした表現は、結局のところ、ナルシシズムとはナルシシズムである、という意味しか果たさない。ここでは、「ナルシシズム」を科学的に、仮定システム的に、言い換える作業を行うつもりはない。たしかに、ナルシシズムには、自己陶酔し外界への関心が失せる、という印象がある。しかし、この現象は、ただ単に、外界への関心が失せ、意識が全て内側へ閉塞してしまう状態を表すわけではない。仮に、ただ単に外界への関心が失せるだけの状態があるなら、それは、ナルシシズムへ向かう途ではあっても、けしてナルシシズムではない。意識の内側への閉塞―それはナルシシズムの、一面的な、いわば外側からの、表現であり、その内側から、ナルシシズムそれから、表現した場合、ナルシシズムとは、すなわち、「私(わたくし)」の全体化・絶対化である。「私」がすなわち全世界・全宇宙・全存在それとなる。「私」が全世界・全宇宙・全存在なのである。それがナルシシズムである。外界への関心が完璧に消滅するとまさに同時に(外界への関心が完璧に消滅するその過程として)、あるいは、外界が全く無意味化するとまさに同時に(外界が全く無意味化するその過程として)、内界が、「私」が、外界それ、全存在それ、意味のすべて、となる。「私(わたくし)」がすべてとなる。それがナルシシズムである。その場合も、同時に二つの現象が起こるわけではない。或る現象が、或る認識のあり方からは内界への閉塞と表現され、或る認識のあり方からは内界の全体化と表現される。さらにこれは、人間の内と外、内界と外界が何ら意味作用を果たさない認識のあり方において表現すれば、「可能性の消滅」ということになるだろう。そこには、可能性消滅の可能性以外、いかなる可能性もない。「私」がすべてであるそこでは――言葉は人間相互の、「私」相互の、関係性をあらしめる生命普遍的な過程によりその正しさ、その意味性は維持されており――「私」が絶対化し調和性と同義たる関係性の絶望化したそこでは、「ナルシシズム」という言葉の意味可能性も消滅する可能性がある。すなわち、それが何らかの意味作用を果たし得る可能性も消滅する可能性がある。したがって、そこでは、この状態を「ナルシシズム」と表現することはこの状態を表さない(つまり、「ナルシシズム」と表現される過程(「ナルシシズム」と表現される状態となった人)においては「ナルシシズム」という言葉も何の意味作用も果たさない)という現象すら起こり得る。ナルシシズムとはそれほどに自己絶望的な過程であり、そうした、自己絶望的な言葉として、この過程を「ナルシシズム」と呼んでおく。すなわち、ナルシシズムとは、自我への、「私」への、絶対的閉塞であり、自我の「私」の、絶対化、絶対的全体化であり、そして可能性の消滅・絶望化である。ナルシシズムは、ただ単に、自分の美しさや正しさに酔う、自惚れる、というような牧歌的な現象ではない。
しかも、ナルシシズムにはさらに本質的な問題が含まれている。そして、これに関する認識がナルシシズムに関する認識の最も本質的な部分である。
ナルシシズムは「私(わたくし)」の絶対化である。
では、自我の絶対的全体化がイクナートン(アメンホテプ4世)において何故生じたのであろうか。
そこには、彼が生まれながらの世界帝国のファラオだったということももちろん影響しているだろう。
エジプト新王国は異民族ヒュクソスの支配を打倒することによって成立した王国であり、新王国のファラオはその異民族を追うように、そして異民族の侵入からエジプトを守るための広大な軍事的緩衝地帯を作るかのように、そして後には莫大な戦利品その他をめざして、東方へ、アジア方面へと支配を拡大していった。とりわけ、イクナートンから4代前のトトメス3世は積極的に植民地政策を行い、ユーフラテス河まで版図を拡大し、異民族を包括した世界帝国を形成した。彼イクナートンはそんな環境に生まれ、そして育った。彼は生まれながらの帝王であり、帝王の、ましてや世界帝国の最高命令者の、意識や思考感覚が全体化していくことは決して珍しいことではないだろう。
しかし、エジプトに限らず、人類史上、帝王は全地球上各地に多数あり、彼が帝王だったから、というただそれだけではここで起こった事態を説明することはできない。
問題はそれだけではないのである。
彼は崇拝対象の視覚化を拒否した。あるいは、視覚化が全く問題にならなかった。彼は野天で、すなわちただ大自然の中で、太陽へ向かって、すなわち光を見つめ、祈り、供儀を行い、賛歌を捧げた。彼は「正義」や「真理」と訳される「マアト」に極めて強力に支配されていた。彼は死後の世界を問題にしなかった。かれは呪術や魔法を信じなかった。彼は自分の肉体から何の抵抗もなく生まれる言葉をそのまま神に捧げようとした。彼は太陽にむかって供儀を行った。彼の崇拝対象は物体としてのあの太陽であろうか。いや、そうではない。太陽神崇拝はエジプトには遥かなる太古からある。イクナートンの祖父にあたるトトメス4世や父親にあたるアメンホテプ3世もラー信仰やアトン信仰を行っている。トトメス4世は、ラーの召命で即位し、アトンの名でアジアを征服した。しかし、全く同じ「アトン」という神に祈り、信仰を捧げたとしても、祖父や父親のそれと、イクナートンのそれとは全く次相(次元)の異なったものとなっている。イクナートンの信仰がエジプト全土にひき起こしたような激しい抵抗や混乱は祖父や父親はひき起こしてはいない。中近東専門のアメリカの古代史学者ブレステッドは『エジプト史』の中でこう言っている。「(イクナートンの信仰)それは決して単なる太陽崇拝ではなかった。というのは、アトンという語は「神(Nuter)」にあたる古語の代わりに用いられたものであって、神は物質的な太陽とは明らかに区別されている」。彼は太陽を崇拝したわけではない。物的なあの太陽は、ただ単に、彼の「信仰」と表現される過程を表現し、満たすための、ひとつの道具としての対象に過ぎない。
では、相対化の生じない、唯一絶対たる彼の崇拝対象は一体何だったのであろうか。
彼は崇拝対象を視覚化しなかった。
彼には崇拝対象の視覚化に関し強迫的な忌避が起こっていた。
何かに関し視覚が作用しない場合―光が作用しない場合―通常それは「無い」。
しかし、彼には唯一絶対なる崇拝対象は確かにあった。
確かにそれは作用していた。
なぜ彼は崇拝対象を視覚化しなかったのであろうか。
崇拝対象の視覚化が問題にならない状態、崇拝対象の視覚化が強迫的に忌避される状態が彼になぜ生じたのであろうか。
対象の視覚化を拒否した場合、あるいは、知覚に関し対象の視覚化が問題にならなくなった場合、そこには何があるであろうか。
何が作用しているであろうか。
それは、音(おと)である。
音(おと)の記憶である。
音(おと)の作用である。
それも、存在化し得る音(おと)、存在となり得る音(おと)、対象となり得る音(おと)、対象それである音(おと)、である。存在化し得る音(おと)、あらゆる存在となり得る音(おと)―すなわち、「言葉」である。
言葉が、自分を離れ客観的に、対自的に存在化する物的存在感、物的存在作用をもって思考過程、全知覚過程に支配的に作用し、しかも、全言葉・全抽象概念の正しさを表す一般的言葉・一般的抽象概念、全世界・全宇宙・全存在を正しく一般的に包括する一般的抽象概念―すなわち「真理」、すなわち「マアト」―これが物的存在性をもって過程に支配的に作用し絶対的全体化を果たしたとき、その、言葉が物的存在性を帯びた過程が、絶対的「私」の擬人的対自的存在化作用をも果たし、「絶対」の、すなわち何の相対性も生じず何の条件も付されない「自由」の、計り知れぬ快感に促迫されつつ、神格化と呼ばれる無いが在る何か(これが神)に対する崇拝と陶酔の状態が生じ、一神教現象が生じる。それが唯一絶対神信仰であり、一神教である。そして、そのとき、その唯一絶対として崇拝された(される)「言葉」は、自らの言葉、すなわち「私(わたくし)」の言葉であり、その唯一絶対として崇拝された(される)神格化は、結局のところ、絶対的な、絶対的に全体化した、自分自身、すなわち「私(わたくし)」の神格化である。そこにはただ自分自身の絶対化と自分自身への絶対的崇拝がある。ナルシシズムの本質的起動因・現象因は言葉なのである。言語なのである。言葉の或る作用の仕方、言語の或る作用の仕方なのである。言葉の或るあり方により一神教は生じる。そして、一神教によりその「言葉の或るあり方」は生じる。なぜなら、その「言葉の或るあり方」が一神教なのであるから。
今、言葉が物的存在性をもって過程を支配する、言葉が物的存在作用を果たす、と言った。すなわち、「言葉」が客観的に存在する物体のように作用するのである。
では、イクナートンにおいて何故そのようなことが起こったのであろうか。
ここで、インド・ヨーロッパ語族に関する問題が生じる。
インド・ヨーロッパ語族においては言葉が浮かぶ透明な物体のように対自的に存在化することを前に述べた。それがここでも問題になるのである。
エジプト人は言うまでもなくハム語族であり、インド・ヨーロッパ語族ではない。
しかし、イクナートンの父親はアメンホテプ3世であり、母親はティエという女である(このティエという女は民間の(神官の)娘であり、ファラオがこうした、いうなれば素性の卑しい、女を后とすることは当事としては極めて珍しいことだった)。さらに、このアメンホテプ3世の父親(つまりイクナートンの祖父)はトトメス4世である。このトトメス4世は、東方のミタンニの王アルタタマと和親条約を結び、さらに、その娘ムテミヤを后として迎えた。このミタンニがインド・ヨーロッパ語族である。つまり、ムテミヤはイクナートンの祖母であり、イクナートンはインド・ヨーロッパ語族との三世混血児である。ただし、この点に関し問題は微妙であり、歴史書の中にはアメンホテプ3世はトトメス4世とムテミヤの子としているものもあれば、この問題を微妙に避けているものもある。つまり、イクナートンの父親アメンホテプ3世がトトメス4世の子であることは確かなことであり、トトメス4世がミタンニ王女を后に迎えたことも確かなのであるが、アメンホテプ3世はトトメス4世が記録には無い他の女に産ませた子供である可能性も必ずしも捨てきれない、ということなのである。しかし、このイクナートンに現れた極めて例外的な現象の特異性を考えれば、この男にはインド・ヨーロッパ語族の血が流れていると考えることが情況として妥当である。さらに、仮に祖母の系列からその血が流れていなかったとしても、民間人たる母親ティエの系列あたりからでも、必ずそれは流れこんでいるだろう。前にも述べたように、この時代のエジプトは東方に深く進出し、東方からも多くの人々が出入りし、民族的流動が極めて盛んな時代だったのである。イクナートンが幼少年期に何を学び何を考えていたのかに関しては、記録も無く、何も分からない。それはブッダほどにすら何も分からない。しかし、当時のエジプトの帝王の子として学ぶべき最も重要なことは、やはり、神に関することだろう。その環境という点から言っても、インド・ヨーロッパ語族たる祖母や、后となる際に伴ってきたであろうその多くの従者たちや、その祖母の子たる父親の影響、そしてインド・ヨーロッパ語族とも民族的交流が盛んだった当時のエジプト社会―そうしたことを考えれば、インド・ヨーロッパ語族の神、その信仰のあり方が家庭環境や社会環境として何らの影響も与えていないと考えることはむしろ不自然である。
ちなみに、イクナートンの信仰に関しては一般に、政治的経済的に極めて大きな権力を握ったアモン神官団に対抗するために生じた現象、と言われている。しかしながら、「他の神」や「他の人」に対抗するため、という動機からは一神教過程は生じもしなければ維持もされない。ナルシシズムにおいては「他の神」や「他の人」は前提過程にはならないのである。「他の神」への強力な対抗として生じるのはただ単に「単一教・henotheism」であり、「一神教・monotheism」ではない。「単一教」とは、多くの神々の中からただ一つの神を(ときには主神として)崇拝するあり方の信仰である。もし、「他の神」や「他の人」に対抗するという極めて政治的な配慮がイクナートンの動機であるなら、あの内政や外政一般にわたる彼の一般的無関心やそれによる国政の混乱は何なのであろうか。
そこで、次に問題となるのが、同じように唯一絶対神への信仰をしめすユダヤ教とこのイクナートンの信仰との関係である(言うまでもなく、後世には、この「ユダヤ教」と呼ばれる信仰の変容的自己展開としてキリスト教があらわれ、さらに後には、それらのさらなる変容的自己展開としてイスラム教があらわれる)。
これに関しては、「関係はあるかも知れないが、明確には何とも言えない」というのが現在最も一般的な見解だろう。
この両者の関係を考える場合、最も重要なのは、ユダヤ教における偶像崇拝の否定、偶像の忌避、である。
「偶像」という言葉は、その漢語自体は、土、石、金属等の物的材料により何か(たとえば或る人間)に似せそれを表すように作ったもの、を意味するが、日本語の日常会話においては、この言葉は一般に、「無意味な像」「無価値な対象」という意味で使われる場合が多いだろう。しかし、ユダヤ教、すなわち『旧約聖書』における「偶像」とはそうした意味ではない。「偶像」はヘブライ語では、すなわち『旧約聖書』の原典では、「ペセル」。これは「刻んだもの」を意味し、ここで「刻む」とは、崇拝対象を物的に作り現すことを意味する(「マッセカア(鋳たもの)」という言い方もある)。崇拝対象を作ってはならないわけではない。エホバ(ヤハウェ)は崇拝対象なのである。『旧約聖書』における偶像の忌避、偶像崇拝の否定や禁止とは、それを(崇拝対象を)、物的に作り現すことが忌避され、否定されることである。それは自分が信仰する神の像なら許されるが、異教の像は許されない、すべて破壊せよ、というものでもない。自分が信仰する宗教であれ、異教であれ、何であれ、崇拝対象を物的に作り現すことが一般的に忌避され否定されるのである。たとえ異教の像に対する破壊が起こったとしても、それは、異教への攻撃がその破壊衝動の本質ではなく、崇拝対象を物的に作り現すことに対する強迫的な忌避感がその破壊衝動の本質なのである。そして、物的に作り現された何かは、物体は、一般に、見える。前にも述べたように、視覚(光覚)は「在る」を作用させる存在知覚とでもいうべき作用をはたす。「偶像」はギリシャ語では(すなわち『新約聖書』の原典では)「ειδωλον・エイドロン:英語のidol・アイドルと同語源」。語頭の「ειδ‐・エイドゥ‐」は、「ιδεα・イデア」の「ιδ‐・イドゥ‐:見る、を意味する」にも通じるものであり。これも「見え」「見えるあり方」「形(かたち)」を意味する。すなわち、『旧約聖書』における「偶像」とは、「物体化され現された崇拝対象」であり、「「見え」「見えるあり方」としての崇拝対象」であり、「視覚化された崇拝対象」なのである。この「偶像」が―崇拝対象の物的顕現化・視覚化が―『旧約聖書』においては徹底的に忌避され、禁圧され、排除されている。そこには、崇拝対象の視覚化に関し極めて強い強迫的禁忌感が働いている。有名な「モーセの十戒」のその(二)がそれである。ここにその部分を転載しておこう。「あなたは自分のために、上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものに似せたいかなる彫刻像や形も作ってはならない。それに身をかがめてはならず、さそわれてそれに仕えてもならない。あなたの神であるわたしエホバは全き専心を要求する神であり、わたしを憎む者については父のとがに対する処罰を子にもたらして三代、四代に及ぼし、わたしを愛してわたしのおきてを守る者については愛ある親切を千代にまでほどこすからである。」(『旧約聖書』「出エジプト記20:4」・以下、『旧約聖書』は『旧』と記す)。あるいは、「こうして、エホバがホレブで火の中から話された日に、あなた方は何の形も見なかったのであるから、あなた方は自分の魂によく注意して、滅びとなるようなことをせず、自分たちのために彫刻像を作ったりすることのないようにしなければならない。すなわち、どんな象徴の形も、男や女の表象も、地にいるどんな獣の表象も、天を飛ぶどんな翼を持つ鳥の表象も、地面を動くどんなものの表象も、地の下の水の中にいるどんな魚の表象も。また、目を天に上げて太陽と月と星を、天の全軍を見、たぶらかされてそれらに身をかがめたり、それらに仕えたりすることのないように。それらは、あなたの神エホバが全天下のすべての民に振り分けられたものである。」(『旧』「申命記4:15―19」)「あなた方は自分に気を付けて、あなた方の神エホバと結んだ契約を忘れぬよう、また自分のために彫刻像を、すなわちあなたの神エホバが禁じられたいかなる物の形をも作ることのないようにしなさい。あなたの神エホバは焼き尽くす火であり、全き専心を要求する神だからである。あなたが子や孫の父となり、あなた方がその地に長く住んだ後になって滅びとなるようなことを行い、彫刻像を、すなわち何かの形を作り、こうしてあなたの神エホバの目に悪を行って怒りを起こさせるようなことがあれば、わたしは今日、天と地をあなた方に対する証人として立てておくが、あなた方は必ず、ヨルダンを渡って行って取得するその地から速やかに滅びることになるであろう。あなた方はそこで自分の(命の)日を長くすることはないであろう。まさに滅ぼし尽くされるからである。」(『旧』「申命記4:23―26」)などという言葉もある。十戒においてこの崇拝対象視覚化の拒否は極めて重視されている。十戒のその(一)は、私は唯一の神だ、という神の宣言であり、これが冒頭にあることは自然なことだろう。偶像否定はその次の(二)に記されている。「殺人を犯してはならない」は6番目である。しかも、文章量も安息日に関するもの(十戒のその四)と並んで多く(安息日が要求されるのは抽象的思考のための時間を確保するためである)、しかも、十戒の中でも、戒律を犯した者は三代四代までも呪い、守った者は千代までも祝福するという呪いと祝福による厳格な戒律の維持が図られているのは偶像崇拝を禁止したこの条項だけである。「殺人を犯してはならない」「姦淫を犯してはならない」「盗んではならない」などはただ一行で簡単に書かれている。崇拝対象の視覚化に関わることは人殺しよりも(生命よりも)重要なことだったのである。『旧約聖書』「出エジプト記32:27―28」あたりの叙述によれば、モーセがシナイ山に登っている間に偶像たる金の子牛をつくったために、古代のユダヤ人が三千人も殺されたそうである。ちなみに、「ユダヤ人」に関しては「ヘブライ人」や「イスラエル人」等の名称もある。「ユダヤ」は本来或る人間集団の一支族の名に由来するものであり、この名称は必ずしも正確なものではないが、最も一般的通用性のある名称としてここではこれを用いる。また、漠然と古代のそれを「古代ユダヤ人」と表現する。崇拝対象の視覚化が呪いと祝福をもって強迫的に忌避され禁圧され徹底的に排除されるというこの信仰のあり方は極めて特異なものである。前にも述べたように、崇拝対象の視覚化が否定され忌避されたとき、「契約をわたしは自分の目と結んだ」(『旧』「ヨブ記31:1」)という状態となり、そこにはただ音の作用が、言葉の作用が、ある。逆に、発生的に言えば、この十戒(二)に現れる偶像崇拝の忌避は、言葉が客観的に、対自的に存在化して作用し、唯一絶対的に神格化していることにより生じた現象である。さらには、ユダヤ教では、『旧約聖書』「レビ記19:26、31」「申命記18:10―14」などにもあるように、魔法や呪術や占い―、いうなれば非科学的な、合理性の無い過程(さらに言えば、言葉にならない過程)が拒否され、否定されている。たとえば、「あなた方は「吉凶の」兆しを求めてはならない。また魔術を行ってはならない」(『旧』「レビ記19:26」)「女呪術者を生かしておいてはならない」(『旧』「出エジプト記22:18」)。さらに、ユダヤ教では死後の世界が問題にならない。なぜ問題にならないのかと言えば、それは(イクナートンの場合もそうなのであるが)、「この者(信仰の或る者)は定めなく続く命に、かの者(信仰のない者)は恥辱に、定めなく続く憎悪に至る」(『旧』「ダニエル書12:2」)からであり、さらには、「洞察力のある者は大空の輝きのように照り輝く。多くの者を義に導いている者たちは定めのない時に至るまで、まさに永久の星のように輝く」(『旧』「ダニエル書12:3」)からである。お分かりになるであろうか。つまり、自分を離れ客観的に存在化した「言葉」は永遠に死なないからである。その結果、死後の世界は初めから問題にならない。そして最後に、一般的特性として、人のあり方として、ユダヤ教における唯一絶対神信仰とは、イクナートンの信仰と同じく、「ナルシシズム」と表現されたあのあり方である――。こうして過程の特性をひとつひとつ検討した場合、ユダヤ教と呼ばれる信仰過程はイクナートンの信仰過程から派生している、正確に言えば、イクナートンに起こり現れた信仰それ、イクナートンに起こり現れた信仰の変容的(それがどのような変容であったのかは後に問題になるが、先取りして言えば、退行化した)自己展開、という結論を出さざるを得ない。イクナートンに現象化した唯一絶対神信仰は、その本質において、抽象的(すなわち、見えない、音覚中枢たる言語中枢的)思考の極致、抽象概念の極致とも言うべきものであり(この点に関しては、彫刻や絵画肖像に残されているイクナートンのあの後頭部の異様な突出もなにがしかの関係があるだろう:脳後頭部は認識の中枢である。脳後頭部で音と光、言葉(聴覚・音覚刺激)と見え(視覚・光覚刺激)は出会う。脳生理学的に言えば、聴覚野と視覚野に左右を挟まれるように後言語野がある(前言語野は運動性言語野である)。後言語野の上には認識野が、下には記憶野がある。すなわち、言語野は、音と光と認識と記憶の中央に位置しそれらすべてを総合的に相互に連絡する中枢となる。大脳皮質に関して言えば、音と光、聞くことと見ることの相互関係に左脳的対自性が作用することにより言語中枢は発生した)、しかもそれは世界帝国のファラオの所産であり、それを、紀元前13・4世紀ころ、荒野の原始的な遊牧民やほとんど他民族の奴隷のような状態であったはずの古代ユダヤ人、しかもセム語族のユダヤ人が(たとえ仮にインド・ヨーロッパ語族たるヒッタイトなどとの混血が多少あったとしても)その内部から自生的に生み出すなどということはあり得ないことである。これは百パーセントあり得ないと言っていい。可能性はゼロである。唯一絶対神信仰というものは、実は、イクナートン→モーセ→イエス→マホメットと受け継がれ、アトン教→ユダヤ教→キリスト教→イスラム教と名を変えつつ続く単純な一本の糸であり、この一本の糸としての系列以外には、過去数千年の人類史において、唯一絶対神信仰なるものは全く現象化していない(この系において、その一本の糸から、出口のない脇道へ入るように共産主義も生じている)。この系列以外の自生的な唯一神教、唯一絶対神信仰の発生は、過去数千年の人類の歴史においてただの一例も無い。
唯一絶対神信仰というものは、その「伝播」に関しては極めて強靭な作用力を有していたとしても、その「発生」に関しては、極めて特異な、極めて稀な例外的現象なのである。ユダヤ教はイクナートンの信仰に由来する。否、過程の本質として、イクナートンの信仰それである。
イクナートンの一神教ナルシシズムが古代ユダヤ人(正確に言えば、その伝達と浸透により「ユダヤ人」が生じる)に伝達され浸透した過程(あるいは、古代ユダヤ人が見えざるそれに支配されていった過程)としては、やはり、『旧約聖書』において「モーセ」と呼ばれている男の媒介があっただろう。「モーセ」という言葉はエジプト語である。これはエジプト語で「子供」を意味する。当時のエジプトにはこの言葉を付した名が非常に多かった。たとえば、「ラムセス→ラー・モーセ」「トトメス→トト・モーセ」「プタハメス→プタハ・モーセ」…。「ラー」「トト」「プタハ」は全て神の名であり、これらはそれぞれの神の子であることを表している。『旧約聖書』「出エジプト記2:10」には「「モーセ」の名の由来として、エジプトの王女が、彼を水からひき出した(「モーセ」した)から、そう呼んだ、と書かれている―『旧約聖書』によれば、モーセは産まれてすぐパピルスの箱のようなものに入れられてナイル河にすてられ、これをファラオの娘が拾いあげたそうである―、しかしこれは、このヘブライ語が能動形で、「ひき出された」ではなく、「ひき出す」を意味することも不自然であり、また、エジプトのファラオの娘が、しかもファラオに殺せと命ぜられていたはずの(そのためにモーセは河にすてられた)ヘブライ人の子供に、ヘブライ語で名をつけるというのも奇妙である。『旧約聖書』のこの伝承は、モーセがエジプトから古代ユダヤ人たちを「ひき出した」ことに由来する通俗語源解釈に基づくものだろう。そうしたことから、モーセはエジプト人だという解釈もうまれてくる。しかし、「モーセ」という言葉がエジプト語であるというただそれだけで彼がエジプト人であると断定することはできないだろう。『聖書』によれば、モーセはうまく口がきけなかった(『旧』「出エジプト4:10」)。そこで、兄弟アロンがモーセの言うことをユダヤ人たちにつたえた。この伝承は、あるいは、アロンは、ユダヤ人の言葉をうまく話せないエジプト人モーセに代わってその通訳を行ったことの伝承とも考えられる。あるいは、「出エジプト記2:19」ではモーセを「エジプト人」とよんでいる……。しかし、結論を言えば、ナルシシズムの相互的形成過程、すなわち伝道、という点に関して言えば、モーセがエジプト人であろうとユダヤ人であろうと全くどうでもよいことである。それはユダヤ人の民族感情として問題になるだけだろう。そこで、このモーセを介し、いつ、なぜ、どのようにして古代ユダヤ人たちにその一神教ナルシシズムが導入されていったのか、が問題となる。時期としては、多分、紀元前14世紀の中頃だろう。イクナートンの死(前1347?)後、彼の内政・外政への無関心やその信仰による宗教的不寛容、すなわちナルシシズムによってひき起こされた人と人との関係相互における絶対分裂的・闘争的相克・不調和、絶対的に相容れない相互闘争(すなわちコンフリクト:この分裂的闘争関係の本質は後に問題になる)により国内は極めて混乱した。議論や口論はもちろんのこと、この分裂的闘争によりエジプト各地で死者をも生じる暴力闘争や破壊などもあっただろう。彼(イクナートン)の死後、「ツタンカートン(トゥト・アンク・アトン:アトンの生ける似姿)」(前1347―38?)がファラオとなった。しかし、彼はアトン信仰に対するあまりに大きな抵抗に会い、その後、その名を「ツタンカーメン(トゥト・アンク・アモン:アモンの生ける似姿)」に変えてしまった。都もアマルナを離れメンフィスへと移した。彼の治世は10年ほどだった(毒殺されたとも言われている)。その次のファラオはアイ(前1338―34?)。この男の治世も極めて短いものだった。このアイはもと武官である。国内の混乱を収拾するために、軍事的権力を握った人間が登場し始めたのだろう。つぎのファラオはホルエムヘブ(前1334―06)。この男も元来軍人であり、この男はイクナートンがファラオであった頃南パレスチナ駐留軍を率いていた。このホルエムヘブの権力奪取は国政の混乱を収拾するための一種の軍事クーデターだったのではないだろうか。さらに、この男は何らの王位継承権もなく実力で王位に就いたため、自己に宗教的な権威を付与する、あるいは、宗教的権威を味方につける、必要もあっただろう。そして、イクナートンの時代に辺地にいた軍人たる彼は本質的にその思考や感性は保守的であり、アトン信仰がもつ抽象的知性(抽象的知的性質)・抽象概念性などからも極めて遠い人間であり、いうなれば新興宗教たる、アトン信仰を国政混乱の原因として忌み嫌い、これに強い抵抗と嫌悪を示し、伝統あるアモンへの信仰を保護し、それへの帰依を命じ、アマルナ時代を(すなわちアトン信仰を)思い出させる痕跡の抹殺をはかりアトン信仰を、すなわちその教団や信徒を、弾圧した。この弾圧の過程で、アトン信仰に生きていた男(これが「モーセ」と呼ばれる)がエジプトを脱出したのだろう(モーセはオン(ヘリオポリス)周辺で何か神官的なことでもやっていたのかも知れない。あるいはイクナートン周辺にいた軍人だったのかもしれない)。その過程で、あるいは暴力的闘争などもあり、モーセは人を殺し官憲やらエジプトの民衆やらから追われていたのかも知れない。それが、ユダヤ人に殴りかかっているエジプト人をモーセが殺し、ファラオに追われたという『旧約聖書』「出エジプト記2:11―15」にあるような伝承になっているのだろう。このモーセの自分とその信仰が生きる地を求めての逃亡の動因と、国内の無政府的混乱状態の中で奴隷状態から解放されたいという古代ユダヤ人たちの動因。さらには、モーセにおける強靭なナルシシズムがもたらす自己の過程の他者の過程を全く前提としない支配力、あるいは他者の過程に対する絶対的壊滅力、そして自己にコンフリクトを、抵抗を、生じさせる過程へのまさに言語を絶し超越した根源的な不快(この根源的不快とその絶対的消滅への衝動がその人間を(この場合にはモーセを)強迫的に「伝道」へと向かわせる)。そして同時にナルシシズムが古代ユダヤ人(少なくとも一部の)にもたらした絶対的快感。ナルシシズムの快感は絶大である。ナルシシズムにおいては自己が絶対的な創造神となる。自己が絶対的な存在となる。ナルシシズム状態になることは、惨めな奴隷の状態だった古代のユダヤ人にファラオの、あるいはファラオをも凌ぐ絶対的な存在の、状態をもたらす(その意味で、エジプトにおいても、極めて惨めな存在だったユダヤ人に最も広くこの信仰が浸透したのかも知れない。さらに、ユダヤ人においてはアモンその他エジプトの伝統の拘束力も弱い)。その絶対的矛盾(その本質は後に問題になる)とそれゆえの根源的人格分裂性ゆえに、ナルシシズムがもたらす不安と抵抗は無数の残忍な死をもたらすほどに強い。しかし同時に、夢見るようなその快感は快感の極致と言い得るほどに強い。それらが、それらのモーセと古代ユダヤ人たちとの相互関係が、ユダヤ人たちを率いてのモーセのエジプト脱出という現象をもたらしたのだろう。もちろん、モーセただひとりでユダヤ人たちを率いたわけではないだろう。彼の周辺にはその信仰を同じくする祭司的な人間も多数いただろう(あるいはこれが『旧約聖書』にいう「レビ人」かも知れない)――。もちろん、『旧約聖書』に伝承され書かれる古代ユダヤ人たちのエジプト脱出の事実にしても、モーセの存在にしても、何もかもが曖昧であり、疑おうと思えばいくらでも疑えるわけであるが、しかし、少なくともユダヤ教がエジプトと何らかのつながりがあり、そこから引き出されてきたという事実がなければ、ヨセフ(『旧』「創世記41:45」によれば、この男の妻はオン(ヘリオポリス)の祭司の娘だそうである)がエジプトへいき、その子孫がその地でふえ、奴隷状態となり、そしてモーセによってそこから引き出されたという、いうなれば迂路としての、伝承がわざわざ作り出され『聖書』に記される必然性はないだろう。ユダヤ教が部族長時代から一貫してシナイ半島あたりで、あるいはカナン(パレスチナ)あたりで、生まれそして発展したとしても一向に差しつかえなかった筈なのである。その後(エジプト脱出後)ユダヤ人たちは(『旧約聖書』によれば40年・「申命記8:2」)荒野を彷徨した後カナン(パレスチナ)へと侵入しこれを席捲していくわけであるが、このカナンへの侵入意思(自分たちの国をつくるという意思)はあるいはエジプト脱出後に生じたものかも知れない。荒野においてナルシシズムが熟成したわけである。モーセに関しては、エジプト脱出後ユダヤ人によって殺されたという説もある。ゼリンという男が言い出した(しかし彼は後に自らこれを撤回した)。モーセが殺されたかどうかはもちろん基本的にはよく分からない。しかし、人類史においてイクナートンの信仰やユダヤ教・キリスト教等のナルシシズムが各時代・全地球上各地で引き起こしもたらした矯激な抵抗・相克・不調和、絶対的に相容れない矯激な相互闘争(コンフリクト)を考えた場合、むしろ殺されることの方が事態のなりゆきとしては自然と言える。モーセに関しては『旧約聖書』に奇妙な伝承がある。エジプト脱出後「カデシュに多くの日――とどまった」(「申命記1:46」)後、彼らが「ホル山からの旅を続け、紅海の道を通ってエドムの地を迂回していた時」(「民数記21:4」)、毒蛇に咬まれて死ぬ者が多く出た。その時モーセは、エホバの声に従って銅の蛇を作り、これを旗竿の上にとりつけた。すると、毒蛇に咬まれた者も、この銅の蛇を見ただけで死ぬことはなくなった(『旧』「民数記21:4―9」)。この銅の蛇に関しては、さらに『旧約聖書』のもう少し後において再びとりあげられている。すなわち、古代ユダヤ人たちがカナン(パレスチナ)で王国を建て、そしてその後北王国(イスラエル王国)と南王国(ユダ王国)とに分裂した後、ユダ王国のレハベアムから数えて13代目の王アハズの子ヒゼキヤが「その父祖ダビデが行った通りに、エホバの目に正しいことを行い続け」異教の聖柱やら聖木やらを切り倒し、そして「モーセの造った銅の蛇を粉々に打ち砕いた」(以上『旧』「列王記下18:3―4」)。このヒゼキヤの行為は偶像の忌避、崇拝対象視覚化の忌避衝動として現れる極めて自然なものである。問題は、なぜモーセがこのような「偶像」を作ったのか、ということなのである。しかもこれは、これを見さえすれば毒蛇に咬まれても死なないという魔法の呪物なのである。「あなた方は吉凶の兆しを求めてはならない。また魔術を行ってはならない」(『旧』「レビ記19:26」)「女呪術者を生かしておいてはならない」(『旧』「出エジプト記22:18」)…。三代四代までもの呪いと千代までもの祝福をもって果たし維持しようとした偶像の絶滅、すなわち十戒のその(二)、を残したモーセがこのようなものを作る筈がないのである。つまり、これを作ったのはモーセではなかったのかもしれない。あるいは、別の、第2のモーセだったのかも知れない。すなわち、「民数記」の「16」にあるような闘争関係の中で死に(あるいは殺された)モーセに代わって宗教をも含めた全ての指導者となった第2の人間もまた同じく「モーセ((神の)子)」と呼ばれたのかも知れない―。「シナイ契約」という言葉がある。すなわち、モーセに率いられた古代ユダヤ人たちが「シナイ」という名の山(この山の名は「ホレブ」ともいう)において唯一絶対の神「エホバ(ヤハウェ)」との間に神の言葉を受け容れた(これがすなわち「契約」である。ユダヤ教やキリスト教等における神との契約は双方が義務を負うのではなく、人間が一方的に絶対の神の言葉を受け容れる。そうすることにより神は多くの祝福を与えてくれる。受け容れない者は呪われる)。このシナイ契約は、ユダヤ人によるエホバ(ヤハウェ)の、唯一絶対の神の、受容という印象を与える。しかしながら、古代ユダヤ人が、エジプトを脱出した後シナイ(あるいはホレブ)において初めてナルシシズム過程に遭遇したなどということはあり得ない。エジプトを脱出したモーセがシナイにおいて初めてユダヤ人たちにその過程に対する支配をもたらした、あるいは、エジプト脱出後そこでナルシシズムがユダヤ人たちに受け容れられるようなあり方に変容した、ということはあり得るわけであるが、そこで初めて遭遇したのでは、唯一絶対の神に導かれてのエジプトからのユダヤ人脱出の動因が成り立たない――。
古代ユダヤ人たちに一神教ナルシシズムが導入されていく時期、その客観的様相は大まかにそういうことだろう。
しかし、それはあくまでも客観的様相である。
問題は、見えざるその本質である。
ナルシシズム状態になっていくとは人がどうなることなのか。
けして目には見えないところで彼らに何が起こったのか。
『聖書』における唯一絶対の神の名を「エホバ(ヤハウェ)」という。
しかし、『聖書』にはもうひとつ神の名がある。
すなわち、「エロヒム」がそれである。
『聖書』に「エホバ」と「エロヒム」という二つの神の名が現れていることは18世紀初頭にドイツ・ヒルデスハイムの牧師ベルンハルト・ウイッターが着目し、それを規準として本文を読み解く聖書学に先鞭をつけた。以来、その方法から様々な聖書研究とその成果が生まれている。
他にも「アドーナーイー」という呼び方もあるが、これは、「わが「主」よ」のように、神の名を直接に呼ぶことをはばかった間接的呼称としての称号である。
では、「エホバ(ヤハウェ)」とは何であろうか。「エロヒム」とは何であろうか。「エホバ(ヤハウェ)」・「エロヒム」とはどういう意味なのであろうか。これらはどのような思考のあり方・感性のあり方をあらわす言葉なのであろうか(「エホバ(ヤハウェ)」・「エロヒム」という言葉、その音(おと)、が各々どのような脳ニューロン反応をひき起こしているか、というあり方でお考えいただきたい:意味とは肉体のあり方、生命体のあり方であり、言葉の意味とは、それを説く言葉、それに関連し記憶されている言葉すべての記憶ではなく、その言葉としてあらわれている音の作用たる肉体の、生命体の、あり方なのである)。そして、唯一絶対の神への信仰でありながら、なぜ二つの神の名が(二つの神が)現れているのであろうか。相対性の生じない絶対の一の神への信仰でありながら、なぜ、二つの神への信仰のような状態が現れているのであろうか……。
まず「エホバ(ヤハウェ)」。
これは『旧約聖書』原典に用いられているヘブライ語の原語では「יהוה」(ヘブライ語は向かって右から左へ読む)。これは日本語の仮名で記せば「エホワー」あるいは「ヤハウェー(Yahveh・Yahweh)」のような音(おん)といわれる。ラテン系アルファベットで記せば「YHWH」、あるいは「JHVH」、とでもなるであろうか(キリスト教関係の辞典では「י」(ヨッド、あるいは、ヨード)の「音写記号」は「y」に、「ו」(ワーウ、あるいは、ヴァヴ)の「音写記号」は「w」に、ヘブライ語の辞書では「י」の「発音記号」は「j」に、「ו」の発音記号は「w,v」になっている:これはローマ字の特質と歴史に由来する)。カソリック教会では「יהוה」は日本語では「主」と訳すことになっており、日本聖書刊行会や日本聖書協会による日本語版聖書ではそうなっている。
日本語の「エホバ」や英語やドイツ語等の「Jehovah」はヘブライ語の表記と昔のユダヤ人の習慣による誤謬に由来すると言われる。ヘブライ語は(ヘブライ語に限らず、古代メソポタミアあたりで生まれた文字(音素文字・アルファベット)はフェニキア系のものもシリア系のものもすべてそうであるが)子音のみを表記したことから、音の伝承は不正確であり、それをより正確に伝承するために、後に、既に書かれていた様々な文書に母音を表す符号を書き加えることが行われた(西暦1千年紀の後半からである)。他方、その昔ユダヤ人たちの間には神の名を直接口にすること、声に出すことをはばかる習慣があり、ユダヤ人たちは目では「יהוה(HWHY)」を見ながら口では「アドーナーイー(主)」や「エロヒーム」と唱えた。その唱えに基づいて「יהוה(HWHY)」に「アドーナーイー」や「エロヒーム」を表す母音符号が記され、そうしたことから「יהוה(HWHY)」は「Jehovah」と読まれ、それが伝承され日本にも広まった、と言われる。では、元来の神の名、日本語で「エホバ」と伝えられている語音のその発生時の原音はどのようなものだったのであろうか。これに関しては、『旧約聖書』「出エジプト記3:14」にある神名の由来らしき伝承を根拠に動詞「ハーヤー:成る」に由来する(その使役態)とし(ただし、ヘブライ語の意味と語音を根拠として、「出エジプト記3:14」にある伝承を根拠に「ヤハウェ」のような音を導き出すことには否定的な見解がむしろ有力)、また初期キリスト教徒思索家・著述家(たとえばオリゲネス(185頃―254頃)やクレメンス(150頃―215頃)その他)によるギリシャ語文献にギリシャ語で発音して「イアエ」・「イアベ」・「イアウエー」・「イアバイ」、さらには「イアオー」「イアホ」(この二者はその昔エジプトに伝承されていたという)のような発音をすると思われる文字が記されること、さらには『詩編』にある「ヤハ」、などを根拠に、「ヤハウェ」のような音(おん)を主張しあるいは支持するヘブライ語学者が多くある。しかし、「ヤフワ」や「エフーア」といった音を主張する者もいる。しかし、「ローマ字」や「アルファベット」と呼ばれる文字はその機能の本質として音(おん)を正確に表現せず、伝承せず、それにより伝承される音(おん)は極めて曖昧であり、その昔のヘブライ語は子音のみしか書かず、神の名を聴覚化することを忌みこれを記憶の深淵へと沈めてしまおうとするような衝動は相当に古代から執拗に働きその効果を果たし、結論を言えば、その原音に関し、正確なことはよく分からない。ある程度正確に言えることは、それは、西暦20世紀頃のラテン系アルファベットで表記すれば「YHWH」、あるいは「JHVH」、と書かれるような音(おん)だったろうということくらいである。正確な語音が分からないにも拘わらずその語源を考えることは無謀であろうか。
その試みがここでなされる。
この「יהוה」は、ギリシャ語にある「神(元来は「光」や「明るさ」を意味する)」を意味する「θεος(ゼオス、あるいは、ツェオス)」と、ヘブライ語にある、『旧約聖書』に山名としてあらわれている「הרב(ホレブ)」とヘブライ語で「主人」や「所有者」を意味する「בעל(バアル)」の合成語であろう。いうなれば「Θεοσלעב-ברה(ゼオホレブバアル)」。ラテン系アルファベットで記せば「Theohorebbaal」。語頭のΘ音(Th音)は子音脱落的に退行化しY音化し、O音は消音化し、ר音(R音)も退化し、退化したそのR音やB音の連音の影響によりV音やW音のような音になり、L音が消音化すれば「イェホヴァー」や音が退行化した「イェホウヮー」のような音になる。さらに、退行化しつつ後音の影響により前音がA音化すれば「ヤーワー」のような音に、さらに音が退化すれば「ヤーハー」や単なる「ヤー」のような音にもなる。「ホレブ・バアル」は、「バアル・ホレブ」と言った場合、「主(所有者)たるホレブ」、「ホレブ」という名の神、という意味になるが、「ホレブ・バアル」はそういう意味ではなく、「ホレブの主(所有者)」という意味であり、「ホレブ」は神の名としては表現されていない(神に名など無かったモーセの信仰と、神の名を欲する古代ユダヤ人たちとの妥協の産物としてこの神名が生まれた)。モーセらがエジプトを脱出しそしてカナン(パレスチナ)へと入っていくその当時、そのあたりではバール信仰は極めて一般的だった。元来は神の名は「ホレブバアル」だけだったであろうが、この「ホレブバアル」の語頭に神格性を表現する「ゼオ」が加わった。空間的移動もあり、世代が進み「ホレブ」への信仰が希薄になっていくにつれその名だけでは神格性に弱さが感じられるようになったのである。つまり、「יהוה(エホバ(ヤハウェ))」は「ゼオス」と山の神への信仰表現の合成語ということである。『聖書』には、「エホバの山」(『旧』「民数記10:33」)という表現や、イスラエル王国と戦争して負けたシリアの僕たちが「彼ら(古代ユダヤ人)の神は山の神です」(『旧』「列王記上20:23」)と言い、あるいは「神みずから住むことを願った山――エホバご自身がそこに永久に住まわれる」「エホバご自身がシナイ(山の名:別名ホレブ)から聖なる場所に入ってこられた」(『旧』「詩編68:16―17」)「神は自らテマンから来られた。聖なる方がパラン山から」(『旧』「ハバクク書3:3」)などという表現があるように、「エホバ」は非常に山に関係が深い。さらには、同一の山を表す「ホレブ」「シナイ」という二つの名に関し、「ホレブ」はエロヒム系であり「シナイ」はエホバ系だと言われるのもそんなところに理由があるのだろう(『聖書』では、「ホレブ」という言葉は「エロヒム」という言葉とともに、「シナイ」という言葉は「エホバ」という言葉とともに、用いられることが多いのである。つまり、「エホバ」という言葉には「ホレブ」という言葉が含まれており、ホレブがホレブに現れたりすることは表現として不自然になってくるわけである。その結果、表現において、エホバ・シナイ、エロヒム・ホレブ、という関係が形成されていく。ただしこれは厳密に維持されているわけではない(たとえば「申命記1:6、4:15)。厳密性がなくなることは「エホバ」という言葉の神名としての成熟性によるものだろう)。つまり、「エホバ」は「Θεοσלעב-ברה(ゼオホレブバアル)」であり、「ホレブバアル」は山の神であり、いうなれば、「エホバ(ゼオホレブバアル)」は「神聖なるホレブの神」、つまり、和語で言えば要するに「山の神」あるいは「神の山」ということである。つまり、これは世界のどこにでもある原始的な山岳信仰の現れである。山という圧倒的な物的存在に対し、それがあたかも巨大な人であるが如く、畏敬の念を捧げ、そして祈ったのである。ここで起こっている事態には、神は自己消滅したとき自己を完成するという特性があり、信仰の立場からは、神の名が「エホバ」であろうと「ヤハウェ」であろうと、あるいは「ゴッド」や「アラー」や「かみ(神)」や「シン(神)」であろうと、すなわちその語源がどうであろうと、全く問題にすらならないという事態も起こりそうである。しかし、その信仰において起こり伝えられる考えのあり方や感性のあり方の問題として、エホバ(ヤハウェでもよいが)は山の神であり、原始的な山岳信仰のあらわれであり、その継承とナルシスティックな変容である。では、この「エホバ」という神名がいつ頃できたのかということになると、これは明確には分からない。モーセが(あるいは第一の、本物の、モーセが)当初から「エホバ」を崇拝対象にしていたということはあり得ない。山などという「偶像」をモーセが崇拝するはずが無い。多分当初は神に名など無かったのではないだろうか。当初は(少なくとも通常言う意味での客観的な)崇拝対象などは何も無かったのではないだろうか(この点はすぐ後に問題になる)。それがいつの日か、崇拝対象を要求する退行的な古代ユダヤ人たちにより、その太古以来の土着的習俗に根ざした「ホレブバアル(そしてエホバ)」が選ばれたのだろう(第二のモーセがその名を口にしたのかも知れない)。その場合、当初は神はただ単に山そのもの、すなわち「ホレブ」であり、山が、あたかも山が巨大な人であるかのごとく、そのまま神として祈り呼びかける対象だったのだろう。その「ホレブバアル」の語頭に、いつの日か、神聖さ荘厳さを加え表すために「ゼオ」が加えられた。それがいつ頃のことなのかに関しては、あるいは、クレタ島から出土した神聖文字がエジプトのそれに酷似し、その或る型(A型)の線文字から派生したと思われる文字がキプロス島から出土し、ギリシャ語として解読された或る型(B型)の文字に類似した文字がキプロスやシリアのウガリトで発見されるという事実に象徴される紀元前2千年紀(前2000年から1000年)中ごろの東地中海域におけるギリシャ・小アジア(トルコ)・シリア・パレスチナ・エジプト等の相互交流の所産かも知れず、あるいはそれよりも後のことなのかも知れない。
『聖書』の神に関しては、その名の由来らしき伝承が『聖書』自体に記されている。「出エジプト記3:13―14」がそれである。以下その部分を抜き書きしよう。これはモーセが古代ユダヤの民たちを率いてエジプトを脱出する前、初めて神に呼びかけられその使命を伝えられた際のことである。場所はホレブ(山)。
「モーセは神に言った、『わたしが今イスラエルの子らのもとに行って、“あなた方の父祖の神がわたしをあなた方のもとに遣わした”と言うとしても、“その方の名は何というのか”と彼らが言うとすれば、わたしはこれに何と言えばよいでしょうか』。すると神はモーセに言われた、『私は有りて有る者』。そしてさらに言われた、『あなたはイスラエルの子らにこう言うように。“私は有るという方がわたしをあなた方のもとにつかわされた”』。」(『旧』「出エジプト記3:13―14」)。日本で一般に流布している『聖書』ではこの「私は有りて有る者」「私は有る」と訳されている部分は、他の日本語版『聖書』では、「私はなるところのものとなる」「私はなる」と訳しているものもある。この後半、すなわち「3:14」の部分の英語訳は次のようになっている(17世紀の表現である)。
「And God saide vnto Moses,I am that I am :And he said,Thus shalt thou say vnto the children of Israel,I AM hath sent me vnto you.(そして神はモーセに言った、『I am that I am』。そして彼(神)は言った、『このようにあなたはイスラエルの子供たちに言いなさい“I AM が私をあなたたちのもとへつかわしたのだ”と』:「v」は「u」に同じ。「thou」は、ドイツ語に由来する、英語の古い二人称。後の「you」)」(『Exodus 3:14』)。
さらに、日本語版聖書で一般に「私は有りて有るもの」あるいは「私はなるところのものとなる」と訳され、英語版聖書で「I am that I am」と訳されている部分の『聖書』原典におけるヘブライ語原語は、「אהיה אשר אהיה」。これは日本語の片仮名で音を表記すれば「エフエ アシェル エフエ」、英語のアルファベットで表記すれば「Ehyh asr Ehyh」とでもなるであろうか。「אהיה・エフエ(Ehyh)」は和語で言えば「…である」という意味の動詞の一人称単数未完了態。すなわち「私は…である」のような意。つまり、名を問われた神は、「私は 私は…である である」と答え、さらに、「“私は…である”があなたたちのもとへ私をつかわした、と言いなさい」と言ったのである。そんな神の声をモーセは聞いた。そんなことがモーセに起こった。つまり、神は“私は…である”なのである。“私は…である”が神であり、神は“私は”であり、私 …は神であり、“私”はこの全宇宙・全存在物を創造し、“私”は唯一絶対の存在として全宇宙に絶対的に君臨し、私がこの全宇宙・全世界・全存在の創造者・絶対者であり、私が、この私が全宇宙・全存在を創造し、私は唯一絶対の存在であり、私は………………………つまり、ナルシシズムなのである。神の名の由来を表すが如き『聖書』のこの「出エジプト記3:13―14」の伝承は内面吐露的にナルシシズム形成が表現されているものであり、「エホバ」・「エロヒム」という神の名の由来を表し伝承しているわけではない(「エホバ」・「エロヒム」という神名はナルシシズムの結果現れたものではあっても、ナルシシズムそれを表現しているわけではない。もし、ナルシシズムそれを表現する神名を創るとすれば、それは「私」である。唯一絶対の「私」である)。前にのべたところの、(本物の)モーセには「通常言う意味での客観的な崇拝対象はなかった」とはそういう意味である。そこには「私(わたくし)」という言葉もなかっただろう(「私」への客観性もなくなっていただろう)。
そして、もうひとつの神の名「エロヒム」。この言葉のヘブライ語原語は「אלהים」。日本語の仮名で音を表記すれば「エロヒーム」(神格的存在感が表現される場合は冠詞がついて「ハー・エロヒーム」という)。英語のアルファベットで表記すれば「Elhym」であろうか。この言葉はギリシャ語にある「ηλιος(ヘリオス、あるいは、エリオス)」と「υμνος(ヒュムノス、あるいは、イムノス)」の合成語であろう。つまり、日本語の仮名で表記すれば「ヘリオヒム」あるいは「イリオヒム」。英語のアルファベットで表記すれば「Heliohymn」。「ηλιος」は結局「太陽」であり、「υμνος」は「歌(うた)」あるいは「賛歌」であり(陶酔した神への讃歌はときにある瞬間神からの声(神託)となり)、「ヘリオヒム」は、いうなれば、「太陽賛歌」「太陽の歌」「光の歌」である。なぜ太陽か、に関してはイクナートンのアトン信仰においてアトンは太陽神でもあったことが思い起こされる。唯一絶対的存在でありあらゆる光の源泉である太陽がナルシシズムを満たす道具的対象となる(さらに言えば、言葉を(音を)光としようとする)。なぜ歌か、に関しては、歌は言葉だからである。「うた」は「我」をうち放す行為であり、それにより放たれた言葉である。崇拝対象の視覚化が否定され忌避されたとき、そこにはただ音が、言葉が、神聖な崇拝対象として作用する。そこにはただ神を讃える言葉だけが、神としての言葉が、ある。そこではその「言葉」がすなわち崇拝対象となっている。神となっている。崇拝対象の視覚化が強迫的に忌避されつつ彼らは強迫的に、本能的に崇拝対象を見ようとする。そしてやがては言葉それが全宇宙・全存在物の創造者、唯一絶対の存在となる。言葉が、抽象概念が、対自的に存在化していくわけである。そうした神への歌(hymn・賛歌)が具体的にどのようなものであるかに関しては、『旧約聖書』の「詩編」に数多くその例が掲載されている(古代インドの『ヴェーダ(知ったこと)』も歌である)。すなわち、この「エロヒム」という神名は、対自的に存在化する言葉が唯一絶対の神となるナルシシズムの本質を表現する。ナルシシズムという運動の一方の(限界まで退行的な:退行的、の意味は後に触れる)極に「エホバ」があり、一方の(限界まで治癒的な:治癒的、の意味は後に触れる)極に「エロヒム」がある。
『新聖書大辞典』(キリスト新聞社)はエロヒム資料(『聖書』内の「エロヒム」が用いられている文書)の特性に関し次のように言う。「(エロヒム資料の)作者はイスラエルの神をまずこの名であらわし、『ヤハウェ』とはこの神がモーセに自身を啓示した名としている(つまり、「ヤハウェ」は「エロヒム」が人間に現れる姿なのである―著者)。顕著な特徴は、(1)神観がJ(エホバ資料)のように擬人的でなく、神は夢や天使を通して人びとに自らをあらわすものとして描かれる。(2)物語としての発展的な流れをもたず、力づよさにおいてもJ(エホバ資料)に劣るが、各個の事件描写にはすぐれた作品がある(たとえばイサクの燔祭)と同時に、祭儀的な関心が深い。予言者的でありつつ祭司的な一面をもつと言われるゆえんである。(3)倫理観は、時代的に明らかにJ(エホバ資料)より進んだ後代のものであることを示している」。ヤハウェ(エホバ)資料(『聖書』内の「ヤハウェ(エホバ)」が用いられている文書)に関してはこう言う。「(1)神観はきわめて擬人的であり、人間の思考・行為を表す用語法をもって神を描写しようとする」……。エホバは人のように現れる(見える)。エロヒムは見えない(しかしその意思は伝える)。エロヒムは祭儀的な関心が深く、予言者的でありつつ祭司的。すなわちエロヒムはより聖化しておりその信仰はより深化している。エロヒムにはエホバよりも時代的宗教的に進んだ印象がある……。『聖書』における「אלהים(エロヒム)」という言葉の用いられ方には言葉の過程(言語中枢の作用)それの印象が極めて強い。たとえば、「ヨシュア記22:34」において、ルベンの子らとガドの子らが祭壇を作り、その祭壇に名をつけた。それは、名をつけることが彼らの間でエホバがエロヒムであることの証しになるからだという。言うまでもなく、名は言葉である。言葉の過程の発動が、言語表現することが、言語中枢が作用することが、エホバをエロヒムにする。あるいは「サムエル記下2:27」において、ダビデ軍とイシ・ボセテやアブネルの軍がギベオンで戦った際(ダビデ軍が勝つのであるが)アブネルが逃げ去り、アサエルという足の速い男がそのあとを追った。アサエルは追いついたとき殺された。そして、ヨアブとアビシャイもアブネルの後を追った。日が暮れるころ、彼らはアブネルに追いつき彼の後ろの丘の頂に立った。そのとき、アブネルが追いかけて来たヨアブに呼びかけて言った、「剣は(人を)果てしなく食らうのか、しまいには悲惨なことになることを知らないのか、いつになったらその民に兄弟たち(ユダヤ人たちはどの部族もみんな兄弟だ、ということである)を追うのをやめて引き返すように言うつもりか」。するとヨアブが答える、「エロヒムは生きている。もしもお前が話さなければ民は朝になってはじめて兄弟を追うのをやめて引き上げたことだろう」。そしてこのアブネルの言葉により、彼らは彼を追うことをやめ、戦いもやめ、ひきあげていく。アブネルの言葉が、言語中枢の作用が、現実的実効性を果たしたとき、彼(ヨアブ)はそれを「エロヒムは生きている」と表現している。ヨアブの言葉にある「エロヒム」を「言葉」と言い換えても不自然さはない。あるいは「列王記上18:21」。北王国(イスラエル王国)アハブ王の時代。アハブは異教の神バアルに仕えた。そこで予言者エリヤはバアルの(400人といわれる)予言者とカルメル山において、バアルとエホバとどちらが真の神であるかを争った。薪の上に犠牲の牛を置き、真の神こそが火によってこれらを焼き尽くすというのである。この戦いを始める際、予言者エリヤは400人のバアルの予言者を前にし民衆に向かって言った。「あなた方はいつまで二つの異なった考えの間をさまよっているのか。もしエホバがエロヒムならこれに従え。しかしもしバアルがそうなら(つまり、バアルがエロヒムなら)それに従え」。そして続く「18:24」において言う。「火によって答えるエロヒムこそエロヒムだ」。つまり、これは、エホバの言葉(エロヒム)と、バアルの言葉(エロヒム)と、どちらが真実が、どちらが真理(エロヒム)か、ということなのである(真理とは、全的に容認される言葉である)。そして火によって答えた神の言葉こそが真理であり、その真理の言葉こそまさに真理だ(火によって答えたエロヒムこそエロヒムだ)ということなのである。あるいは「サムエル記下7:28」「列王記下19:15」「歴代志上17:26」などには、「エホバこそエロヒム」「エホバがエロヒム」という表現がある。「列王記上18:39」のものは、先述のバアルとの戦いにおいてエリヤが勝った際民衆が「エホバこそエロヒム!エホバこそエロヒム!」と叫んだものである。つまり、「エホバはエロヒム」とは言っても、「エロヒムはエホバ」とは言わない。これは、「(神格化された)山(エホバ)は(真理として神格化された)言葉(エロヒム)→エホバの言葉は真理」は成り立っても「(真理として神格化された)言葉(エロヒム)は(神格化された)山(エホバ)」は成り立たないということなのである。あるいは、「エロヒムの箱」「エロヒムの契約の箱」という表現が目立つ。たとえば「サムエル記上4:17、5:1」「サムエル記下6以下、15:24―25」「歴代志上13以下、15以下」。ただし「エホバの契約の箱」という表現ももちろんある。たとえば「列王記上3:15」「歴代志上15:26、22:19」(ただしこの『歴代志』のものは叙述全体にエロヒムが優越的にあらわれている。「エホバ」がまるで人間との契約のための道具のような状態なのである)。この箱の中にはモーセがホレブで神から受けた二枚の石板が納められている。石板には契約が、すなわち神の言葉が、彫り記されている。つまり、この箱の中には言葉が入っている。あるいは「サムエル記下12:16」では、子供が病気になったときダビデは断食してエロヒムを求める。これは、どうすれば良いかを知るために神の声を、言葉を求めたのである。「サムエル記下16:23」では、アヒトフェルが助言するとき(の人々の態度は)まるで人がエロヒムの言葉を伺うときのようだったと言う。「サムエル記上14:36―37」では、「エロヒムに近づこう」と言って神に伺いをたてる(つまり、神の言葉を求める)。「歴代志上16:42」には「エロヒムの楽器」という表現もある。この時代には、「歴代志上25:1―6」あたりに叙述されるように、琴やシンバルのような楽器を奏でつつ陶酔するように、歌うように予言し、神への賛歌(hymn)と予言との間にほとんど差異はなかった。歌としての言葉に神の言葉を聞き、神の言葉は予言となる。「ヨシュア記24:19以下」では、古代ユダヤ人たちはシケムにおいてエロヒムの前に立って神との契約を更新した。言うまでもなく契約は言葉であり、複数の者に同じ言葉の記憶が作用することである。あるいは「サムエル記上9:7、8、10」「列王記上12:22。13:4以下。17:18」「列王記下1:9、11、13。4:7、21、22、25、27等」においては、予言者が「エロヒムの人」と呼ばれている。予言者は言葉を告げる。言葉を与えてくれる。ちなみに、将来のことや神の意思を述べる者(一般に言う予言者)は、『旧約聖書』では当初「ローエー」あるいは「ホゼー」と言った。これらは「見る者」を意味する。しかし、やがて、時代が下るにつれ、それは「ナービ」と言われるようになっていく。これは「語る者」を意味する。永い歳月をかけ唯一絶対神信仰が成熟していくにつれ(ナルシシズムが成熟していくにつれ)、予言が見ることから言葉を得ることへと変質していくのである。「サムエル記」が記されたころにはもはや変質していたようである(サムエル記上9:9参照)。あるいは、「日の下には新しいものは何もない」と言い「伝導者は喜ばしい言葉を見いだし、真実の正確な言葉を書き記そうと努めた」と記す、いうなれば「知的」な(つまり、言葉による抽象的思考過程の支配的影響性の強い)「伝道書」において、「エホバ」はただの一言もあらわれず、ただ「エロヒム」だけが用いられている………。ここで『聖書』の冒頭、すなわち「創世記」にも多少触れておこう。
「初めにエロヒムは天と地を創造せり」(『旧』「創世記1:1」)―『聖書』はそんな言葉で始まる。この部分の「エロヒム」は日本語版聖書では一般に「神」と訳される。それに冠詞がつき存在化した「ハー・エロヒム」の初見は「創世記5:22」であり、「エホバ」の初見は「創世記2:4」(人間の創造(すなわちアダムとイブの話)の部分)である。厳密に言えば、「創世記2:4」(人間の創造)のそれは「エホバ」と「エロヒム」を併記した「エホバ・エロヒム」であり、「エホバ」単独の初見は「創世記4:1」である。また、その表現頻度は極めて少ないのであるが、「エホバ」と冠詞の付された「ハー・エロヒム」を併記した「エホバ・ハー・エロヒム」の初見は「歴代誌(一)22:1」(神殿を「エホバ・ハー・エロヒムの家」と表現したダビデの言葉)である。
神は初めに天と地を創造した。地には象(かたち)がなかった。そこは虚無であり、闇が淵、すなわち水の深み、の表(おもて)にあった。そして神の活動力とでも言うべきものが水の表をゆきめぐっていた(以上『旧』「創世記1:1―2」)。
このあたりの描写は、虚無の原初の深淵ヌンからアトゥムが「独りでなった」古代エジプト神話に似ている。
そして神が言った。「光あれ」。すると光があった(『旧』「創世記1:3」)。言葉が光となった。言葉という音の過程・聴覚刺激過程が光の過程・視覚刺激過程となった。ここから全てが始まった。しかし、この光は光ではない。矛盾した言い方であるが、この光は光ではない。「それゆえ、用心していなさい。もしかすると、あなたのうちにある光は闇であるかもしれません」(『新約聖書』「ルカ書11:35」)……。光の源たる太陽、そして月や星は4日目に造られる。このときにはまだ太陽はない。光はない。しかし「光」はある。その後神は天と地を造る。天と地を造る、というよりも、「天」や「地」という言葉を造る。神が「天」と呼び「地」と呼ぶ―それが天となり地となる―それがすなわち天や地の創造である。それがすなわち「創造」である。それが何語で表現されようと、それがすなわち『聖書』における「創造」である。1日目に「光」が、2日目に「天」が、3日目に「地」が、「海」が、そして同じ3日目には「植物」が造られ、4日目には「太陽」や「月」や「星」が造られ、5日目には「魚」や「鳥」が、そして6日目にはあらゆる地の動物が造られ、そして最後に「人」が造られた(この創造の過程、とりわけ3日目からの植物→魚→鳥→獣→人間という生命体の創造の過程、は素朴な進化論である。「創世記」は素朴な進化論に基づいて書かれている)。この創造の過程において、神はあらゆる植物や動物を「その種類にしたがって」創造している(『旧』「創世記1:11、21、24、25」)。この、あらゆる生物は「その種類にしたがって」創造された、という点を19世紀に相対化しようとしたのがチャールズ・ダーウィンの『種の起源』(原題はさらに長い)及び「進化論」だった。しかし、ダーウィンはただ或る種を他の種にしただけ(あるいは、そうしようとしただけ。あるいは、(彼において)「種」が無意味化していただけ)、だった。結局のところただそれだけのことだった。彼は「種の起源」を解明することはなかった(ダーウィンの仕事における本質的問題はあくまでも『種の起源』であり、けしてそれは生物における『進化』の有無ではない)。ダーウィンによる種の無意味化(たとえば人と猿の異なりを無意味化するような)は多くの(とりわけキリスト教文化圏たるヨーロッパ系の)人々に(本質的にはそこで生じる言語の無意味化、たとえば「人(ひと)」と「猿(さる)」という言葉の無意味化、そして、猿は言葉を話さない、ゆえに)強い抵抗を引き起こしはした。あたかもそれが「その種にしたがって」なされた『聖書』の創造の無神論的否定であり、神への冒涜であるかのような嫌悪感を感じる者もいた。しかし、人工栽培(人の意思と手による栽培)による変異から、主体(人と自然(神))を同一化させつつ、自然のもとでの(自然(神)の意思と手による栽培による)変異へ、そして生存闘争へ、と叙述が移行していく彼の書物において、「進化」(あるいは、「種の起源」原典の表現をかりれば「Preservation of Favoured Races」(神に? その生物に?)好まれた経過(種?・raceには競争や経過の他、種という意味もある)の保存(保護))は神の意思であり、「進化論」は神の意思として、(後に述べる)エロヒムの治癒として、そして「神に選ばれた者」を賛美するナルシスティックな「真理」として、初めから予定されたことだった。ダーウィンはナルシシズムの闘争的分裂性を刺激し、ナルシシズム社会に(後に述べるところの)治癒的なナルシシズム(科学)と退行的なナルシシズム(宗教)相互の虚無的な分裂的闘争関係を触発し、生じさせ、拡大深化させはした。しかし、全く同じ「キリスト教徒」と呼ばれ、同じように生活し、同じ教会へ通っていたとしても、原始的な山の神のレベルの信仰に生きている者もいれば、全く抽象化した、悟性でなければ見えない“かのもの”のレベルの信仰に生きている者もいる。そしてどちらも唯一絶対である。ダーウィンはけして無神論者ではなかった。彼はけして神から自由な者ではなかった。むしろ、彼は忠実な神の僕であり、エロヒムの僕だった。彼は系統発生を、生命体としての過去の記憶の全てを、エロヒムに捧げ、神の意思として成就させた。科学は神の(エロヒムの、唯一絶対なるものとして対自的に存在化する「言葉」の)初めから予定された自己成就なのである。科学は神(エロヒム)の自己成就であり、言葉信仰たる宗教なのである。言葉がすべてと、すなわち絶対の神と、なる宗教なのである。無いが在るになること―それが宗教である。科学とは、無いが在る言葉が幼児における親の記憶のように意思とは無関係な権威として作用する宗教なのである。知の人たる人間は知覚したあらゆる現象の動因や因果を言い分け(言語化し)、記憶していく。知は人間の本能である。そうした人間の本能を巧みに利用するかのように、エロヒムは、言葉は、権威としての自己を確立、強化、増大していく。果てる際(きわ)なく、エロヒムは増大していく。種とは何か。種とはすなわち抽象概念であり、言葉なのである。たとえば、「三角」という言葉が、それが具体的にどのような三角形であれ、あらゆる三角形を一般化した名称であり、「兎」という言葉が、それが具体的にどのような兎であれ、あらゆる兎を一般化した名称であるように、「種」は個別的具体性を離れた概念である。言葉が成るとき種は成る。言葉が異なるとき種は異なる。異(こと)なる→ことなる→言成(ことな)る(「異(こと)なる」という和語はそういうことなのである)。『聖書』における、「創世記」における、創造、天地創造、あらゆる生命体の創造、そして人間の創造、とはすなわちそうした過程、すなわち、言葉(音)が光となり、聴覚刺激過程が視覚刺激過程となり、聴覚的体験(言葉の体験)が視覚的体験となり、言葉が創造されていく過程、言葉が対自的に存在化し見えていく過程、なのである。まさに無いが在るになる創造である。そして「神は人をご自身の象(かたち)に創造していき、神の象にこれを創造された」(『旧』「創世記1:27」)。そして、「人がそれを、すなわちそれぞれの生きた魂をどのように呼んでも、それがすべてその名となった」(『旧』「創世記2:19」)。神の、エロヒムの、象(かたち)の人があらゆる名を与えていく。あらゆる言葉を創造していく……。
「創世記」から「エロヒム」にもどる。
この「エロヒムという」言葉がいつごろ生まれたものなのかに関しては何とも言えない。あるいは「エホバ」のように紀元前2千年紀中ごろの東地中海域における相互交流の所産かも知れず、あるいは古代ユダヤ人たちがカナン(パレスチナ)に定着した後相当後期の、小アジア方面からのギリシャの影響、あるいは『聖書』にある「フィリスティア人(ペリシテ人)」などの影響、によるものかも知れない。「エホバ」と「エロヒム」に関しては、古代ユダヤ人たちの間にエホバ派とエロヒム派があったのではないかという議論もあり、それを王国の分裂にからめ北王国(イスラエル王国)をエロヒム派、南王国(ユダ王国)をエホバ派に関連させる議論もある。そうした議論で言われるような現象はけして起こり得ないことではない。しかし、エホバ派とエロヒム派なるものが人と人との関係において分裂し常に双方の人間集団(二王国)を形成しなければならないというものでもない。すなわち、「エホバの言葉こそ真理」「バアルの言葉こそ真理」、あるいはイスラム教の神「アラー」において、「アラーの言葉こそ真理」、という過程、すなわち「エホバこそエロヒム」「バアルこそエロヒム」「アラーこそエロヒム」という過程によって、エロヒムはいかなる神ともひとりの人間内部で過程として併存(並作用)し得る。(異なった次相で)並び置かれ得るのである。「אלהים(エロヒム)」も「יהוה(エホバ)」「バアル」も「アラー」も、全て言葉なのである。「(かみ)神」は言葉なのである。音覚中枢たる言語中枢の反応なのである。そして「エホバ」の言葉、「アラー」の言葉、「神」なる言葉、それがすなわち「エロヒム」なのである。エロヒムは神である。人間の意思や感情、理性や感性を超越した神である。そして言葉である。言葉の過程、言語中枢の反応過程それなのである。それは唯一絶対であり、絶対的・絶望的に自由であり、そこには何らの条件もなく、抑制もなく、そこには、全脳的抑制は無い、全脳的抑制から全く自由な、人類にとって全く未知の言語がある―――――。
唯一絶対の神への信仰は二つの神を現した。
それは二つの神への信仰でもあり一つの神への信仰でもあった。
それは絶対でもあり相対でもある神への信仰だった。
すなわち「エホバ」と「エロヒム」。
これは唯一絶対神信仰の本質を表現する。
すなわち、自分を離れ客観的に、対自的に存在化した言葉が唯一絶対の存在となることにおける(思考や感覚の、すなわち人格の)絶対的分裂と矛盾。
言葉の過程は音の過程である(言語中枢は広い意味で音覚中枢である)。言葉は音(おと)である(文字は捨象する。言葉は文字のある前からあった)。この過程は決して、視覚(見ること)、触覚(触れること)、嗅覚(嗅ぐこと)、味覚(味わうこと)等の過程を(それによる、在る、を、いうなれば存在を)代替しない。決してそれらと同価に作用しない。代替しないからこそ、それが客観的に、対自的に存在化した場合、それは(作用として)現実から切り離された、現実から自由な、絶対的な自由を得、それはすべてに、唯一絶対に、なり得た。そして、代替しないからこそ、それは(作用として)現実においてけしてすべてに、唯一絶対に、なり得ない。
絶対矛盾……。
では、言葉の過程が全宇宙・全存在である過程(いうなればエロヒムの過程:当時(たとえばイクナートンの死の直後)はまだ「エロヒム」という言葉はなかったが)にいつ、どこで、どのように、そしてなぜ、山の神・神の山(あるいは山そのもの)を崇拝する過程(いうなればエホバの過程)が融合したのであろうか。これは時期と場所に関しては、エジプト脱出後、ヨルダンを渡りカナン(パレスチナ)へ侵攻するまでの(『旧約聖書』によれば40年の)荒野での流浪期にシナイ半島からカナン南部にかけての地域のどこかで、としか言いようがないだろう。場所としては、モーセがエホバから十戒を受けたと言われるシナイ山よりも、むしろ、カデシュ・バルネアあたりでエホバの過程導入による(あるいは、退行的な古代ユダヤ人たちが神の名を欲することによる(それがエホバ、あるいは単なるホレブ、の導入をもたらした))抵抗と混乱(「民数記16」以下にあるような)があったのではないかという推測は成り立つ。抽象的思考・抽象概念思考の極致とも言うべきエロヒムの過程・対自的に存在化する言葉の過程が絶対なるものとして、それを受け容れなければ生存し得ない絶対性をもって、その強迫的な強靭なナルシシズムをもって古代のユダヤ人たちに導入されていくことには、その絶対的な自我の分裂性ゆえに、すなわち、自分が見ているこの世界と「かの世界(悟性でなければ見えない“かのもの”の世界)」、その言葉と“言葉”、物と“物”、私と“私”との根源的絶対的分裂性ゆえに、彼らには得体の知れない言い知れぬ、そして底知れぬ、不安と劇甚な抵抗が生じた筈である。この過程は古代のユダヤ人たちに底知れぬ不安を伴う強圧的な、恐ろしい抵抗を伴って作用した筈である(不安は分裂症状を警告しそれへの対処を促し迫る)。「あなた(神)の手を私の上から遠ざけてください。あなたへの恐怖―それが私をおびえさせませんように」(『旧』「ヨブ記13:21」)「彼(私、あるいは人間)の上から視線をそらしてください。彼が息むためです」(『旧』「ヨブ記14:6」)という強迫的状態である。アメリカの考古学者・旧約聖書学者オールブライトは、「オリエント世界において、パレスチナ(カナン)ほど多数の裸形女神像が出土する地はなく、中には卑猥な姿態さえあり、この地にいかに性的祭祀が深く根をおろしていたかという事実を示す」と述べた。また、カナンからは燧石製の男根なども出土する。つまり、この地では、元来、肥沃祭祀や感応魔術などと言われるような過程が一般的だったのである。古代のユダヤ人たち(正確に言えば、その後その子孫たちが「ユダヤ人」と呼ばれるようになる人間たち)はそうした官能的な人間たちだったのである。その者たちに、神への畏怖を生じさせる強迫的なナルシシズムをもって抽象的思考の極致ともいうべき過程が導入されていく。その導入の過程において、深く恐ろしい抵抗とそれからの解放衝動たる暴力の勃発や破壊や殺戮(この過程でモーセは殺されたのかも知れない)などをひき起こしつつエロヒム(当時はまだ「エロヒム」とは表現されていなかったが)はその過程を強迫的に貫徹しようとした。この貫徹の過程において、言葉の過程、抽象概念の過程、「感覚的なものは一切ともなわず」「悟性によるのでなければ見ることのできない“かのもの”」たる言葉が“在(あ)る”に、全存在それになる過程、は一気に視覚や触覚や嗅覚や味覚の過程(いうなれば、生(あ)れなる知的生命の過程、その知的生命活動が全存在の、自然なる全宇宙の、活動それとしてある過程、あらゆる外的知覚は自己の過程それであり、山や海や樹木や岩や風や雨等が自己の全知覚過程として作用する過程、外的知覚過程が内的知覚過程それであり、内的知覚過程が外的知覚過程それである調和としての総体的統合的一体的過程、精霊崇拝やアニミズムと客観的に表現される過程、世界が、空や地や海や山や川や原野や風や雨や太陽や月や星その他全存在が私の官能それである過程)―そんな過程へ向かって、エロヒムの過程が一気に退行化する。そうすることにより(そうなることにより)、最も抵抗を低減させ弱めたあり方でエロヒムが自己を貫徹させる。この退行の過程たる所産がすなわち原始的精霊崇拝的過程なるエホバの導入である。エホバを導入することにより(エホバが導入されることにより)、エロヒムの過程(対自的に存在化する言葉の過程)が自己を退行化させつつ貫徹したのである(されたのである)。そして古代ユダヤ人たちにナルシシズムが形成されていく。果てる際(きわ)無く増殖しいつ果てるとも知れぬそのナルシシズムが自己展開をはじめる。(正確に言えば、このナルシシズムの形成により「ユダヤ人」はこの世に生まれた。「ユダヤ人」という記憶はナルシシズムにより刺激された自我分裂的抵抗の所産であり、その人類史的蓄積であり増幅である)。このナルシシズムの快感は絶大である。自己はその欲望のままに創造され、自己は、「私(わたくし)」は、全宇宙、全世界、全存在の創造者となる。「私」は絶対となる。「私」の欲望や快感は絶対となり絶対の自由を得る。ユダヤ人たちは「神に選ばれた民」となる(そこにはもはや全く不安の喪われた者もいたかも知れない。不安の消失は、もはや警告が無効化し諦められたほどその原因たる状態が悪化したか、さもなければその状態が消えたのかのどちらかである。どちらの場合も、その解放感と安らぎゆえに、人はそれを「救い」と表現する)。この退行化した原始的なナルシシズムによる昂揚と強迫的なエネルギーをもって古代のユダヤ人たちは一気にカナン(パレスチナ)へと侵攻しこれを攻略する。この原始的なナルシシズムの過程が示す昂揚と圧倒的なエネルギーは、後7・8世紀には唯一絶対の神「アラー」を奉じるアラビア人らにより大サラセン帝国を現出させたりもする(もちろんそれだけが世界史的事例というわけではなく、それがナルシシズムにより現象化した主要な世界史的事例というわけでもない)。
この退行過程そのものはナルシシズムとは無関係に一般的にも生じる。たとえば、古代インドにおいて、言葉の創造源たるブラフマンがその後その信仰過程においてしだいに没落し、英雄クリシュナ伝説などを背景に成長し魚や亀やその他さまざまな姿に権化するヴィシュヌや、破壊や再生や生殖などをつかさどり『リグ・ヴェーダ』において「男根を祀る者」が批判されているにもかかわらず男性生殖器(リンガ)の姿で崇拝されたりもするシヴァが大神として興隆し、その宗教態度も非人格的対象に対する知的・精神的な「信仰(シュラッダー)」から人格的対象に対する情動的な「誠信(バクティー)」へと移行し、ヴェーダ時代には存在しなかった神像(視覚化された崇拝対象(いうなれば偶像))が徐々に作られるようになり、これに服を着せ花や香を捧げ食物を与えたりするようになっていく過程。すなわち、インド・ヨーロッパ語族と彼らが浸入する以前のインド原住者との間の相互交流によってブラフマン教とでもいうべき過程がヒンズー教と呼ばれる過程へと移行していく過程。あるいは仏教でいうなら、説一切有部(一切のダルマ(法)が実在するという説)のアビダルマ学に代表されるような僧院の煩瑣学に対する抵抗解放現象としての大乗仏教の成立。あるいは仏教がヒンズー教との相互的接触交流過程においてヒンズー的魔術呪術や神秘の過程へと移行していく過程の所産たる密教の成立。あるいは不立文字・教外別伝・直指人心・見性成仏の禅宗の成立。仏教は中国へと伝来し、六朝期においては張融という男がその死に臨んで言ったという「左手に孝経と老子を執らせよ。右手に小品(般若)と法華経を執らせよ」というこの過程においてブラフマンやダルマが「道のなるべきは常の道に非ず」へと雲散霧消する過程(法華経も退行的なものである。仏教典で治癒的な指向性があるのは般若経系のものである)。老荘思想による仏教解釈、すなわち格義仏教。あるいは「即事而真(現実の中にこそ真(まこと)がある)」という過程における智顗(ギ)による天台宗の創立。あるいは中国はもちろん日本や東南アジア方面においても生じた呪術仏教……。これらはすべてブラフマンの退行現象なのである。6世紀、日本へと仏教が公伝したときにはもはやブラフマンにはその自己治癒能力などなくなっていた。インドにおいては、ブラフマンは(すなわち言葉は)頑強にその治癒を果たし自存を果たそうと抵抗しつつも、総体的過程としてはただ一方的に退行していく(それがすなわち調和努力過程なのである:後にインドに浸透するイスラム教はここでは問題にしていない)。しかし、カナン(パレスチナ)そしてヨーロッパにおいてはそうはならなかった。インドと彼の地との過程の相異はすなわちナルシシズムの有無である。古代インドにはナルシシズム過程・一神教ナルシシズム過程はなかった。しかし、退行化したナルシシズムはけして消滅しない。彼のナルシシズムは自己のナルシシズムを満たさぬ知覚、そのナルシシズムを、絶対性を、動揺させる知覚、「私(わたくし)」に何らかの抵抗や不安や不快を感じさせる知覚に偏執的・強迫的な拒否と嫌悪を示す(彼のエロヒム(言葉、その活動)の絶対性を動揺させるその知覚が、彼の根源的な自我分裂性を(彼に)露呈し、刺激し、彼に自らがよって立つ大地が崩れていくような図り知れぬ不安を覚えさせるのである。逆に言えば、その自我分裂性を彼に対し露呈的に刺激する知覚に彼は言い知れぬ不安と憎悪を覚える。それはサタン(悪魔)となる。彼は、あらゆる物や事が唯一絶対の「私(エロヒム:言語活動)」なる物や事として現れる限りに満たされる)。そして、強迫的エネルギーと偏執的執拗さをもってその「サタン」の排除をめざす。その過程と記憶を永遠に清らかにこの地から拭い去ろうと努める。彼を衝き動かす衝動の本質は、前述した絶対矛盾の統合、唯一絶対神信仰の本質たる根源的不安をもたらす絶対的人格の、自我の、分裂と矛盾の統合・揚棄である(視点を変えて、抵抗(障り)の排除・昇華と言ってもいい。この「障り」は、ときには生命の危機を予感させるほど、その不安が生命に、すなわち死に、触れるほど、根源的である)。根源的自我分裂(Schizophrenie・精神分裂:一般に流布しているこの用語は「自我不和」と言った方が誰にでも分かりやすいかも知れない。自我(私・わたくし)が「触(ふ)れ」「さはり・触り・障り」となり、自我(私・わたくし)と自我(私・わたくし)が不和になる。この「さはり」を精神医学では「抵抗」という)―その根源的な自我分裂の言い知れぬ不安から逃れ救いと解放を求める根源的統合衝動に彼は果てしなく衝き動かされる。この人格の分裂性・自我分裂はときとして、生存の危機に触れるほどに、生命を虚無化・無意味化させる事態に陥るほどに、根源的である。すなわち、その統合衝動もまた或る場合には生命を虚無化・無意味化するほどの、人間の死をももたらすほどの、生命が全く無意味化・無価値化するほどの、虚無性をもって現れる(歴史的事実としてそうだということである:多少なりとも歴史に関心のある方なら、そうした、とりわけ宗教に起因する、全地球上各地での、大規模な虚無的・絶望的な多くの歴史的出来事はご存じだろう)。そしてその統合衝動は唯一絶対の「私(わたくし)」を、唯一絶対の神を、貫徹させ現実化させようとする過程として現れる。唯一絶対の神が、エロヒムが、「言葉」が、自己を貫徹し現実化させようとする過程として現れる(すなわち、前述の、ナルシシズムを動揺させる知覚の排除、その永遠なる清らかな拭い去り、とは、あらゆる物や事を「私」なる物や事として現す努力なのである)。唯一絶対の「私」を現実化することにより彼は自己の絶対的分裂の統合を果たそうとする。その場合、彼は自分がなぜそうなるのかは知らない。それが分裂に由来することも、その分裂がなぜ、に関しても、彼は知らない――。そうした衝動に彼は強迫的に衝き動かされる。或る場合、その衝動の現れは「伝道」と呼ばれ、彼は伝道者、予言者となる。彼はエロヒムの人、言葉の人なる。「神へ帰れ…神へ帰れ…」と彼はものに憑かれたように叫びつづけ呻きつづける。第2、第3、第4、第5のモーセが次々と現れては消え現れては消えユダヤ人その他に一神教ナルシシズムの過程をさらに拡大・強化・深化させていく。強迫的な、強靭なエネルギーをもって、偏執的な執拗さをもって……。その過程において、退行により深く傷ついた「言葉」の過程、エロヒムの過程、唯一絶対なる“かのもの”はまるで得体の知れない、未知の、巨大な獣がゆっくりとその傷を癒すかのように治癒していく。在る筈の自己へ帰り回復していく。この治癒過程は、社会において、そして歴史において、唯一絶対の「私(わたくし)」相互の闘争によりさらに促迫され推進される。教えがなされる。人々は唯一絶対の神を知る。唯一絶対の「私」を知る。社会のあらゆる「私」が唯一絶対になっていく(もちろんこれは永い歳月を要することであり、ヨーロッパ(西ヨーロッパ)でも、キリスト教が全社会的に故習的な、まるでそれが自らの生来の風俗や文化であるかのような、状態になるのはほぼ12世紀である(西暦紀元元年から考えれば1000年以上の歳月が流れている)。また、土地に関する関係(土地という対象に関する人と人との関係)で言えば、その分裂的関係の始まり、すなわち封建制(Lehensverfassung・feudalism:中国語や日本語の「封建」とは意味が異なる。地域的にはヨーロッパのライン河とロワール河に挟まれた地域。その始まりの時期を明確に確定することは困難であるが、それは土地という対象に関する人と人との関係性が王のナルシシズムにより虚無化・無意味化することから始まる。その神的信仰によって、神への畏れと敬いによって、土地関係が維持されるのである)の始まりを8世紀とするなら、(フランス)革命議会において封建制廃棄が決議・強行され私的所有権の絶対(「私」の絶対)と契約自由(「言葉」の絶対)を原則とした『ナポレオン法典』が現れたのが18世紀最末期から19世紀最初期であるから、その間約1100年(それは“かのもの”が宗教から科学へと衣を変えていく過程でもある))―。しかし、唯一絶対の神が、唯一絶対の「私」が、二つ並び立つことはあり得ない。統合衝動に衝き動かされあらゆる唯一絶対の「私」はあらゆる唯一絶対の「私」との永遠の、果てることのない、絶望的な闘争へと入っていく。そしてこの唯一絶対の神は「言葉」である。あらゆる「私(わたくし)」があらゆる物や事を唯一絶対に正しき「私」なる物や事として現す。彼は、あらゆる物や事が唯一絶対の「私(エロヒム:言語活動)」なる物や事として現れる限りに満たされる。言葉における闘争は、或る場合には礼儀正しく上品に、或る場合には無礼かつ下品に、直接間接に、交渉、議論、討論、論争となって現れる。そして言葉が限界に至るまで虚無化・無意味化したときその統合衝動は、分裂不安からの解放衝動は、暴力となって勃発する。何らかの理由により規模が大規模化すればそれは戦争である。この分裂的闘争過程は言葉を無意味化させていく過程である。唯一絶対の神が人を支配し、その本質たる絶対矛盾と分裂により、人と人との関係性・調和性は壊滅していき、言葉が人を支配し、言葉と人との関係性・調和性は壊滅していき、言葉が言葉を支配し、言葉と言葉の関係性・調和性は壊滅していき、言葉は虚無化し、無意味化していく(言葉の意味性は、音(聴覚刺激)と光(視覚刺激)の関係に現れるところの、自然現象たる普遍的な生命現象を機構としたあらゆる内的知覚・外的知覚の総合的関係性により維持される)。この過程は、「言葉」に認識の座を置き表現すれば、「言葉」が、言語活動が、現実から遊離し、切り離され、絶対的な自由を得、唯一絶対へと向かう過程でもある。すなわち、エロヒムが自己を貫徹し成就していく過程である。個人の人生の次相においても、人類文化の、すなわち人類史の、次相においても、そうした現象が相乗化しつつ進行する(個体発生が系統発生を繰り返すように、個人の人生は人類の歴史を繰り返す)。百年単位、千年単位の歳月をかけ、幾世代にもわたり永々と事態は発展的に受け継がれ、緩慢に、着実に社会において、人と人との関係において、そうした分裂的・(自然性や人間性における)破滅的過程が進行していく(多分そうなるだろうという推測ではない。人類史に現れる事実としてそうだということである)。治癒とは、エロヒムの治癒とは、そうした過程である(この治癒過程の一環として、ひとつの現れとして、「エロヒム」という神名が現れた)。エロヒムは一気に退行し自己を貫徹し拡大しそしてゆっくりとゆっくりと自己を回復し治癒していく。そしてまた退行し傷つきつつ拡大しそしてまたゆっくりと治癒していく。退行し、拡大し、治癒し、退行し、拡大し、治癒し……。そうした過程を経つつ、エロヒムは着実に拡大深化的に自己を貫徹し成就していく。その絶対的支配を着実に拡大していく。ここに言う「拡大」とは、地域的空間的な支配、同時に時間的な(個人としての、そして国家や民族や人類としての)過去(の記憶)や未来に対する支配、はもちろんのこと、その支配の深度、強度、すなわち人格への、人間の記憶や思考や感情におけるあらゆる過程への、支配の拡大深化をも意味する。この、相互に(とりわけ退行的ナルシシズムと治癒的ナルシシズムが相互に)分裂的な闘争を展開しつつ、退行し拡大深化しそしてゆっくりと治癒していくこの過程が、それへの(絶対矛盾核たるエロヒムへの)闘争をも含め、以後、いうなれば言葉教としての、一神教ナルシシズムの展開過程であり、そして人類史である(その結果、世界の歴史は、絶対矛盾を含み、分裂的に現れる。受け継がれるにつれそのエネルギー解放時の震度とマグニチュードを増しつつ、自我分裂的・精神分裂的に現れる。言うなれば、自然の歴史、全内的知覚・外的知覚調和的な、全脳的歴史と、人工の歴史、まるで脳から遊離したような、(ラカン的表現を借りれば)言語活動(ランガージュ)として構造化したような、歴史)。
ナルシシズムが自己を展開していく。たとえイクナートンが死のうと、モーセが死のうと、イエスその他が死のうと、言葉さえあれば、言葉が記憶伝承され、あるいはそれを記した文字さえあれば、そしてその言葉の過程に、ナルシシズム過程(絶対矛盾核たるそれによる絶対的闘争的な「わたくし」の分裂)、エロヒムの治癒過程、「言葉」の治癒過程、言語活動の治癒過程(偶像崇拝拒否、崇拝対象視覚化の強迫的忌避を中枢とする過程)がたとえ間接潜在的にでも、無意識暗示的にでも組み込まれていさえすれば、そうした、いわば現象核としての過程さえあれば、あとはただ自動的に事態は展開していく。まるで、目には見えない得体の知れぬ生命体のように、過程が全く自動的に自己を展開し、成長し、その支配を遂げていく。
契約の箱を、すなわち神の言葉を、担(にな)いで古代ユダヤ人たちはヨルダン河(死海北方)を渡った。それがいつ頃のことなのかは判然としない。仮に、あくまでも仮に、紀元前1330年頃にエジプトを脱出したとすれば、『旧約聖書』「民数記14:29―33、32:13」によれば彼らは40年荒野を彷徨(さまよ)い、20歳以上の人間はすべて死に、ただ幼い者だけがカナンへ入り、「申命記2:14」によれば「カデシュ・バルネアから歩き続けてゼレドの奔流の谷(死海南部沿岸東側)を渡るまでの日数は38年」だそうであり、荒野で世代が交替し荒野でエホバのもとに生まれ育った者たちの退行的強迫的エネルギーが現象を動かす力になったとすると、二世代で60年。ヨルダンを渡ったのは紀元前1280―60年頃ということであろうか。「見なさい。全地の主なる方の契約の箱があなた方の前をヨルダンに入って行きます」(『旧約聖書』「ヨシュア3:11」)。
そして歴史が始まる。時間が動き始める。
Copyright(C)書いた人